76001
計算機アーキテクチャ特論(Advanced Computer Architectures)
後学期 2−0−0 前島 英雄 教授
パソコン,ワークステーション,携帯情報機器など計算機のダウンサイジング,パーソナル化に大きな役
割を果たしているマイクロプロセッサについて,その動向,技術を実際の商用のマイクロプロセッサを例に
挙げながら論じる。また,理解を深めるため設計演習としてアーキテクチャ設計を実施する。
76003
プログラム理論(Mathematical Theory of Programs)
前学期 2−0−0 小林 直樹 助教授
プログラミング言語の様々な意味定義手法について学び,プログラムの仕様記述や検証,合成,変換など
の原理とその実際的な応用について理解することにより,プログラミング言語の形式的な取り扱いを習得す
る。
76004
知識工学(Knowledge Engineering) 西暦奇数年度開講
後学期 2−0−0 徳永 健伸 助教授
コンピュータを用いた知識の利用方法としては大きく分けて以下の2つのアプローチが考えられる。ひと
つは知識をコンピュータが扱える形式に変換し,コンピュータに推論させることによって利用するアプロー
チである。知識ベースの構築技術やエキスパートシステムがこのアプローチに関係する。一方,知識を人間
が理解できる形式のままで蓄積し,人間が必要とする知識を効率よく検索するためにコンピュータを利用す
るアプローチも考えられる。いわゆる情報検索と呼ばれる技術がこれに当たる。本講義では,これら2つの
アプローチを対比させ,それぞれの技術を紹介しながら,コンピュータで知識を扱うことの諸問題について
論じる。
76005
フォールトトレラントシステム論(Fault Tolerant Systems)
後学期 2−0−0 米田 友洋 教授・権藤 克彦 助教授
システムの故障が及ぼす影響を阻止し,高い信頼性を持つフォールトトレラントシステムを実現するため
に,システム構成と回復,誤り検出,分散システムのフォールトトレランス,テスト生成,検証等の技術に
ついて詳論する。
76006
並行システム論(Concurrent System Theory)
前学期 2−0−0 米崎 直樹 教授
並行処理を記述するための概念と形式化の手法を,代数的な立場と論理的な英語講義立場から学ぶことを
目的とする。さらに,そのような形式化を用いて,並行システムの検証や設計を行う方法についても学ぶ。
76007
ソフトウェア設計論(Software Design Methodology)
前学期 2−0−0 権藤 克彦 助教授・米田 友洋 教授
オブジェクト指向ソフトウェア設計法についてその手法,特徴などを理解する。実際にUML記法に基づ
いたCASEツールを利用し,小規模な例題プログラムの分析/設計を行い,各自がその結果を発表し,比較,
議論する。
76008
人工知能特論(Advanced Artifical Intellingence) 英語講議
後学期 2−0−0 篠原 浩一 助教授
人工知能基礎で学んだ基盤技術に基づき,さらに高度な理論や技術を学ぶ。最新の研究成果についても紹
介するとともに推論機構特論,ヒューマンインタフェース,機械学習の各講義への導入および認知科学など
の関連する分野についても概説する。
76009
マルチメディア情報処理論(Multi-media Information Processing)
前学期 2−0−0 亀井 宏行 教授・斎藤 豪 助教授
画像音声情報の分折,圧縮のためデジタル信号処理技法,画像音声認識のための特徴抽出,パターンマッ
チング手法について学ぶ。
76010
オペレーティングシステム特論(Advanced Operating Systems)
後学期 2−0−0 渡部 卓雄 助教授
具体的なオペレーティングシステムの事例を通してオペレーティングシステムの設計論を学ぶ。最近の分
散オペレーティングシステムの話題についても触れる。
76011
空間情報論(Theory of Pseudo Biorthogonal Bases) 西暦偶数年度開講
前学期 2−0−0 小川 英光 教授
信号,画像,パターン情報を統一的に取り扱うために開発された擬似双直交性理論を学ぶことにより,問
題のとらえ方,数学的定式化の仕方,理論体系の構築の仕方等を身につける訓練をするとともに,理論体系
の美しさを味わえる感性を磨く。
76012
自然言語処理特論(Natural Language Processing)
前学期 2−0−0 田中 穂積 教授
自然言語をコンピュータで解析し,理解させる研究が重要になってきている。日本語を具体例として取り
上げ形態素・統語解析・意味解析の諸技法を学ぶ。また,その応用についても説明する。
76013
パターン情報処理(Pattern Information Processing)
後学期 2−0−0 杉山 将 助教授
本講義では,数値的情報,曖昧な情報,非記号的情報,そして人間が無意識的に行なっている非論理的情
報処理手続きを工学的に扱うための枠組について学ぶ。
76015
計算環境論(Foundations of Computing Environments)
後学期 2−0−0 徳田 雄洋 教授 英語講義
現代的な計算環境は,ネットワーク,オペレーティングシステム,データベース等の並行型システムや分
散型システムによって支えられている。これらの並行型システムおよび分散型システムのための基本的アル
ゴリズムの設計原理を解説する。
76016
ソフトウェア論理学(Logic and Software)
前学期 2−0−0 西崎 真也 助教授
論理による証明は,情報を伝達,構成するプロセスと見なすことができる。このよう考え方とその応用に
ついて習得すると同時に,ソフトウェアの分野に特有の様々な論理体系について理解することを目的とする。
76017
機械学習(Machine Learning)
後学期 2−0−0 村田 剛志 講師(非常勤)・佐藤 泰介 教授
人工知能における学習手法について論ずる。学習における入力データや得られる知識の表現として,決定
木やルールなどの基本事項を学ぶとともに,知識発見や構造を持ったデータからの学習などの応用について
も考察する。
76018
コンピュータグラフィックス(Computer Graphics)
前学期 2−0−0 中嶋 正之 教授
CAD/CAM,科学,工学,医用,芸術,ゲーム等の分野において広く利用されるようになってきたコンピ
ュータによる映像・画像生成の技法について学ぶ。また関連するディジタル画像処理や符号化アルゴリズム
についても紹介する。なお,偶数年は,主に日本人学生を対象として日本語,奇数年は主に留学生を対象と
して英語により講義する。従って,2004年は,全て日本語により行う。
76019
符号理論特論(Advanced Coding Theory)
前学期 2−0−0 藤原 英二 教授
符号理論の計算機への応用の現状と実用的な符号設計理論について講義する。計算機システムにおける故
障,誤りの傾向をもとに,プロセッサシステム,高速半導体メモリシステム,磁気/光ディスクメモリシス
テム,テープメモリシステムを指向した符号の設計理論を詳述する。
76022
推論機構特論(Machine Inference)
前学期 2−0−0 佐藤 泰介 教授・村田 剛志 講師(非常勤)
述語論理の完全性定理/不完全性定理について解説し,人工知能で良く使われる融合法,項書換えなど演
繹的体系の手法を学ぶ。また同時に確率的推論の基礎としてベイジアンネットについて講義する。
76023
計算言語学(Computational Linguistics) 西暦偶数年度開講
後学期 2−0−0 徳永 健伸 助教授
本講義では,自然語処理特論の受講を前提とし,すでに学んだ自然言語文の解析技術の背景にある言語理
論の基礎について述べ,自然言語処理特論では扱わなかったテクストや談話の扱いについて紹介する。
76024
ソフトウェア工学特論(Advanced Software Engineering)
後学期 2−0−0 佐伯 元司 教授
ソフトウェアの生産性を向上させるための種々な工学的手法について概説する。特に,開発プロセスのモ
デル化手法,マネジメント手法,再利用法,テスト手法について,最新の技術及びその現状について学習し,
実際的な適用法を習得する。
76025
ヒューマンインタフェース(Human Interfaces) 英語講義
前学期 2−0−0 古井 貞熙 教授
ヒューマンインタフェースのデザイン・構築技術と評価技術を論じる。基礎として,マルチモーダルイン
タフェースの動向,認知工学と人間工学の最新の知見,人間の情報処理モデルを講義し,それらに基づいた
デザインのあり方と評価技術を論じる。最後に次世代ヒューマンインタフェースを展望する。
76026
情報認識特論(Advanced Pattern Recognition and Learning) 西暦奇数年度開講
前学期 2−0−0 未 定
パターン認識,画像処理,機械学習等にまたがる広大な分野の基本概念の一つである推定・予測の問題を,
逆問題の立場から統一的に論じることにより,問題の定式化の仕方がいかに重要であるかを示す。
76027
音声情報処理特論(Speech Information Processing) 西暦奇数年度開講
後学期 2−0−0 古井 貞煕 教授 英語講義
音声に含まれる種々の情報を統一的に処理する概念と原理,音声情報の圧縮法,合成法,認識法等につい
て講義する。特に,統計的モデルに基づいた音声分析法,音声符号化法,音声合成法,音声認識法,話者認
識法,統計的音声言語モデルなどに重点をおき,最近の応用技術についても紹介する。
76028
自律分散システム(Autonomous Decentralized System)
前学期 2−0−0 森 欣司 教授
成長・変動し続ける大規模システムにおけるニーズと技術課題を明らかにし,その解決手段として自律分
散システムを講義する。具体的には,自律分散システムコンセプトと,それに基づくシステムアーキテクチ
ャ,自律通信技術,自律駆動技術,稼働中の拡張・保守技術などについて述べる。さらにこれら技術の実適
用例についても言及し,システム技術の展開能力の向上の一助とするため,見学,討論を交えて講義を進め
る。
76029
データ工学特論(Advanced Data Engineering)
後学期 2−0−0 横田 治夫 教授
データ工学は,データベース処理に代表されるような,格納された不揮発の大量データに対する高度処理
に関する研究分野で,計算機システムの大きな利用分野の一つである。大量データを対象とするため,高速
化が重要であり,いろいろなレベルで並列/分散化等の試みが行われている。本講義では,大量データ処理
のためメカニズム,アルゴリズム,アーキテクチャについて評論する。
ネットワークプログラミング特論(Advanced Network Programming)
後学期 2−0−0 望月 祐洋
インターネットを利用したネットワークアプリケーションを設計・開発するための知識および手法を,講
義とプロジェクト形式のグループ実習を交えつつ実践的に学ぶ。講義部分では,ソケットプログラミング,
RPCプログラミング,RMIプログラミング,Webサービスプログラミング,移動コード/エージェントプログ
ラミング等を採り上げる。講義全体を通じて,複数の通信プリミティブの設計思想・抽象化の相違や長所・
短所について実感・考察する。
76031
情報セキュリティ特論(Advanced Information Security)
後学期 2−0−0 丸山 宏 講師(非常勤)・江藤 博明 講師(非常勤)・工藤 道治 講師(非
常勤)
情報セキュリティは領域が広く,どこか一部だけでも弱い点があるとそこが破られる。したがって,情報
セキュリティを確保するためには,幅広いセキュリティ知識が必要である。この講義では特定のエリアに固
執することなく,必要な知識をバランス良くカバーすることを目標とする。
75015
計算量理論(Computational Complexity Theory)
前学期 2−0−0 数理・計算に従う。
数理・計算科学専攻の教授要目を参照のこと。
75001
計算機支援数理(Mathematical Models and Computer Science)
後学期 2−0−0 小島 政和 教授
数理・計算科学専攻の教授要目を参照のこと。
75003
ソフトウェア界面(Human Interfaces in Computing Systems)
後学期 2−0−0 松岡 聡 教授
教理・計算科学専攻の教授要目を参照のこと。
77016
広領域知識ベース特論(Theory & Applications of Wide Areal Knowledge-Base)
後学期 2−0−0 大佛 俊泰 助教授
情報環境学専攻の教授要目を参照のこと。
|
75102 |
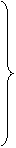
|
情報環境学専攻の教授要目を参照のこと。 |
|
インターネットインフラ特論 |
||
|
前学期 2−0−0 太田 昌孝 |
||
|
75103 |
||
|
インターネット応用特論 |
||
|
後学期 2−0−0 太田 昌孝 |
76711〜76712
|
計算工学特別実験第一 |
前学期 |
0−0−2 |
 |
各教官 |
76711 |
|
同 第二 |
後学期 |
0−0−2 |
76712 |
専攻しようとする分野に関連のある高度の実験を行うものである。
76701〜76704
|
計算工学講究第一 |
前学期 |
1単位 |
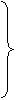
|
各教官 |
76701 |
|
同 第二 |
後学期 |
1 〃 |
76702 |
||
|
同 第三 |
前学期 |
1 〃 |
76703 |
||
|
同 第四 |
後学期 |
1 〃 |
76704 |
76801〜76806
|
計算工学講究第五 |
前学期 |
2単位 |
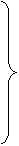 |
各教官 |
76801 |
|
同 第六 |
後学期 |
2 〃 |
76802 |
||
|
同 第七 |
前学期 |
2 〃 |
76803 |
||
|
同 第八 |
後学期 |
2 〃 |
76804 |
||
|
同 第九 |
前学期 |
2 〃 |
76805 |
||
|
同 第十 |
後学期 |
2 〃 |
76806 |
専攻しようとする分野に関連ある専門書,文献につき輪読,討論を行うものである。