〔教 授 要 目〕 (電気電子工学専攻)
50101
電磁波特論(Advanced Electromagnetic Waves)
前学期 2−0−0 ○安藤 真 教授・広川 二郎 助教授
電磁界解析の基礎として,マクスウェルの方程式の一般的解法について講義する。内容の概略は以下のと
おりである。講義は英語で行う。
1. 微小ダイポールからの放射
2. マクスウェルの方程式の導出と解釈
3. 電磁界の積分表示
4. 電磁界の等価定理
5. 境界条件,端点条件,放射条件
6. 波源のない斉次方程式の解
7. 変数分離によって解ける境界値問題
8. 半無限導体板の回折現象
9. 円筒導体による回折現象
Advanced Electromagnetic Waves
Spring Semester (2-0-0)
Prof. Makoto ANDO and Assoc. Prof. Jiro HIROKAWA
Derivation and interpretation of Maxwell's equations, radiation from a dipole, direct integration
the field equations, field equivalence theorem, boundary, edge and radiation conditions, Solutions
for homogeneous equations, canonical problems sloved by separation of variables and diffraction from
a half plane or a cylinder
50102
無線通信工学I(Wireless Communication Engineering I)
前学期 2−0−0 荒木 純道 教授
国際大学院コースで学ぶ学生を対象として,無線通信システムの諸技術を学ぶ。具体的内容は,波動伝搬,
散乱,フェージング,アンテナ,空間信号処理,変復調方式,符号化,多重化,等化技術,高周波デバイス,
高周波回路設計,多重化方式,将来動向などである。講義は英語で行う。
Wireless Communication Engineering I
Spring Semester (2-0-0)
Prof. Kiyomichi ARAKI
Wireless Communication Systems; Wave propagation, reflection, refraction and diffraction;
Stochastic Behavior of wireless channel; Antenna and Diversity; Space and Time Signal Processing;
Modulation and Demodulation; Coding and Decoding; RF Devices and Circuit Design; Multiple Access;
Software defined radio; UWB transmission
50133
無線通信工学II(Wireless Communication Engineering II)
前学期 2−0−0 村田 英一 助教授
無線通信システムの基礎について講義する。具体的には,符号化変調,FDMA,TDMA,CDMA,空間多重,マ
ルチユーザ受信,セルラ方式,マルチホップ無線ネットワークなどである。
50105
導波回路論(Guided Wave Circuit Theory)
前学期 2−0−0 水本 哲弥 助教授
マイクロ波集積回路や光集積回路用の導波路,光ファイバにおける導波現象,モード結合などを説明し,
結合回路,合分波器,非相反回路などの基本的な電磁波回路,光波回路の動作原理,設計法について講義す
る。
Guided Wave Circuit Theory
Spring semester (2-0-0)
Assoc. Prof. Tetsuya MIZUMOTO
The lecture will be focused on the guided wave theory and its application to the design of guided
wave circuit in microwave, millimeter-wave and optical regime. Topics included are electromagnetic
wave in waveguides, dispersion in an optical fiber, coupled mode theory, electromagnetic wave in a
periodical structure, scattering matrix representation, eigen excitation, and the design of some guided
wave circuits.
50106
光通信工学(Optical Communications)
後学期 2−0−0 荒井 滋久 教授
光伝送工学の基礎,光ファイバ伝送路の特性,発光素子,光増幅器,検波器などの光デバイスの特性と受
信雑音,光回路および光伝送システムの特徴等について講義する。
50107
プラズマ工学(Plasma Engineering)
前学期 2−0−0 石井 彰三 教授
I. 電子とイオンから構成され,電気的に中性な電離気体であるプラズマは現代の工学において重要な役割
を果たしている。プラズマを取り扱う理論と考え方は,電気電子工学の広い範囲にわたって共通なものが
多い。本講義ではプラズマ物理の基礎から,プラズマの発生,計測,応用など工学的側面までを学ぶ。
II. 電磁界中における荷電粒子の運動,プラズマの粒子的取り扱い,プラズマの流体的取り扱い,衝突と輸
送現象,プラズマの閉じ込め,プラズマ中の波動,プラズマ計測,プラズマの応用
50108
パワーエレクトロニクス特論(Advanced Course of Power Electronics)
前学期 2−0−0 藤田 英明 助教授
半導体制御素子を用いて電力の変換,制御などを行う分野―パワーエレクトロニクスについて,その応用
と技術動向について講述する。具体的内容として,電力用半導体素子(GTO,MOSFET,IGBT)の応用,整流回
路の特性改善,インバータ,交流電力調整装置,高調波及び無効電力補償装置,自励式整流回路,最新の技術
動向,を取り扱う。
50109
電力・電機システム解析(Electric Power and Motor Drive System Analysis)
後学期 2−0−0 赤木 泰文 教授
電力システム,モータ駆動システムなどの特性を知るために必要な解析手法とその応用について講述する。
電力・回転機制御システムの解析手法概要,交流回路の解析法・三相交流の取扱い,電力の取扱い,有効電
力と無効電力,座標変換法,回転機の基本式と等価回路,回転機制御の基礎,誘導電動機の制御。
Electric Power and Motor Drive System Analysis
Spring Semester (2-0-0)
Prof. Hirofumi AKAGI
This lecture is focused on analysis of electric power systems and motor drive systems, and on their
applications. It includes the p-q theory in three-phase circuits, and the instantaneous active and
reactive power defined by the theory, as well as d-q transformation for ac motors. In addition, it
presents the so-called vector control or filed-oriented control for induction and synchronous
motors.
50110
システム制御工学(Systems Control Engineering)
後学期 2−0−0 高橋 宏治 助教授
システムの複雑化や要求する制御内容の高度化にともない,種々の新しい制御手法が発展している。電気・
情報系の関連する分野において,これらの制御手法を有機的に応用することを主題として講義する。
物理システムから人工システムまで,量の制御から手順の制御までを扱う。フィードバック制御に関す
る基礎知識をもっていることが望ましい。
50111
電力工学特論(Advanced Electric Power Engineering)
後学期 2−0−0 猪野 博行 講師(非常勤)・市川 元保 講師(非常勤)
水力・火力・原子力発電,電力系統の周波数,電圧の制御,電力系統の経済運用,系統保護,直流送電,
電力用通信技術,その他電力事業における最近の話題,ならびに電力機器と電力分野における新技術開発に
ついて講述する。
50130
パワーデバイス特論(Advanced Power Semiconductor Devices)
後学期 2−0−0 大橋 弘通 教授・小倉 常雄 講師(非常勤)・
大村 一郎 講師(非常勤)・四戸 孝 講師(非常勤)
MOSFET,IGBT(Insulated−Gate Bipolar Transistor),GTO,サイリスタなどのパワー半導体デバイス
の構造,動作原理,特性,設計理論について講義する。特に,デバイス構造・設計に着目し,信号処理を目
的とした半導体デバイスとパワーデバイスの相違点を論じ,その基本設計法の習得をはかる。さらに,次世
代の半導体材料として注目されているシリコンカーバイド(SiC)と,そのパワー半導体デバイスへの応用の
可能性についても講述し,将来の発展方向を示す。
50112
パルスパワー工学(Pulsed Power Technology)
後学期 2−0−0 安岡 康一 助教授
パルスパワー工学は高電圧工学から発展したもので,高密度プラズマ,大出力レーザー,大強度荷電粒子
ビームなどの発生を可能にし,近年では環境改善機器といった新たな産業応用を生み出している。この急速
に発展してきた大電力短パルスに関する工学について,基本原理を説明し,応用例についても講述する。
50127
エネルギー・マネージメント特論(Energy Management)
前学期 2−0−0 七原 俊也 教授
社会の根幹を支えるエネルギーについて,エネルギー需要動向,地球環境問題,分散型電源など新エネル
ギーの開発動向,電力自由化,大規模電源,電力系統新技術,エネルギー・情報複合システム,循環型社会
の構築,など多角的な視点から述べる。その上で,大規模集中電力輸送システムと中小型分散型システムの
協調システムによるエネルギーの有効利用システムの重要性を講義する。
50129
マイクロプロセッサ設計特論(Design for High-Performance and Low-Power Microprocessors)
後学期 2−0−0 内山 邦男 教授・荒川 文男 講師(非常勤)
90年代の後半に開発されたデジタル民生機器向けマイクロプロセッサを例題にしながら,マイクロプロセ
ッサのアーキテクチャ,論理,回路の設計について次の項目に沿って講義を進める。(1)マイクロプロセッサ
の技術動向,(2)アーキテクチャ設計,(3)高性能化のための論理方式とその実装,(4)低消費電力化技術とその
実装
56009
アナログ集積回路(Analog Integrated Circuits)
後学期 2−0−0 高木 茂孝 教授
集積システム専攻の教授要目を参照のこと。
56007
信号処理特論(Advanced Signal Processing)
前学期 2−0−0 西原 明法 教授
集積システム専攻の教授要目を参照のこと。
56006
移動通信工学特論(Advanced Topics in Mobile Communications)
後学期 2−0−0 鈴木 博 教授・府川 和彦 助教授
集積システム専攻の教授要目を参照のこと。
54711〜54712
|
電気電子工学特別実験第一 |
前学期 |
0−0−2 |
 |
各 教 官 |
|
同 第二 |
後 〃 |
0−0−2 |
(Special Experiments I and II on Electrical and Electronic Engineering)
専攻しようとする分野に関連のある高度の実験を行うものである。
54701〜54704
|
電気電子工学講究第一 |
前学期 |
1 単 位 |
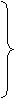 |
指導教官 |
|
同 第二 |
後 〃 |
1 〃 |
||
|
同 第三 |
前 〃 |
1 〃 |
||
|
同 第四 |
後 〃 |
1 〃 |
(Seminar I〜IV on Electrical and Electronic Engineering)
専攻しようとする分野に関連ある専門書,文献につき,輪読,討論を行うものである。
54801〜54806
電気電子工学講究第五 |
前学期 |
2単位 |
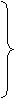 |
指導教官 |
|
同 第六 |
後 〃 |
2 〃 |
||
|
同 第七 |
前 〃 |
2 〃 |
||
|
同 第八 |
後 〃 |
2 〃 |
||
|
同 第九 |
前 〃 |
2 〃 |
||
|
同 第十 |
後 〃 |
2 〃 |
(Seminar V〜X on Electrical and Electronic Engineering)
いずれも博士後期課程における授業科目であって,それぞれ示した期間に履修しなければならない。この
内容は博士後期課程相当の程度の高い輪講,演習,実験,等より成るものである。
54501〜54506
電気電子工学特別講義第一〜第六(Special Lecture I〜VI on Electrical and Electronic Engineering)
前・後学期 各1〜2単位 各 教 官
各教官がそれぞれ専攻する分野において,特殊の題目を選択して随時開講するものである。