〔教 授 要 目〕 (電子物理工学専攻)
50113
電子物性論A(Electronic Materials A)
前学期 2−0−0 ○阿部 正紀 教授・中川 茂樹 助教授
量子力学的観点から固体の電子物性を講義する。量子論の基礎を復習した後に,量子力学の近似解法(摂
動論)を学ぶ。これを電磁波の吸収・放出課程に応用する。さらに電気伝導および超伝導の基礎を講義し,
超伝導応用デバイスについて学ぶ。また講義内容に関する演習を適宜行い理解を深める。
Electronic Materials A
Spring Semester (2-0-0)
Prof. Masanori ABE and Assoc. Prof. Shigeki NAKAGAWA
Electronic properties of solids are lecturecd based on quantum mechanics. Beginning with fundamentals
of quantum mechanics, perturbation theory, an approximate method, is given. It will be applied to
electromagnetic radiation in solids. Also, fundamentals of superconductivity are given, which are
extended to superconductivity devices.
Exercises are carried out during the class to help understanding.
50114
電子物性論B(Electronic Materials B)
前学期 2−0−0 ○阿部 正紀 教授・真島 豊 助教授
結晶学の基礎(格子と点群対称性)を学び,結晶のテンソル物理量(電気的,磁気的,弾性的,光学的定
数)を導出する。また,結晶物性の基礎として結晶解析法,格子振動を学び,結晶解析手段であるX線の基
本を学ぶ。
Electronic Materials B
Spring Semester (2-0-0)
Prof. Masanori ABE and Assoc. Prof. Yutaka MAJIMA
Fundamentals of crystallography, including lattice and point symmetry, are given to introduce
physical tensors (electric, magnetic, elastic optical, etc.) of crystals. Principles of
crystal-structure analyses and phonon vibrations are introduced, with Which fundamentals of
methodologies for crystal-structures analyses using X-ray, are given.
50115
電子物性論C(Electronic Materials C)
後学期 2−0−0 ○小長井 誠 教授・山田 明 助教授
半導体や金属の電気伝導の基礎,半導体中の少数キャリア再結合過程などについて学んだ後,フォノンに
関連した比熱,熱伝導,ラマン散乱などの物性を学習する。ついでキャリア散乱機構と移動度,有効質量,
磁界中でのキャリアの振る舞いなどのキャリア輸送現象に関連した物性を学ぶ。また,半導体の光吸収過程,
発光過程などについて学んだ後,半導体ヘテロ接合のエネルギー準位や電流輸送現象を学ぶ。
50116
電子物性論D(Electronic Materials D)
後学期 2−0−0 ○岩本 光正 教授・中川 茂樹 助教授
磁性材料および有機電子材料の基礎を,物質の磁性と誘電,導電性に関する理論から学ぶ。磁化,分極と
導電性など物質の性質と機能がどのようにして発現するかを学び,関連の電子材料についての理解を深める。
1. 磁性材料の基礎物性(磁気モーメント,各種磁性,実用磁気特性)
2. 有機電子材料の基礎物性と電子・光機能(誘電性・導電性,電子機能,光電子機能,光非線形性)
Electronic Materials D
Autumn Semester (2-0-0)
Prof. Mitsumasa IWAMOTO and Assoc. Prof. Shigeki NAKAGAWA
Fundamentals and advanced theories of magnetic properties and dielectric properties for the better
understanding of ferro- and ferri- magnetic materials and dielectric and ferroelectric materials.
Origins of magnetic moment, its alignment and anisotropy, electronic and optical properties in advanced
organic materials.
50117
先端電子材料(High-Tech Electronic Material)
前学期 2−0−0 ○阿部 正紀 教授・小長井 誠 教授・岩本 光正 教授
中本 高道 助教授・中川 茂樹 助教授・山田 明 助教授
真島 豊 助教授・サンドゥー・アダルシュ 助教授
エレクトロニクスの急速な進展と共に,高密度記録材料,分子機能材料,量子波材料などの先端電子材料
が注目されている。そこで,本講義では,最近の先端材料についての動向を紹介しながら,これらの材料が
半導体物性,磁性体・誘電体物性,量子物性を基礎としてどのように進展しているかを学ぶ。特に,磁気・
光記録,分子膜,生体材料,半導体超薄膜,アモルファス材料などエレクトロニクスに関係の深い話題を取
上げる。
50118
半導体デバイス特論I(Advanced Semiconductor Devices I)
前学期 2−0−0 杉浦 修 助教授
MOSトランジスタの動作原理を理解し,物性定数ならびに構造パラメータがトランジスタ特性にどのよ
うな影響を与えるか説明できる能力を身につける。特に,短チャネル化効果について学び,大規模集積回路
を構成するトランジスタの抱える問題とその解決手段を理解する。
50119
半導体デバイス特論II(Advanced Semiconductor Devices II)
後学期 2−0−0 宮本 恭幸 助教授
本講義では,MOS以外の高速電子デバイスとして,バイポーラデバイスや化合物半導体デバイスの動作と
その高速化の条件を学ぶ。また高速化実現を可能にするための微細デバイス作製のプロセス技術について,
その原理と限界も示す。学部において「電子デバイス」「半導体物性」「基礎電気回路」を,大学院において「
半導体デバイスI」を,履修していることを前提として講義を行う。
50120
先端電子デバイス(Advanced Electron Devices)
後学期 2−0−0 小田 俊理 教授
I. 固体電子デバイス・材料に関する最近の話題について講述する。
II. 半導体デバイスの微細化・集積化,高速化の限界。量子効果デバイス。超伝導デバイス。
Advanced Electron Devices
Autumn Semester (2-0-0)
Prof. Shunri ODA
Limitation of silicon microdevices and alternative technology: Quantum nano-devices, will be
discussed.
Major topics include; Approaches for high-speed devices, Parameters which determine the speed of
ICs, Heterojunction devices, Scaling limit of MOSFETs, Interconnections, Criteria for quantum effects,
Fabrication technology of quantum nano-structures, Single electron transistors, Superconducting
digital devices, Quantum computer.
50136
先端電子デバイスシミュレーション(Advanced Electron Device Simulation)
後学期 2−0−0 水田 博 助教授
本講義では,サブミクロンからナノメータスケールの電子デバイスに対する数値シミュレーション技術の
基礎理論と,それを用いた先端電子デバイスの設計・解析の実際について学ぶ。
半導体のキャリア輸送方程式,ドリフト・拡散法,エネルギーバランス法,モンテカルロ法,およびそれら
基本方程式の数値解析手法と,シリコン・化合物半導体デバイスへの適用法を習得する。さらに,最近の量子効果
デバイスに対する散乱行列計算と量子輸送シミュレーションの最前線について論じる。
Advanced Electron Device Simulation
Autumn Semester (2-0-0)
Assoc. Prof. Hiroshi MIZUTA
This course gives the fundamental theory of numerical simulation technologies for submicron- and
nanometer-scale electronic devices and discusses their applications to design and analysis of advanced
electron devices. It includes study of semiconductor carrier transport equation, drift-diffusion method,
energy-balance equation method, Monte Carlo method, numerical solution techniques for those semiconductor
equations, and their applications to silicon and compound semiconductor devices. The scattering matrix
calculation and quantum transport simulation are also studied for recent quantum functional devices.
50121
VLSI工学(VLSI Technology)
前学期 2−0−0 ○松澤 昭 教授・古山 透 講師(非常勤)・渡辺 重佳 講師(非常勤)
畝川 康夫 講師(非常勤)・天川 博隆 講師(非常勤)
河野 和義 講師(非常勤)・宮森 高 講師(非常勤)
I. システムオンチップ(SOC)時代を支える大規模集積回路(VLSI)の基本技術について説明し,VLSI
技術の理解を深める。
II. 1. システムLSI概論(1回)
2. 低電力・高速化技術(2回)
3. マルチメディア用システムLSI(3回)
4. メモリLSI(DRAM/SRAM/Flash/混載,等)(2回)
5. CMOSアナログ回路と混載技術(2回)
6. 設計技術(機能合成,論理合成)(1回)
7. 製造技術(デバイス,リソグラフィ,配線,等)(2回)
8. システムLSIの将来展望(1回)
50122
情報ストレージ工学(Information Storage Engineering)
後学期 2−0−0 ○杉田 愃 講師(非常勤)・杉江 衛 講師(非常勤)
ディジタルシステムにおける情報ストレージ技術を対象とし,そこで使用される磁気記録,光記録(光磁
気,相変化,有機膜応用などを含む)などの書き込み・読み出し動作原理,記録媒体,センシング技術から
ディスクアレイなどのファイルメモリシステムに関する基礎知識を修得する。
50123
光・量子電子工学(Optical and Quantum Electronics)
前学期 2−0−0 古屋 一仁 教授
本講義は,光と物質の相互作用,およびナノメートルサイズ構造における電子の量子現象を扱う。屈折率と
吸収の関係および光増幅現象,有効質量近似方程式,電子状態の量子化,コンダクタンスの量子化,電子波
共鳴構造の負性微分抵抗特性,等を導き,これに基づいてレーザ,量子構造レーザ,および量子効果電子デバ
イスについて講義する。
50124
電子計測論(Electronic Measurement)
前学期 2−0−0 中本 高道 助教授
各種物理量・化学量を検出するセンサ,計測回路,信号処理法について述べ,これらを用いた計測システ
ムの構成法について論じる。
1. センサの動作原理(物理量センサ,化学量センサ)
2. マイクロマシーニング,集積化センサ
3. センサ用計測回路(アナログ回路,ディジタル回路)
4. センサ信号処理法(スペクトル解析,多変量解析,ニューラルネットワーク)
5. センシングパラダイム
50125
非線形ダイナミカルシステム論(Nonlinear Dynamical Systems)
後学期 1−0−0 ○田中 尚樹 教授・川口 英夫 助教授
各種の非線形現象を統一的に理解する手法を学ぶとともに,それが実際の例にどのように応用されるかを
学ぶ。力学系の基礎,非線形システムの解析法(アトラクタの次元,リアプノフ指数の計算,実験データ解析
法(埋込み)など)について解説し、続いて非線形系の代表例である脳神経系について述べる。入門的解説に
加えて、前半で学んだ方法を脳神経系に応用した例を紹介する。
50126
電子回路特論(Advanced Electronic Circuits)
前学期 2−0−0 藤井 信生 教授
学部の電子回路を基礎にして,更に高度なアナログ電子回路の理論と技術について詳述する。
1. 能動機能素子のモデル化 2. 能動回路の一般解析法 3. 回路関数と回路の安定性 4. 素子感
度 5. 帰還回路理論 6. アナログフィルタ 7. 能動RCフィルタ 8. スイッチトキャパシタフ
ィルタ
Advanced Electronic Circuits
Spring Semester (2-0-0)
Prof. Nobuo FUJII
On the basis of Circuit Theory and Analog Electronic Circuits of under graduate course, this course
provides general consideration on electronic circuits leading to advanced discussion on analog
integrated circuits, integrated filters, and switched capacitor filters.
1. Modeling of active elements by nullators and norators
2. General analysis of active circuits
3. Zeros and poles of network functions and stability of circuits
4. Sensitivity and optimum design of circuits
5. Feedback Amplifiers
6. Analog Filters
7. Active filters
8. Switched Capacitor Filters
50135
アナログ・デジタルシステムと集積回路(Mixed Signal systems and integrated circuits)
後学期 2−0−0 松澤 昭 教授
学部の電子回路とシリコンデバイスを基礎として,現代のエレクトロニクスで最も重要な技術となっている,
アナログ・デジタルシステムとその集積回路技術について,システムの理解,CMOS回路設計技術,デバイス
技術,LSI設計手法について学ぶ。
1. アナログ・デジタル混在システム 2. 高速A/D・D/A変換器 3. ΣΔ型A/D・D/A変換器 4. PLL
とその関連システム 5. 無線システム 6. 無線システムの構成ブロックと回路設計
Mixed Signal systems and integrated circuits
Autumn Semester (2-0-0)
Prof. Akira MATSUZAWA
On the basis of Electronic Circuits and Device for under graduate course, this course provides
general consideration on mixed signal system and its integrated circuit technology which becomes
the most important technology in current electronics. Basic understandings on mixed signal systems,
CMOS circuit design, device technology, and LSI design, will be covered.
1. Mixed signal systems 2. High speed A/D and D/A converters 3. Sigma delta A/D and D/A converters
4. PLL and related systems 5. Wireless systems 6. Building blocks and circuit design for wireless
systems
56009
アナログ集積回路(Analog Integrated Circuits)
後学期 2−0−0 高木 茂孝 教授
集積システム専攻の教授要目を参照のこと。
56007
信号処理特論(Advanced Signal Processing)
前学期 2−0−0 西原 明法 教授
集積システム専攻の教授要目を参照のこと。
56006
移動通信工学特論(Advanced Topics in Mobile Communications)
後学期 2−0−0 鈴木 博 教授・府川 和彦 助教授
集積システム専攻の教授要目を参照のこと。
50132
Fundamentals of Technical English for Electrical and Electronic Engineers
後学期 2−0−0 サンドゥー アダルシュ 助教授・ジョン バニエッキ 講師(非常勤)
The lectures will be given in English with supplementary material available in Japanese.
電気電子系の大学院生が国際学会発表および英語論文執筆の際に要求される「科学技術英語力」を深める。
構成:(1)和英・英和技術翻訳を行う。(2)長い英文書を100単語以内にまとめる。(3)英文で書かれている
電気電子回路,電気磁気学,固体物理,数学等に関する問題を解く。(4)最近の技術の課題に関するデベート
を行う。(5)英文論文を書くと共に自分の研究テーマについて英語で発表する。
Fundamentals of Technical English for Electrical and Electronic Engineers
Autumn Semester (2-0-0)
Assoc. Prof. Adarsh SANDHU and John Baniecki
This course is intended for graduate students studying electrical and electronic engineering
wishing to improve their ability to write technical papers and make presentations at international
conferences. Structure of the course: (1) translating technical papers from Japanese into English;
(2) writing abstracts by summarizing long technical passages; (3) solving English language problems
on electrical circuits, electromagnetism, material science, and mathematics; (4) English language
debate on recent developments in science and technology; (5) writing a manuscript for a refereed
journal and making an oral presentation.
The lectures will be given in English with supplementary material available in Japanese.
55711〜55712
|
電子物理工学特別実験第一 |
前学期 |
0−0−2 |
 |
各 教 官 |
|
同 第二 |
後 〃 |
0−0−2 |
(Special Experiments I and II on Physical Electronics)
専攻しようとする分野に関連のある高度の実験を行うものである。
55701〜55704
|
電子物理工学講究第一 |
前学期 |
1 単 位 |
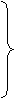 |
指導教官 |
|
同 第二 |
後 〃 |
1 〃 |
||
|
同 第三 |
前 〃 |
1 〃 |
||
|
同 第四 |
後 〃 |
1 〃 |
(Seminar I〜IV on Physical Electronics)
専攻しようとする分野に関連ある専門書,文献につき,輪読,討論を行うものである。
55801〜55806
|
電子物理工学講究第五 |
前学期 |
2単位 |
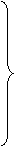 |
指導教官 |
|
同 第六 |
後 〃 |
2 〃 |
||
|
同 第七 |
前 〃 |
2 〃 |
||
|
同 第八 |
後 〃 |
2 〃 |
||
|
同 第九 |
前 〃 |
2 〃 |
||
|
同 第十 |
後 〃 |
2 〃 |
(Seminar V〜X on Physical Electronics)
いずれも博士後期課程における授業科目であって,それぞれ示した期間に履修しなければならない。この
内容は博士後期課程相当の程度の高い輪講,演習,実験,等より成るものである。
55501〜55506
電子物理工学特別講義第一〜第六(Special Lecture I〜VI on Physical Electronics)
前・後学期 各1〜2単位 各 教 官
各教官がそれぞれ専攻する分野において,特殊の題目を選択して随時開講するものである。