〔教 授 要 目〕
93001
エネルギー科学原論(Fundamentals for Energy Sciences)
前学期 2−0−0 各教官(○専攻主任)
各教官が担当し,エネルギーの創造,変換の基礎,先端的エネルギーシステム,高効率エネルギー変換技
術,粒子ビーム,プラズマやレーザーのエネルギー応用について講述する。
93002
エネルギー環境基礎論(Fundamentals for Energy Environment)
前学期 2−0−0 ○長崎 孝夫 助教授・肖 鋒 助教授・矢部 孝 教授
宮田 秀明 講師(非常勤)・近藤 裕昭 講師(非常勤)
佐藤 正樹 講師(非常勤)
エネルギーの利用とエネルギー拡散過程の関連を物理的に解説するとともに種々のエネルギー機器の特性
を述べ,エネルギーの大量消費に対する環境の影響を少なくするエネルギープロセス及びエネルギーシステ
ムの構築に関する指針を講述する。
93004
低温理工学(Cryogenic Engineering and Physics)
前学期 2−0−0 ○岡村 哲至 教授・栗山 透 助教授
超伝導・超流動現象の基礎とエネルギー機器への応用,及び高臨界温度超伝導の原理と開発の現状につい
て講述する。
93006
エネルギー変換基礎論(Fundamentals for Energy Conversion)
前学期 2−0−0 ○奥野 喜裕 教授・山岬 裕之 教授・長谷川裕夫 講師(非常勤)
渡辺 隆夫 講師(非常勤)・岩堀 徹 講師(非常勤)
各種エネルギーの形態,エクセルギー評価及び相互変換の基礎を論じ,従来の熱エネルギー変換サイクル
のみならず,MHD発電,分散型電源,燃料電池,二次電池等の新型のエネルギー変換方式についても講述
する。また各エネルギー変換方式の最先端の技術開発の状況についても紹介する。
93008
核融合工学(Controlled Nuclear Fusion Engineering) 西暦偶数年度開講
前学期 2−0−0 ○糟谷 紘一 助教授・嶋田 隆一 教授
核融合エネルギー,各種の核融合反応過程,ローソン条件,慣性閉じこめに関する基礎,レーザー光の吸
収,標的の爆縮,レーザー核融合,イオンビーム慣性核融合,磁場閉じこめに関する基礎,トカマク,トカ
マク以外の磁場閉じこめ装置,核融合炉の構造,核融合炉における問題などについて論じる。
93009
エネルギー創造基礎論(Fundamentals on Nuclear Energy Sources)
前学期 2−0−0 ○河野 俊之 教授・小川 雅生 教授・今崎 一夫 講師(非常勤)
小関 隆久 講師(非常勤)
原子核の基本的性質と原子核反応の基礎,核融合・核分裂エネルギーの基礎物理と仕組みについて講述す
る。さらに,レーザーや粒子ビームによる慣性核融合,磁場閉じ込め核融合について,最新の研究成果を交
えながら,基本原理や現状と課題を解説する。
93016
プラズマ理工学(Plasma Science and Engineering)
前学期 2−0−0 ○堀田 栄喜 教授・堀岡 一彦 教授・沖野 晃俊 助教授
プラズマの生成,プラズマ中の衝突,プラズマの基礎方程式,電磁流体力学,プラズマ中の線形および非
線形波動,プラズマの平衝,安定性,輸送現象,プラズマ診断,プラズマ応用等について講述する。
93010
ハイパワービーム理工学(Physics and Engineering on High Power Beam) 西暦偶数年度開講
後学期 2−0−0 ○河野 俊之 教授・志甫 諒 教授・金井 達明 教授
大電流・高エネルギー粒子ビームの発生とその応用について講述する。発生に関しては,大電流・高エネ
ルギー粒子加速器における加速や集束の原理,システムを構成する各種機器について解説する。また応用と
しては,放射性同位元素の生成,放射性同位体ビーム,高エネルギービームの医学応用,自由電子レーザー,
慣性核融合などについて講述する。
93011
高密度エネルギー変換工学(High-Density Energy Conversion Engineering) 西暦奇数年度開講
後学期 2−0−0 ○堀岡 一彦 教授・服部 俊幸 教授・赤塚 洋 助教授
根本 孝七 助教授
レーザーの基本原理,荷電粒子ビームの加速原理などについて説明した後,電磁エネルギーや荷電粒子ビ
ームから高温・高密度プラズマへのエネルギー変換過程について講義する。また,核融合,物質変換,超高
圧物性研究をはじめとする種々の応用についても解説する。
93013
電力システム工学(Electric Power System Engineering)
前学期 2−0−0 ○堀田 栄喜 教 授・根本 孝七 助教授
電力システムの運用・制御に関する基礎事項ならびに電力自由化を含む最近の電力供給の課題と技術開発
の将来について講述する。
93015
計算流体工学(Computational Fluid Engineering)
前学期 2−0−0 ○長崎 孝夫 助教授・肖 鋒 助教授
非圧縮流れ,圧縮性流れ,および熱・物質輸送など熱流体問題の数値計算法について,差分法および有限
体積法を中心に基礎から講述する。
93017
燃焼学特論(Advanced Course of Combustion Science)
後学期 2−0−0 吉澤 善男 教授
反応系の熱力学に基づく有効エネルギー評価,反応速度論,予混合火炎の理論,拡散火炎,乱流火炎,デ
トネーション,液滴および噴霧の燃焼など燃焼学の基本を論ずるとともにボイラーなど実用の燃焼機器につ
いて講述する。さらに,エネルギー循環燃焼,燃料電池など新しい燃焼技術,ならびに原子力関連施設の燃
焼,爆発に関係する安全についても言及する。
93018
放射線・粒子線の科学(Sciences of Radiation and Beams)
前学期 2−0−0 ○小川 雅生 教 授・伊藤 満 教授・中村 聡 教授
石野 史敏 助教授・實吉 敬二 助教授・梶原 将 助教授
佐々木 聡 教授
放射線,放射性同位元素,種々の粒子線の物理およびそれらの物質科学,生命科学などへの応用などにつ
いて解説する。更に,放射線や放射性同位元素の安全取扱についても解説する。
93021
プラズマ科学の基礎(Fundamentals for Plasma Science) 西暦偶数年度開講
後学期 2−0−0 ○沖野 晃俊 助教授・堀田 栄喜 教授・堀岡 一彦 教授
プラズマ生成,基礎方程式,電磁流体力学,プラズマの特性,診断,応用について講述する。
Plasma Generation
Basic Equations of Plasmas
Magnetohydrodynamics
Characteristics of Plasma
Plasma Diagnostics
Plasma Applications
17010
分子分光学(Molecular Spectroscopy)
後学期 2−0−0 上妻 幹男 助教授
物性物理学専攻の教授要目を参照のこと。
98011
エネルギーシステム・環境論(Energy Systems and Environmental Engineering)
前学期 2−0−0 ○吉澤 善男 教授・小栗 慶之 助教授
環境理工学創造専攻の教授要目を参照のこと。
50111
電力工学特論(Advanced Electric Power Engineering)
後学期 2−0−0 猪野 博行 講師(非常勤)・市川 元保 講師(非常勤)
電気系2専攻の教授要目を参照のこと。
|
創造エネルギー特別実験・演習第一 |
前学期 |
0−0−2 |
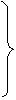 |
各 教 官 |
93711 |
|
同 第二 |
後 〃 |
0−0−2 |
93712 |
||
|
同 第三 |
前 〃 |
0−0−2 |
93713 |
||
|
同 第四 |
後 〃 |
0−0−2 |
93714 |
(Advanced Experiments and Exercises on Energy Sciences I−IV)
エネルギー理工学について,各指導教官の指導により,比較的長時間を費やして行う専門的実験・演習で
ある。
|
創造エネルギー講究第一 |
前学期 |
2単位 |
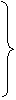 |
各 教 官 |
93701 |
|
同 第二 |
後 〃 |
2 〃 |
93702 |
||
|
同 第三 |
前 〃 |
2 〃 |
93703 |
||
|
同 第四 |
後 〃 |
2 〃 |
93704 |
(Seminar in Energy Sciences I−IV)
学生の希望と研究題目により,各指導教官の指導のもとに,国内外の論文の輪講,研究事項の討論を行う。
|
創造エネルギー講究第五 |
前学期 |
2単位 |
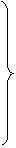 |
各 教 官 |
93801 |
|
同 第六 |
後 〃 |
2 〃 |
93802 |
||
|
同 第七 |
前 〃 |
2 〃 |
93803 |
||
|
同 第八 |
後 〃 |
2 〃 |
93804 |
||
|
同 第九 |
前〃 |
2 〃 |
93805 |
||
|
同 第十 |
後 〃 |
2 〃 |
93806 |
(Seminar in Energy Sciences V−X)
いずれも博士後期課程における学科目であり,それぞれ示した期間に履修するものとする。この内容は博
士後期課程の,程度の高い輪講,演習,実験,製図などよりなるものである。