〔教 授 要 目〕
先端物理情報システム論(Advanced Information Processing)
前学期 2−0−0 各教官
現代の情報システムを包括的に理解することを目的とする。トピックスとして,情報処理,ネットワーク,
ヒューマンインターフェースなど,情報システムの基盤技術を取りあげ,関連するサイエンス,ハード・ソ
フト両面の技術要素およびその動向について講述する。
ディジタル信号処理基礎論(Fundamentals of Digital Signal Processing)
前学期 2−0−0 ○小林 隆夫 教授・山口 雅浩 助教授・杉野 暢彦 助教授
情報処理,メディア処理,画像処理などの基本となる信号のディジタル処理の基礎を習得する。離散時間
信号とシステム,サンプリング定理,離散的フーリエ変換,ディジタルフィルタ,2次元フーリエ変換,多
次元信号処理などを取りあげる。
音声言語メディア処理(Spoken Language Processing)
後学期 2−0−0 ○小林 隆夫 教授・住田 一男 客員助教授
音声言語メディアの解析・処理手法を解説し,そのヒューマンインタフェースの応用や,音声言語メディ
アと他の情報メディアを統合したマルチモーダルインターフェースへの応用についても言及する。
光画像工学(Optical Imaging and Image Processing)
後学期 2−0−0 ○山口 雅浩 助教授・大山 永昭 教授
光の回折・干渉や結像理論と2次元フーリエ変換やサンプリング等との関係について述べるとともに,こ
れに基づくディジタル画像処理・解析等の手法並びに応用例を紹介する。
離散情報システム(Analysis of Discrete Systems) 西暦奇数年度
前学期 2−0−0 伊東 利哉 教授
情報ネットワークやVLSIに代表される大規模離散システムのパラメータに対して,適当な確率分布を
仮定し,それらのパラメータを確率変数として扱うことにより,大規模離散システムの設計やその振舞(最
適性)の解析を行う手法について述べる。
視覚情報認識(Visual Perception)
前学期 2−0−0 ○内川 惠二 教授・金子 寛彦 助教授
人間の視覚系が外界の視覚情報をいかに受容,伝達,分析,統合して,最終的な視覚像を形成しているか
を述べる。講義では豊富な心理物理的な実験データを示しながら,眼球の構造,明暗順応特性,等色と3錐
体,色の見えと認識,色覚の時空間特性,運動知覚,奥行き知覚,視空間認識などについて基礎的な面から
解説する。
感覚情報システム(Sensory Information Systems)
後学期 2−0−0 ○金子 寛彦 助教授・安藤 広志 客員助教授・栗木 一郎 客員助教授・
平原 達也 客員教授・内川 惠二 教授
感覚情報システムの低次から高次までの機能と機構,異種感覚情報の統合過程や感覚系の発達と学習など
に関する基礎特性と先端的な知見,感覚系の分析とモデル化の各種手法,および感覚情報処理に関連する応
用技術について述べる。
脳の統計物理と並列計算(Statistical physics and parallel computing of brain)
2学期 2−0−0 熊澤 逸夫 教授
脳の並列計算の原理を統計物理学的に理解しようとする試みを題材にしながら、脳の情報処理の仕組み、
並列計算を解析・設計するための統計物理学的方法、確率的計算の原理を学ぶ。
1. 生体の神経系とニューラルネットワーク
2. ニューロンと脳の工学的モデル
3. 統計物理学の基礎
4. 粒子系の相互作用のモデル:スピングラス
5. 計算素子の相互作用のモデル:ボルツマンマシン
6. 学習システムの数学的基礎:勾配法
7. ボルツマンマシンの学習
ヘルスケア情報創造工学(Creative Healthcare Informatics)
前学期 2−0−0 ○谷内田益義 客員助教授・小尾 高史 助教授・大山 永昭 教授
ヘルスケア情報工学を物理情報システム工学の創造応用分野として位置付け,そのコンセプトを習得させ
る。あわせて新規システムの構築や製品を開発する場合の創造性のあり方,実際の臨床例への応用あるいは
近未来ヘルスケア情報社会をテーマとした討議を通じ,知識のみではなく,実業に対する感性及びイメージ
形成力を磨き,情報システム構築上の問題点の抽出と解決策を提案できる創造性を養う。
具体的には医用画像診断機器,モニター診断,セキユリティ機構および,電子保存技術を中心としたヘル
スケア地域連携システムの構築を素材に進める。また,画像再構成の原理,医用画像情報の高度利用,知識
抽出等の関連技術についても解説する。
機能電子デバイスI(Functional Electron Devices I)
前学期 2−0−0 ○益 一哉 教授・石原 宏 教授・酒井 徹志 教授・岩井 洋 教授
徳光 永輔 助教授・筒井 一生 助教授・大見 俊一郎 助教授
半導体物理,pn接合,ヘテロ接合などの基礁を概説し,MOSトランジスタ,バイポーラトランジスタ
の動作原理を詳述する。これらデバイスの直流特性,高周波特性などの電気的特性と物理的現象を論じる。
さらに,集積回路の構成要素としてのこれらデバイスの現状と高性能化,高速化に対する物理的考察と実例
を紹介する。MOSFETの微細化限界,スケーリング則などはここで論じる。
機能電子デバイスII(Functional Electron Devices II)
後学期 2−0−0 ○浅田 雅洋 教授・青柳 克信 教授・渡辺 正裕 助教授
ヘテロ接合を利用した化合物半導体デバイスやその応用を論じる。さらに,機能デバイスの基礎となる極
微細構造の物性を論じ,極微細電子材料における量子効果や単電子輸送などの新しい物理現象を利用した機
能電子デバイスについて詳述する。
先端材料光物性(Optical Properties of Advanced Materials)
前学期 2−0−0 ○青柳 克信 教授・宗片 比呂夫 教授・梶川 浩太郎 助教授
高機能で微小な光デバイスを研究・開発する上で理解しておく必要のある物理学的基礎知識(光と物質,
量子効果と光物性)を習得することを目的とする。受講対象者は,電磁気学基礎,および,半導体物性・固
体物理・物理化学の中のいずれか1つを履修済みであることが望ましい。
オプトエレクトロニクス(Optoelectronics)
前学期 2−0−0 ○宮本 智之 助教授
光通信や光記録などの光エレクトロニクスシステムを理解するために,光デバイスの動作原理の基礎を講
義する。受動光デバイスの基礎となる光導波路や光ファイバの導波モード解析,能動光デバイスの代表とな
る半導体レーザの動作原理や特性,また,その他の光機能デバイスについてもその動作原理について解説す
る。
イメージング材料I(Imaging Materials I)
前学期 2−0−0 ○半那 純一 教授・原 和彦 助教授
情報システムにおける「情報」と「材料」の関わり,位置づけについて解説し,この立場からハードコピ
ーを中心とした情報記録技術やディスプレイなどの情報表示技術を例に,これらの情報システムの原理,用
いられる材料の基礎物性と材料設計の考え方について講義する。また,最新の技術動向についても述べる。
イメージング材料II(Imaging materials II)
後学期 2−0−0 ○原 和彦 助教授・梶川 浩太郎 助教授
画像の入力,処理,記録,表示などの情報プロセスシステムに用いられる材料のうち,無機および有機の
光学材料に焦点を当てて講義を行う。前半は,表示・記録用発光デバイスに用いられる無機の発光材料につ
いて,基本的な発光過程,各種デバイスの動作原理,材料物性とシステム設計の考え方等を解説する。後半
は新しい光情報デバイス材料として研究されている低分子および高分子材料について述べる。まずそれらの
材料の物性や光学応答について議論し,次いで液晶材料,有機EL材料,非線形光学材料,プラスチックフ
ァイバ材料等の最近の話題を解説する。
高機能光センサ特論(Advanced Functionality Photosensors)
後学期 2−0−0 ○半那 純一 教授・谷 忠昭 客員教授・久間 和生 客員教授・
高田 俊二 客員助教授
情報の入力デバイスとして有用な高機能光センサについて,前半では光センサを感度と解像力を軸に概観
し,撮影に適した特性を有するセンサとしてカラーフィルムとCCDを取り上げて比較分析すると共に,機能
材料からのアプローチとしてハロゲン化銀微結晶を用いた写真用カラーフィルムについて解説する。後半では,
電子機能デバイスからシステム化からのアプローチとして人間の目の機能を模倣したインテリジェントイメ
ージセンサ(人工網膜LSI)を中心に講義する。
光通信システム(Optical Communication Systems)
前学期 2−0−0 ○小山 二三夫 教授・植之原 裕行 助教授
大容量光通信システムを構成するための構成要素,システム性能,大容量化のための多重化方式,ネット
ワーク構成,クロスコネクトなどについて解説する。幹線系大容量システムのみならず,光LANやネット
ワーク化の展望についても概観する。
物理情報システム特別講義(Special Lectures on Information Processing)
後学期 1−0−0 北原 利行(非常勤)・岡崎 宣夫(非常勤)・関原 謙介(非常勤)
山内 泰樹(非常勤)・高橋 庸夫(非常勤)
複数の非常勤講師により,情報処理,情報技術に関わる材料,デバイス,システムに関する最新の研究成
果について解説する。
知的情報資源の活用と特許(Utilization of Intelligent Information Resources and Patents)
前学期 1−0−0 吉井 一男(非常勤)
知的情報資源の活用という立場から,特許制度の法的な位置,「特許される発明」とは何か,特許制度を活
用するための具体的・実際的な知識,更には簡単な明細書の書き方に至るまでを,豊富な具体例とともに解
説する。
88711
創造物理情報システム特別実験第一(Special Experiments of Information Processing I)
前学期 0−0−2 各教官
動的情報処理,情報メディア,光情報デバイス,機能デバイス,情報資源表現,情報資源知識化等,物理
情報システムについての実験を通じて,基礎的な理論,方法および幅の広いものの見方を習得することを目
的として,原則的に指導教官以外の教官の研究室において実験を行う。
88712
創造物理情報システム特別実験第二(Special Experiments of Information Processing II)
後学期 0−0−2 各教官
指導教官の指示のもとに専攻しようとする分野に関連する実験を通じて,動的情報処理,情報メディア,
光情報デバイス,機能デバイス,情報資源表現,情報資源知識化等の物理情報システムについての最先端の
研究,応用技術等について知識を広め,その研究に必要な基礎技術を習得することを目的とする。
|
創造物理情報システム特別演習第一 |
前学期 |
0−1−0 |
 |
各教官 |
88721 |
|
創造物理情報システム特別演習第二 |
後学期 |
0−1−0 |
88722 |
(Special Exercise in Information Processing I〜II)
本特別演習は,動的情報処理,情報メディア,光情報デバイス,機能デバイス,情報資源表現,情報資源
知識化等の物理情報システムに関する各テーマについて討論主体の演習を通じて,関連領域における基礎学
問や最新技術における視野の拡大や問題発見能力を習得させることを目的とする。
|
創造物理情報システム講究第一 |
前学期 |
2単位 |
 |
各教官 |
88701 |
|
創造物理情報システム講究第二 |
後学期 |
2単位 |
88702 |
(Seminar in Information Processing I〜II)
各指導教官の指導の下に動的情報処理,情報メディア,光情報デバイス,機能デバイス,情報資源表現,
情報資源知識化等の物理情報システムの基礎概念・関連する他分野との関わりも含めて,テキスト・学術論
文を中心とした輪講・討論を行うことによって各自が取り組む研究の位置づけを習得させる。
|
創造物理情報システム講究第三 |
前学期 |
2単位 |
 |
各教官 |
88703 |
|
創造物理情報システム講究第四 |
後学期 |
2単位 |
88704 |
(Seminar in Information Processing III〜IV)
各指導教官の指導の下に動的情報処理,情報メディア,光情報デバイス,機能デバイス,情報資源表現,
情報資源知識化等の物理情報システムに関して,各自が取り組む研究に関連する学術論文の読解を中心とし
た輪講を行うとともに,修士論文作成の指導を行う。
|
創造物理情報システム講究第五 |
前学期 |
2単位 |
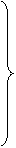
|
各教官 |
88801 |
|
創造物理情報システム講究第六 |
後学期 |
2単位 |
88802 |
||
|
創造物理情報システム講究第七 |
前学期 |
2単位 |
88803 |
||
|
創造物理情報システム講究第八 |
後学期 |
2単位 |
88804 |
||
|
創造物理情報システム講究第九 |
前学期 |
2単位 |
88805 |
||
|
創造物理情報システム講究第十 |
後学期 |
2単位 |
88806 |
(Seminar in Information Processing V〜X)
博士後期課程において,各指導教官の指導の下に,各自が取り組む研究に関連する学術論文の読解を中心
とした輪講を行うとともに,自立した研究者として必要な学術論文作成や国際会議等での発表論文に関する
実際的指導を含めた素養について習得させる。