〔教 授 要 目〕
65020
教育システム研究法(Methodology of Educational System)
前学期 0−1−0 中川 正宣 教授ほか
教育システムを研究する上で必要となる基礎的事項として,人間の発達と学習や,ミクロ及びマクロレベ
ルの様々な教育システムのモデル,教育メディアの特性と効果等に関わる基礎知識を修得させるとともに,
教育システムに関わる基礎,開発,評価研究の具体的事例を挙げ,教育システム研究法を演習を通して理解
させる。
65021
行動システム研究法(Methodology of Human Dynamics Design)
前学期 0−1−0 中原 凱文 教授ほか
人間行動システムを研究する上で必要となる基礎的事項として人間の認識,コミュニケーション,生理・
心理行動特性や,その計測・分析法に関わる基礎知識を修得させるとともに,人間行動システムに関わる基
礎,開発,評価研究の具体的事例を挙げ,人間行動システムの研究法を演習を通して理解させる。
人間行動システムに関する研究の方法論について,オムニバス形式で関連分野の教官が協力して演習を行
う。
65001
教授・学習システム論(Educational Technology for Instructional System Design)
前学期 1−1−0 松田 稔樹 助教授
I 授業の計画,実施,評価や,教授・学習支援システムの開発,評価の基礎として,教授・学習過程のモ
デル,教師の意思決定モデル,学習者モデルなどを理解し,それらと関連づけて,教授活動を支援する教
育工学的手法を演習により修得する。さらに,具体的な教授・学習支援システムの設計,評価を通して,
教材情報や教授方略,教授スキルの体系化の方法や,授業研究の方法を修得する。
II 教授活動モデル,授業設計・評価手法,カリキュラム開発,教材情報データベース,授業設計システム,
CAIと学習者モデルなどについて扱う。
III 教育工学文献の講読,教材研究,授業設計,教材情報の知識表現化,シミュレーション&ゲーミング型
教材の作成,授業・学習実験の計画・実施・分析等について課題を出す。
65002
数理モデル論(Mathematical Models of Congnitive Science)
前学期 2−0−0 中川 正宣 教授
I 教育の研究対象である認知現象(記憶,学習,思考,問題解決,言語処理など)の数理的理論モデルを
構成し,その数理的理論モデルをコンピュータシミュレーションなどを用いた応用実験で確かめるという,
理論と実験結果との対比について理解させる。さらに,数理モデルを,より高度な論理的思考の学習過程
にまで発展させ,ニューラルネットワークモデルを用いた理論を一般的に説明する。
II 講義では,図表やコンピュータグラフィックスの実演を多用し,直感的に理解しやすい説明を心がける。
65003
学習情報ネットワーク(Educational Information Network)
前学期 1−1−0 室田 真男 助教授
I インターネット等のコンピュータネットワークについて,学習活動におけるインフラストラクチャとし
て理解した上で,それを具体的に学習活動へ応用する方法について,演習による体験を通じて考察する。
また,実際に学校現場でコンピュータネットワークを管理・運用する際に必要となる技術的基礎について
も合わせて理解する。
II インターネットプロトコル,学習活動へのインターネットの活用方法,学校ネットワークの構築・運用
などを主な内容とする。
III 毎回課題を課す。課題は授業時間後に各研究室の計算機を用いて行う。
65004
教育評価システム特論(Educational Evaluation System)
前学期 1−0−0 石塚 智一 教授
教育評価システムに関わる具体的事例として入学試験,進路選択,大学評価等を取り上げ,その理論的側
面や現実的応用などについて解説する。
教育評価システムについて,講義を行う。
65005
生体動作システム分析法(Analysis of Human Movement System)
前学期 1−1−0 丸山 剛生 助教授
人間の行動や動作の制御について,運動学的,生体情報学的,バイオメカニクス的方法を用いた評価法,
分析法の講義を行い,演習を通して生体動作システムの分析方法を習得することをねらいとする。
65006
自律系運動生理学(Exercise Physiology of Autonomic Function)
前学期 1−1−0 須田 和裕 助教授
人間が運動をするときの自律系機能および,環境や運動に対する適応反応について論ずる。
65007
言語資源解析法(Analysis of Discursive Practices)
前学期 2−0−0 赤間 啓之 助教授
言語資源の解析方法について,頻度・共起データの取得法から,統計処理まで,コーパス言語学,計量文体
論,情報検索学の観点から講義する。
65009
マルチメディア学習特論(Advanced Multimedia Learning Environments)
前学期 2−0−0 西原 明法 教授
マルチメディアシステムは教育において活用可能なメディアであるが,その効果的・効率的な利用方法が
求められている。この科目では,各種メディアの特徴を詳述し,教育的効果と可能性を述べる。特に,新し
いメディアによってはじめて可能になったマルチメディア学習システムを取り上げ,今後の教育の在り方に
ついて論じる。
65011
教育開発と評価(Educational Development and Evaluation)
後学期 1−1−0 牟田 博光 教授
発展途上国の教育開発を考える上で必要な知識,技術を身に付けるための講義,演習を行う。発展途上国
の現状理解,援助プロジェクトの形式,援助プロジェクトの評価などの実践的知識と同時に,マクロな視点
から教育援助の効果や費用を計量する基礎的方法について講義,演習を行う。
65014
能力測定法特論(Introduction to Test Theory)
後学期 1−0−0 未 定
人間の能力測定の諸手法について,その統計学的基礎から,実際的利用法までを指導し,結果の読みとり
方についても習熟させ,実践的な教育の場で活用できる能力を育成する。
能力測定法について,講義を行う。
65015
生体動態学(Human Dynamics)
後学期 2−0−0 中原 凱文 教授
人間が本来所有している「適応能力」とは何かを理解させ,高度機械化・高度技術化等による産業構造・
社会構造変化の中で,人間としていかに能力発揮させるか,またより人間らしく生きるためにはどうしたら
よいかを視点とし,今日の健康問題(高齢者対策を含む),生活設計,職場設計等に関しての方策を論じる。
生体動態について,講義を行う。
65016
精神適性論(Psychological Aptitude)
後学期 2−0−0 石井 源信 教授
人間の行動を理解するためには,個人の所有している性格や能力,並びに感情,意識,態度等の心的機能
に関する統合的な研究が必要である。個人差を様々な観点から捉え,スポーツや日常生活における適応した
行動と情緒的な安定,精神的な健康との関連の重要性に関して解説し,その対応策等を理解させる。精神適
性とメンタルマネジメントに関する講義のなかで,各種心理検置を用いて自己診断し,メンタルマネジメン
トの具体的な手法を学び,研究活動や社会生活に生かせるような授業を展開する。
65017
書誌環境論(Historical Sciences and Information)
後学期 2−0−0 早坂 真理 教授
言語とそれを機軸に形成される民族・国民意識の関連という視点から,固有の言語獲得をめぐる闘争的性
格を帯びた歴史上の事例を紹介する。「自己」と「他者」の区別をめぐって異言語間に生ずる,錯綜した人間
社会の諸問題を取り上げ,それをめぐる近代以降の書誌環境の変遷を通時的かつ共時的に論ずることにする。
とくに複数の民族がそれぞれの自己認識していく過程で,民衆レベルの情報ネットワークへの接近行動を把
握しながら,さらに日常の言語行為を増幅するマルチメディアの現実を考慮して,それに対応した新しい異
言語間インターフェース・システムの可能性を考える。
本講義では,1989年の東欧革命,1992年のソ連崩壊を契機とした国際秩序の再編成を射程に入れ,ヨーロ
ッパの東部地域から日本海におよぶスラヴ東欧地域の歴史過程を比較史の立場で検討しながら,上記の課題
を論じることにする。
65018
教育情報工学(Instructional System Design)
前学期 2−0−0 赤堀 侃司 教授
教育システムの設計・評価や教授活動の計画・評価に有効な数理的・工学的手法について,事例を上げな
がら講義する。具体的には,教育目標の構造化手法,学習評価の方法,ハイパーテキストの設計手法,テキ
ストデザインの方法,グループウェアを活用した学習活動の分析手法,コミュニケーション分析の方法など
を扱う。教育情報工学の構築について講義を行う。
65019
教育情報工学特論(Advanced Educational Information Technology)
後学期 2−0−0 中山 実 助教授
人間の行動を解析・評価するための,計測方法とデータ分析方法について,特に視点移動,瞳孔面積,G
SR,脳波,などの生理学的指標の活用法について講義する。授業では各種指標の計測法や分析法とともに
その指標の特性,学習行動との関わり,教授学習システムへの応用等について,研究事例を上げながら解説
し,今後の課題も提起する。
教育情報工学について,講義を行う。
65036
情報教育論(Information Technology Education)
前学期 1−0−0 赤堀 侃司 教授
情報教育は,現代の教育の中で重要な位置を占めてきた。本科目では,小中学校における情報教育の実際,
諸外国の情報教育,高等学校の教科「情報」,情報教育の政策,ネットワーク活用の意義と課題,情報リテラ
シーのねらい,オンライン授業の取り組み,情報倫理やモラル,情報教育と教育課程,など今日的なトピッ
クスを取り上げて解説する。授業では,資料を提示しながら討論を中心に実施する。
65023
日本語の言語構造(Linguistic Structure of Japanese Language)
後学期 2−0−0 仁科 喜久子 教授
日本語を具体例として言語構造に関する知識を修得することを目的とする。形態素解析,構文解析,談話
分析の具体的な方法,対話システムのための音声言語の特色について講述する。また概念とその表現形式と
しての言語について考察し,コンピュータ工学における自然言語処理に関する問題点も取り上げる。
65026
心理・教育データ解析(Data Analysis for Psychogy and Education)
前学期 1−0−0 吉野 諒三 講師(非常勤)
I 思考,学習,感性などの人間の心理的諸特性の解明や,教育効果の評価,教育計画の立案などに必要な
データを実験,観察,調査,テストなどによって収集したり,分析する方法について理解する。
II 推測統計の基礎を中心に概説する。
III 単に理論を理解するだけでなく,実際的なデータの分析を通じて実践的な技能を身につけることを目的
とする。
65027
教育用ソフトウェア設計演習(Practices for Designing Educational Software)
前学期 0−1−0 野村 泰朗 講師(非常勤)
I 教育用ソフトウェアの開発について,学習活動を制御したり,誤り・つまずきに対応するための対話イ
ンタフェースのデザインと実装に焦点を当てながら,その設計方法を修得する。
II 教育用ソフトウェアとユーザ特性,目標分析とソフトウェアの要求分析,誤り・つまずきへの対応とイ
ンタフェースのデザイン,学習履歴の保存と活用,教育用ソフトウェアの評価・改善などを内容とする。
III 演習をする上で必要な(CやJavaなどの)プログラミングの基礎については,学部の授業を履修す
るか,自学自習することを原則とする。なお,設備の都合上,履修者を制限する場合がある。
65028
運動機能解剖学
後学期 1−0−0 福林 徹 講師(非常勤)
運動器の各部位に関して,基礎解剖学的な捉え方は必要であるが,特に本専攻にあっては機能的に捉える
考え方の方が,バイオメカニクス的な研究を進めていく上で有効と考えられる。膝,足首,大腿部,肩,肘,
手首などの筋肉,靭帯,腱のつき方ならびにある種の運動が発現するメカニズムなどに関して概説する。
65031
思考・学習の認知科学(Cognition in Thinking and Learning)
前学期 2−0−0 山岸 侯彦 助教授
人間の認知・学習プロセスを,情報処理システムとして捉える基本的な考え方とモデルを,認知心理学,
認知科学の実証的知見に基づいて概観する。特に記憶,学習,発達,概念,知識,問題解決,意思決定など
に関する最新トピックスに重点を置く。授業では,簡単な実験を行うことがある。
65032
ストレスマネジメント実習(Practices of Stress Management)
後学期 0−0−1 石井 源信 教授
ストレスフルな研究活動における情緒面のコントロール能力は個人のメンタルヘルスにとってきわめて重
要なものである。この実習ではテニスを通して日頃のストレスをうまく発散するとともに,個人がもってい
る能力をどんな状況でも十分に発揮するための心理的技法を習得することによってメンタルマネジメント能
力を高めさせる。
65035
言語資源活用演習(Practical Exercise in use of Language Resource)
前学期 0−0−1 赤間 啓之 助教授
本年度は休講とする。
65034
学習環境デザイン論(Methodology for Learning Environment Design)
後学期 1−0−0 加藤 浩 助教授
I 行動主義,表象主義,構成主義,状況論などの学習観を歴史的変遷に従って紹介し,それらに基づく教
育システムの特徴や相違点について理解する。さらに,状況論的学習観の立場から,物理的システムばか
りでなく社会システムも含んだ広義の教育システム(学習環境)をデザインしたり,評価・改善するため
の方法論を修得する。
II 学習観の歴史的変遷,状況論的学習観に基づく学習環境のデザイン,参与観察法,ビデオ分析法などを
主な内容とする。
65037
大学教育とe-Learning(Higher Education and e-Learning)
後学期 2−0−0 馬越 庸恭
講義の狙い:大学教育とe-Learningについて,本学,日本国内,海外の具体的なケースを紹介しながら,
21世紀の動向をさぐってみたい。
65042
聴覚情報工学特論(Auditory Information Engineering)
前期 2−0−0 西方 敦博 助教授
視覚に並ぶ情報受容器官としての聴覚およびその受容情報に焦点をあて,聴覚器官の構造,聴覚モデル,
ピッチ知覚,マスキング,両耳聴効果,音源定位,音楽情報処理など,聴覚の諸特性について論じる。ま
た,音像定位システムや音質評価システムなどの工学的応用について述べる。
65040
身体系メディアとバーチャルリアリティ(Body-oriented media and virtual reality)
後期 1−0−0 池井 寧 講師(非常勤)
情報技術の進展に伴って人間中心の設計が重視されるようになり,人間の身体的特性を反映したメディア
があらわれはじめた。人間の身体をまるごと計算機シミュレーションのループに取り込み,メデイアと一
体化した形態で人間の情報処理能力を拡大しようという考えである。
本講義では,身体系メデイアの方法論として進展しつつあるウェアラブルコンピュータやバーチャルリア
リティに関して,近年の進展と今後の方向を概観する。
近年バーチャルリアリティによる身体感覚・動作のシミュレーション技術は非常に重要になってきており,
その概念や基礎技術を習得することが必要である。
65039
Webベース学習システム設計(Web-based Learning System Design)
後期 0−1−0 柳沢 昌義 講師(非常勤)・赤堀 侃司 教授
Webで実装される学習システムの概念と実装法を習得する。学習システムをWeb上で構築する意義/
可能性を,例示・実装を通して理解を深める。具体的には,実際のWebベース学習システムを例にとり
ながら,三階層クライアントーサーバモデル,SQL,XMLの基礎とシステム構築方法を学ぶ。最後に
自らWebベースの学習システムを設計し,実装を行う。環境は,Microsoft Windowsを想定して行うが,
基本知識・技術はUNIX等,多くのシステムにそのまま応用することができる。
教育測定法(Foundation of Educational Measurement)
前期 1−1−0 前川 眞一 教授
この講義では,心理学における計量的方法に関する概説を行う。主な内容は,心理学的測定法ならびに,
学力テスト・性格テストなどの基となっているテスト理論の基礎についてである。講義の前半では,これ
らの方法の学習に必要な統計学ならびに数学の解説を行う。
Building Effective English Communication Skills through Applied Psychology Topics I
(英語コミュニケーションスキルの習得)
前学期 2−0−0 馬越 庸恭 教授・Dr.Jean Kenne
参加者が毎週英語で提出する短いレポートに基づいてディスカッションを行うことで英語によるコミュニケ
ーションのスキルを身に付けることを目指す。
21世紀COEプログラム「大規模知識資源の体系化と活用基盤構築」グループの教育プログラムの一環とし
て新設科目。
65741,65742
|
教育システム特別実験第一 前学期 0−0−2 〃 第二 後学期 0−0−2 |
 |
中川 正宣 教 授,牟田 博光 教 授 石塚 智一 教 授,前川 眞一 教 授 山岸 侯彦 助教授,赤堀 侃司 教 授 室田 真男 助教授,松田 稔樹 助教授 中山 実 助教授,加藤 浩 助教授 |
I 教育の現場で実践・支援活動を行う際に必要となる専門知識,技能や問題解決力を修得するために,各
学生と指導教官とが相談の上で教育システムに関わる具体的テーマを設定して課題解決の実習を行う。
II 発達・学習・思考,教育計画・教育方法・教育課程編成,科学教育・技術教育・情報教育,教育評価・
心理測定,教育メディア・教材の開発などを主な内容とする。
III 教育系各研究室に所属する学生を対象とする。
(Practical Exercise in Educational System I-II)
65721,65722
|
行動システム特別実験第一 前学期 0−0−2 〃 第二 後学期 0−0−2 |
 |
中原 凱文 教 授,石井 源信 教 授 早坂 真理 教 授,西原 明法 教 授 丸山 剛生 助教授,須田 和裕 助教授 赤間 啓之 助教授,西方 敦博 助教授 仁科喜久子 教 授,馬越 庸恭 教 授 |
人間行動システムに関する専門基礎知識ならびにその思考方法を修得するために,所属する研究室におい
て行われる研究に参加させ,行動システム及び教育工学に関する高度な演習及び実験を行わせる。人間行動
システムに関する専門的内容について,実験・演習を行う。
(Practical Exercise in Human Dynamics Design I-II)
|
教育システム講究第一 前学期 2 単 位 〃 第二 後学期 2 〃 〃 第三 前学期 2 〃 〃 第四 後学期 2 〃 |
 |
中川 正宣 教 授,牟田 博光 教 授 石塚 智一 教 授,前川 眞一 教 授 山岸 侯彦 助教授,赤堀 侃司 教 授 室田 真男 助教授,松田 稔樹 助教授 中山 実 助教授,加藤 浩 助教授 |
65731 65732 65733 65734 |
I 教育システムに関わる研究や実践を行う上で必要となる専門知識や見方・考え方を修得するために,教
育システムに関わる最新の専門学術書や論文等を読み,各自の関与している具体的テーマと関連づけて解
釈・討論したり,新たな課題や解決方法を考察することを目的とする。
II 発達・学習・思考,教育計画・教育方法・教育課程編成,科学教育・技術教育・情報教育,教育評価・
心理測定,教育メディア・教材の開発などを主な内容とする。
III 教育系各研究室に所属する学生を対象とする。
(Colloquium in Educational System I-IV)
|
行動システム講究第一 前学期 2 単 位 〃 第二 後学期 2 〃 〃 第三 前学期 2 〃 〃 第四 後学期 2 〃 |
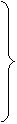 |
中原 凱文 教 授,石井 源信 教 授 早坂 真理 教 授,西原 明法 教 授 丸山 剛生 助教授,須田 和裕 助教授 赤間 啓之 助教授,西方 敦博 助教授 仁科喜久子 教 授,馬越 庸恭 教 授 |
65711 65712 65713 65714 |
学生各自が専門分野に関連のある原著論文の紹介を行い,論文に対する理解力の養成,語学の習熟,学術
講演における表現の方法および討論の訓練を行う。
人間行動システムに関する高度な研究内容について,演習を行う。
(Colloquium in Human Dynamics Design I-IV)
|
人間行動システム講究第五 前学期 2 単 位 〃 第六 後学期 2 〃 〃 第七 前学期 2 〃 〃 第八 後学期 2 〃 〃 第九 前学期 2 〃 〃 第十 後学期 2 〃 |
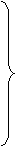 |
各教官 |
65801 65802 65803 65804 65805 65806 |
学生各自が,それぞれ専門分野に関連のある原著論文の紹介を行い,論文に対する理解力の養成,語学の
習熟,学術講演における表現の方法,討論,および論文作成の訓練を行う。人間行動システムに関する高度
な研究内容について,演習を行う。
(Colloquium in Human Dynamics Design V-X)