�k���@���@�v�@�ځl
�@
67001
�Z�p�v�V�_�iTechnological Innovation Systems�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@�n�Ӂ@�瘿�@����
��Ƃ𒆐S�Ƃ���Z�p�v�V�ɂ��Čo�ϔ��W�Ƃ̊W�Ɏ��_�𐘂��C���̗U���\������уC���p�N�g�ɂ�
���āC���ؓI�ɋ��猤������B
67002
�Z�p�����_�iTechnology Policy Systems�j
��w���@2�|0�|0�@�@�n�Ӂ@�瘿�@����
�Y�ƁE��Ƃ̋Z�p�v�V��U�������ł̐���C���x�y�ъ�Ɛ헪�̃_�C�i�~�Y���ɂ��āC���̗��_�I�g
�g�y�ю��ۓI���ʂ𑍍��I�E���ؓI�Ɍ������炷��B
This course provides a theoretical and empirical review on a dynamism in policy, institution
and firm's R&D strategy for inducing industry/firm's innovation.
67003
�i�V���i�� �C�m�x�[�V���� �V�X�e���iNational Systems of Innovation�j
2nd Semester�i2�|0�|0�j�iOdd year�j
Prof. Kumiko MIYAZAKI
The course relates to Systems of Innovation with a global and national perspective at different levels
1. Within the firm, 2. Between firms and networks of firms and other institutions,
3. National, 4. Globalization
67004
�Z�p�o�c�V�X�e���_�iStrategic Management of Technology�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@�{��v���q�@����
�i���o�ϊw�ɂ��ĊT��������ɁC��Ƃɂ����鎖�ƌo�c�헪�ƋZ�p�o�c�헪�CR��D�}�l�W�����g�C�Z
�p�����͂̒~�ωے��C�Z�p��g�헪�C��ƊԂ̋Z�p�g�y�C���ƓI�C�m�x�[�V�����V�X�e���C�O���[�o������
�����ɂ��āC�Z�p�헪�V�X�e���_�̊ϓ_�ɗ����ĉ������B
1st Semester�i2�|0�|0�j
Prof. Kumiko MIYAZAKI
This course aims to teach students the following; corporate and technological strategic planning
process, R&D management, core comptences of the firm, management of strategic alliances, National
System of Innovations, managing the globalization process.
67005
���Y�Z�p�J���헪�iProduction Management and Strategy�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@����@���v�@�����C���@�@���J�@������
�e�C���[���烊�[�����Y�����܂ł̐��Y�p���_�C���̃V�t�g��W�]������ŁCSCM�i�T�v���C�`�F�[���}�l
�W�����g�j�J���ɏd�_��u�����R���J�����g�G���W�j�A�����O�ɑ�\����邱�ꂩ��̏��Z�p���x�[�X��
�������Y�Ǘ��Z�p�̐헪���������B�܂��C����܂ł킪���̐����Ƃ̋������x���Ă����s�p�b�C�i�h�s�C
�s�o�l�ɂ��ĉ������ƂƂ��ɁC�O���[�o�����ɑΉ������C�O���_�Ɋւ���헪�ƃ}�l�W�����g�ɂ���
���ӂ��B
67006
�q���[�}���}�V���E�C���^���N�V�����iHuman-Machine Interaction�j
��w���@2�|0�|0�@�@�ɓ��@�����@����
���Y�V�X�e���̃C���^�t�F�[�X�C�����ăR���s���[�^�����p��������̍��x�}���|�}�V���E�V�X�e���̃C
���^�t�F�[�X��v����ۂɕK�v�ȍl�����C��@�E���@�_���C�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B�{�u�ł́C���ɃV
�X�e�����p�҂̐l�ԓI���ʂ���A�v���[�`����Z�@�𒆐S�Ƃ��C�F�m�H�w�̍l������C�F�m���f���̍쐬��
���@�_�Ƃ��̐v�ւ̉��p���̓��e�ɂ��Ę_���C�㔼�ɂ͍u�`�Ɋ֘A������e�̉ۑ茤�����s���B
67008
�v���Z�X�E�}�l�W�����g�iAdvanced Process Management�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@���@�����@����
���u�H�Ƃɂ����鐶�Y�ݔ��i�v���Z�X�v�����g�j�̓����Ɋ�Â����ށC���ŕ��ނ��ꂽ���ꂼ��̃v��
�Z�X�v�����g�ɑ��ĊǗ��ɕK�v�ƂȂ�v���Z�X�V�~�����[�V�����@����уv���Z�X��͖@�C����ɐ��Y��
�ɑ傫���e������v���Z�X�v�����g�̐ݔ��v��E�Ǘ��C���Y�v��E�Ǘ��C�^�]�v��E�Ǘ�����ш��S���]���E
�Ǘ����̏����@����ъ��Ǘ��ɂ��ďq�ׂ�B
67009
�}�l�W�����g���_�iAdvanced Course of Management�j
��w���@2�|0�|0�@�@�˓c�@�ۈ�@�u�t�i���j�ق�
�G���W�j�A�����O�ɕK�v�ȃ}�l�W�����g�̍l�������C��Ƃ̃g�b�v�܂��̓g�b�v�o���҂̍u�t�����ꂼ��
�̌o���Ǝ��H�̗��ꂩ��q�ׂ�B���i�J���}�l�W�����g�C�Z�p�J���C��Ƃ̊�ƊC�O�i�o�C�l������C�c��
�}�l�W�����g�C���������̂�����Ȃǖ���قȂ�e�[�}�ŁC�������ƂɌ��炸�C�L���T�[�r�X�Y�ƂɊ֘A
�����e�[�}�ɂ��Ă��b������B
67011
���p���v����iApplied Statistical Methods�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@�{��@�떤�@����
�Z�p�C�o�c�C�Љ�Ȃǂ̏�����Ɍ����s�m�茻�ۂɂ��āC������ώ@���C���f�������C���茋�ʂ���
�͂��C�������E�ł̈Ӗ����l�@���铝�v�H�w�̕��@�Ɖ��p�ɂ��ďq�ׂ�B���ϗʉ�͂Ƃ��āC���`��A��
�f���Ɗe�퐳�����͂����グ�C���_�I�ȑ��ʂƉ��p��̏����ɂ��ĉ������B
67013
�t�B�i���V�����E�G���W�j�A�����O�iFinancial Engineering�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@����@�G�q�@������
���Z�H�w�ŗ��p����鐔�����f���ɂ��Ċ�b����u�`���s���B�O���͐�n�E�X���b�v�E�I�v�V�����Ȃ�
�̉��l�]���̖{���I�ȃA�C�f�A����ъ�{�I�ȃ|�[�g�t�H���I���_�ɂ��āA��w���{���w�̒m����O���
���ĉ������B�㔼�́A�}���`���Q�[���Ƃ����T�O���x�[�X�Ƃ������Z�s��̗��U���Ԃ̊m�����f���ɂ�
�ĉ�����ABlack-Scholes�����̓��o�܂ł�ڎw���B
67014
�o�c�������_�iMathematical Science on Management�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@��@���q�@������
�o�c�H�w�̏�����ň�������͕��G�ł��邪�C������\�������C�����I�Ɏv�l���邱�Ƃɂ���Ė��
�̖{����c���ł��邱�Ƃ������B���̍\����\�o���鐔���I����Ƃ��āC���^�E����^�v��@�C�l�b�g��
�[�N�v��@����ї��U�œK���Ȃǂ��p������B�{�u�ł͉��K���\���Ɏ�����āC�����̊�b�ƂȂ鐔
�w�I���ʂ������B
67017
�r�W�l�X���V�X�e���v���W�F�N�g����iBusiness Information Systems Project II�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@��Á@�M�F�@�����E�ѓ��@�~��@����
���Ɉ��������C�O���[�v�w�K�ɂ��C�r�W�l�X���V�X�e���Ƃ����g�g�݂ŁC���V�X�e���̊J���Ɋւ�
��v���W�F�N�g�𐋍s����B��̓I�ɂ́CUML�ɂ�镪�́C�v�ɂ�����\���ƁC�I�u�W�F�N�g�w�������p
���������ɂ��Ċw�ԁB
���F���Ƃ͌����Ƃ��ĉp��ōs���B
Business Information Systems Project II
1st Semester�i2�|0�|0�j
Professor HIGA Kunihiko, Professor IIJIMA Junichi
Following Business Information Systems Project I, a project on business related information systems
development will be performed based on group learning methodology. Through a semester-long project,
students will learn how to analyze, design and implement business information systems.
67018
�Z�p�j���_�iAdvanced Course for History of Technology�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@�ؖ{�@�����@����
�Z�p�j�Ɋւ����b�I�m����O��ɂ��ċZ�p�̔��W�̘_���u�����C�Z�p�̓��I�Ș_���ƊO�I�E�Љ�I���v
���̊W�����鎋�_���猟������B�d�C�Z�p�C�@�B�Z�p�Ȃǂ̌ʕ���̋Z�p���W�̃��J�j�Y��������
�Ȃ��C�Љ�I���Y�@�\�Ƃ��Ă̋Z�p�S�̂̍\���I�ȓW�J�ߒ��������B�A���C�A�v���[�`�̎d���́C���N�ق�
��̂ŁC����̎��Ƃɂ͕K���o�Ȃ��邱�ƁB
67019
�Ȋw�E�Z�p�E�Љ���_�iAdvanced Course for Science & Technology Studies�j
��w���@2�|0�|0�@�@�����@�G�l�@������
���̎��Ƃł́C�Ȋw�Z�p�j�C�Ȋw�Z�p�Љ�w�C�Ȋw�Z�p�Љ�_�i�r�s�r�j�Ȃǂ̐��Ƃ������ڎw����w
�@����ΏۂƂ��āC���ƂƂ��čŒ���m���Ă����ׂ��m�����K�����邱�Ƃ�ڕW�Ƃ���B��̓I�ɂ͊w�p
�����_���⏑�Ђ̓lj��̕��@�Ȃǂ��擾���邱�Ƃ�ڂ����B�Ȃ��C�Q���҂ɂ���ē��e��ύX���邱�Ƃ��L
�蓾��̂ŁC����̃I���G���e�[�V�����ɂ͕K���o�Ȃ��邱�ƁB
67020
��r�Ȋw�j���_�iHistory of Science in Regional and National Contexts�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@���@�@��́@������
�Ȋw�̐��x���E�E�Ɖ����͂��܂�C�Ȋw�̎Љ�I�Ȃ�������傫���ω����C�܂��Ȋw�ƋZ�p�̊֘A������
����Ă����C19���I�ȍ~����̌���ɒʂ���Ȋw���W�̌`�Ԃɑ���n�搫�̂������̉e���ɂ��āC���j
�I���ጤ����ʂ��Č�������B�p���ƂȂǐ�������A�����J�ł�19���I�����20���I�ɂ�����Ȋw�̐��x��
�̐i�s�̎d����C���\�A�Ȃǂ�����u�Љ��`�v���ł̉Ȋw�ƍ��Ƃ̊W�C�m���ł̉Ȋw���W�C�A��
�n�ɂ�����Ȋw�̑��`�ԁC���{�ɂ�����Ȋw�E�Z�p�̓����Ɣ��W�ߒ��Ȃǂ��ʂɂƂ肠���Ę_����B��
���e�[�}�͌����Ƃ��Ė��N�قȂ�B
67021
�Ȋw�Љ�j���_�iAdvanced Course in Social History of Science�j
��w���@2�|0�|0�@�@�R��@�����@����
�Ȋw�̐������߂����\�I�Ș_�_�𑍍��I�Ɍ������C�Ȋw�������C���W����ׂ̎Љ�I�C�v�z�I�v�����C
���،����܂��Ȃ��猟����B���킹�Č���̃r�b�O�E�T�C�G���X�𐬗�������Љ�I���Ƃ��Ċ֗^
���Ă��鏔�����C���j�I���ጤ����ʂ��Č�������B
67022
�_���E�Ȋw���@�_�iLogical Foundation of Methodology of Science�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@�m�J�@�q���@����
�Ȋw�y�ыZ�p�ɑ�\�����l�Ԃ̍����I�����̍���͘_���ɂ���Đ�����Ă���B����͑O���I����
�獡���I�����ɂ����Ę_���w�͐��w�I�ɐ�������C���݂ł͐����_���w�Ƃ��āC�Ȋw�I���_�̊�b��^����
�ƂƂ��ɁC�Ⴆ�Όv�Z�@�Ȋw�ȂǂɌ�����悤�ɋZ�p�I���p�ʂł̏d�v�Ȗ�����S���Ă���B�{�u�ł́C
�����_���w��l�Ԓm���̕\��������i�Ƃ��čl�@���C�ʏ�g�p����Ă��鐔���_���̌n�����_��K��
�Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃ����݁C���̌��ʓ���ꂽ�����_���̌n�̃��^�_���I�����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ�
��B
67023
���Ƒn�o�_�iPractical Business Establishment�j
�O�w���@1�|1�|0�@�@�S���{�ق��i���j
�V�K���Ƃ̗����グ�����Ƃ����̉ߒ��ɂ����ĕK�v�Ƃ������E�}�[�P�e�B���O�E�����E�Z�p�Ǘ��E�g
�D�Ǘ��Ȃǂ̏��Z�@�ɂ��Ď��H�I�ȗ��ꂩ�������C���ƌv�旧�Ă̂��߂ɕK�v�Ȓm������ыZ�\�̏K��
��ڎw���B���Ɗ��Ԃ�ʂ��Ď��ۂɎ��ƌv�揑���쐬�����\���邱�Ƃɂ����H�I�Ȓm����g�ɂ���B
67024
�o�c�v���Z�X�]���iEvaluation of Business Processes�j
��w���@2�|0�|0�@�@�I�J�@�L�F�@������
��Ɖ��l�̑n�����ƕϊv�Ȃǂɂ����āC�e�r�W�l�X�E�v���Z�X�𐮍��I�C�����I�ɉ��P���邱�Ƃ����
�o�c�ɂƂ��ĕs���ƂȂ��Ă���B�����ŁC��ƌo�c�ɂ�����ŐV�̃g�s�b�N�����グ�C�r�W�l�X�E�v��
�Z�X�Ƃ������_����T������B
67025
�Ȋw�j�Z�p�j�Ȋw���@�_I�iAdvanced course for History and Methodology of Science and Technology�j
�O�w���@�@2�|0�|0�@�@�ؖ{�@�����@�����C�R��@�����@�����C�m�J�@�q���@����
�����@�@��́@�������C�����@�G�l�@�������@�ق�
�Ȋw�j�E�Z�p�j�E�Ȋw���@�_�̏d�v�ȃe�[�}�����グ�āC�����[�u�`�`���ōu�`����B���킹�ă[�~�`
���ł̊�b�����u�ǁE���\�E���_���K�X�s���Ă����B�{�u�`�ł͉Ȋw�j�E�Z�p�j����щȊw���@�_�̊�b�m
����O��Ƃ��āC��荂�x�Ȑ�勳����߂����Ă���B
67026
�Ȋw�j�Z�p�j�Ȋw���@�_�U�iAdvanced Course for History and Methodology of Science and Technology�j
��w���@�@2�|0�|0�@�@�ؖ{�@�����@�����C�R��@�����@�����C�m�J�@�q���@����
�����@�@��́@�������C�����@�G�l�@�������@�ق�
I�ɑ����āC�Ȋw�j�E�Z�p�j�E�Ȋw���@�_�̏d�v�ȃe�[�}�����グ�āC�����[�u�`�����ōu�`����B��
�킹�ă[�~�`���ł̊�b�����u�ǔ��\�E���_���K�X�s���Ă����B�{�u�`�ł͉Ȋw�j�E�Z�p�j����щȊw���@
�_�̊�b�m����O��Ƃ��āC��荂�x�Ȑ�勳����߂����Ă���B
67028
���l�I�œK�����_�iNumerical Optimization�j
�O�w���@�@2�|0�|0�@����@�����@����
�œK���Ƃ������_����o�c�H�w��̏��������f�����O���邽�߂̋Z�p�Ɛ��l�I�ɖ����������߂̃A��
�S���Y���̏C����ړI�Ƃ���B�������f���Ƃ��āC���v����C2���v����C����`�v����C������C
������l�v����C�l�b�g���[�N�t���[���C�g�����œK�����Ȃǂ������B
67030
����v�_
��w���@1�|0�|0�@�@���c�@�Ǔ�@�u�t
��Ƃ̊����Ɋւ���v���Ǘ�����ыq�ϓI�ȏ��J���̕K�v���̊ϓ_����C����v�E�̌�����T��
����ƂƂ��ɁC ����̑傫�ȉۑ�Ƃ��������������Ɍo�σV�X�e���Ɏ�����邩�Ɋւ��C���Ǘ���
�v�̎�@��r�o�ʎ���Ȃǂ� ����Ƃ��ė��_�I�������s���B
67031
�����t�@�C�i���X�iMathematical Finance�j
��w���@�@2�|0�|0�@��{�@�ˈ�@������
�ߔN�C�����H�w�܂��͋��Z�H�w�ƌĂ�镪�삪���ڂ𗁂тĂ���B����́C���Z�������̍��x���ƃ�
�X�N�Ǘ����Љ�I�ɔ��ɏd�v�ɂȂ��Ă��Ă��邱�ƂɑΉ����C�����̉ۑ�𐔊w�I�^�H�w�I�ɍ�������
���Ƃ������̂ł���B�{�u�`�ł́C�����t�@�C�i���X�̍ŋ߂̘b��̒�����C�ЂƂ̃g�s�b�N���Ƃ肠���C
�������B
67032
�r�W�l�X���V�X�e���v���W�F�N�g����iBusiness Information Systems Project I�j
��w���@2�|0�|0�@�@�����@��@�������E�ѓ��@�~��@����
�O���[�v�w�K�ɂ��C�r�W�l�X���V�X�e���Ƃ����g�g�݂ŁC���V�X�e���̊J���Ɋւ���v���W�F�N�g��
���s����B��̓I�ɂ́C���z�x���c�[���̗��p��^�t�@�[�̗��p�C���[�N�f�U�C���C�\�t�g�V�X�e���Y�A�v
���[�`�C�Ȃǂ̖��ݒ�Ƃ��̒莮���̎d���ɂ��Ċw�ԁB
���F���Ƃ͌����Ƃ��ĉp��ōs���B
Business Information Systems Project I
2nd Semester�i2�|0�|0�j
Associate Professor SENOO Dai, Professor IIJIMA Junichi
Based on group learning methodology, a project on business related information systems development
will be performed. Through a semester-long project, students will learn how to set and formulate a
problem including the usage of an idea generation tool and a metaphor, work design, and soft systems
approach.
67033
Globalization, Technology and Enterprize Development
2nd Semester�i2�|0�|0�j
����
67034
Global Technology and Technoprenuership: A Comparison of International Institutional Systems
1st Semester�i2�|0�|0�j
����
67037
�l�b�g�Љ�̃r�W�l�X�iBusiness in The Net-Society�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@��Á@�M�F�@�����E�����@�@��@������
�l�b�g�Љ�ɂ����鋣���̋K�͂ƃX�s�[�h�Ɋ����̊�Ƃ��ǂ��Ή����Ă��邩�C���ɏ��E�ʐM�Z�p�̊�
�p���@�ɂ��Ċw�ԁB����ɁC�V���ȃr�W�l�X�`�����X�Ƃ��Ẳ��z�g�D�E���z�`�[����d�q������ɂ�
�Ă��w�ԁB�w���͂��ꂼ��̃g�s�b�N�ɂ���1�i�v2��j�_����ǂ�Ŕ��\���s���B
���F���Ƃ͌����Ƃ��ĉp��ōs���B
Business in The Net-Society
1st Semester�i2�|0�|0�j
Professor HIGA, Kunihiko Associate Professor SENOO Dai
The new business challenges and opportunities brought by the networked society will be studied in
this class. Particularly the use of information and communication technology by organizations to
respond to the challenges and to take the opportunities will be discussed. The students will be asked
to read two research papers (one for each topic) and make an in-class presentation for each paper.
67038
�v���_�N�g�E�f�U�C���Ɛl���iProduct Design and Human�j
1st Semester�i2�|0�|0�j
Hiroyuki UMEMURO
The goal of this course is to understand the concept and applications of human-centered product
design. Subjects include understanding physiological and psychological characteristics of human, aging
and gerontechnology, and universal design.
67052
�N�������iPension Mathematics�j
�O�w���@2�|0�|0
�ٗp���s�̕ω��Ŋ�ƔN�����傫���ϖe�����邪�C�{�u�`�ł͔N��������̌n�I�ɍu�`����Ƌ��ɁC��
�x���Ƃ�܂����ω��Ⓤ�����_�ւ̉��p���ɂ��Ă����y����B
(1)�N�����x�_�G���I�N���C�ސE���t��v�C��s���x
(2)�N�������G��b���C�����C���x�����C���������C���v���f����
(3)�������_�ւ̉��p�G���]���CMPT�C���Y�z���C�N��ALM
|
67701 |
�o�c�H�w�u����� |
�O�w�� |
1�P�� |
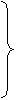 |
�e���� |
|
67702 |
���@�@�@�@�@��� |
��w�� |
1�P�� |
||
|
67703 |
���@�@�@�@�@��O |
�O�w�� |
1�P�� |
||
|
67704 |
���@�@�@�@�@��l |
��w�� |
1�P�� |
�iColloquium in Industrial Engineering and Management I-IV�j
�Z�p�E�����Ǘ���Z�p����E�v�V�_�C�Z�p�̔��W�\����Z�p�j�C���Y�E�i���Ǘ��C�̔��E���ʊǗ��C�v��
�Z�X�Ǘ��C�����E�o�c�Ǘ��C�I�y���[�V�����Y�E���T�[�`�C�}���E�}�V���E�C���^�t�F�[�X�C���Z�p�Ȃ�
�̕��삩��I�����������e�[�}�ɂ��āC�����E���́E�����Ȃǂ��s���B
67711�C67712
|
�o�c�H�w���ʉ��K��� |
�O�w�� |
0�|1�|0 |
 |
�e���� |
|
���@�@�@�@�@�@�@��� |
��w�� |
0�|1�|0 |
�iSeminar in Industrial Engineering and Management I-II�j
�o�c�H�w�̈�����v�e�[�}�ł����Ƃ�g�D�̊Ǘ��E�^�c�Ɋւ���X�̖��ɂ��āC���̉����ɕK�v
�ȍl������T�O�C�����ŗ��p����Z�@����@�_�Ɋւ��āC�����O�̒����E�_���̗֓ǂⓢ�`��ʂ��Đ��I
�m���̏K�����s���B���ł͓��ɂ��ꂼ��̕���Ō�����i�߂Ă�����Ŋ�{�ƂȂ���m�����C���ł�
���ꂼ��̕���̍Ő�[�̐��m���C���тɋZ�p�������K��������B
67721�C67722
|
�o�c�H�w���ʎ������ |
�O�w�� |
0�|0�|1 |
 |
�e���� |
|
���@�@�@�@�@�@�@��� |
��w�� |
0�|0�|1 |
�iPractical Exercise in Industrial Engineering and Management I-II�j
�o�c�H�w�̈�����v�e�[�}�ł����Ƃ�g�D�̊Ǘ��E�^�c�Ɋւ���X�̖��ɂ��āC���K�C�������s
���C���̌��ʂ̃v���[���e�[�V�����ⓢ�_��ʂ��āC�o�c�H�w�Ɋւ��錤�����s���\�͂�{���B���C���
�̋�ʂ́C�w���̐i�W�ɑΉ������ď������C�̍��x����}����̂Ƃ���B
|
67801 |
�o�c�H�w�u����� |
�O�w�� |
2�P�� |
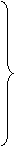 |
�e���� |
|
67802 |
���@�@�@�@�@��Z |
��w�� |
2�P�� |
||
|
67803 |
���@�@�@�@�@�掵 |
�O�w�� |
2�P�� |
||
|
67804 |
���@�@�@�@�@�攪 |
��w�� |
2�P�� |
||
|
67805 |
���@�@�@�@�@��� |
�O�w�� |
2�P�� |
||
|
67806 |
���@�@�@�@�@��\ |
��w�� |
2�P�� |
�iColloquium in Industrial Engineering and Management V-X�j
�o�c�H�w�̈�����v�e�[�}�ł����Ƃ�g�D�̊Ǘ��E�^�c�ɕK�v�ȍl������T�O�C�����Ă����ŗ��p����
�Z�@����@�_�̍\�z���Ɋւ��錤���ɂ��ăe�[�}��I�сC�֍u�ɂ��ŐV�Z�p�E�m���̏K���C�����v���
���āC�����E�����C���_�C�_���쐬�Ȃǂ�ʂ��ďC��������B
67035
IP�}�l�W�����g����iIntellectual Property Management I�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@���{�@�����@����
�m�I���Y���ɂ��āC���̈Ӗ��C���Ƃ���ъ�Ƃ̐헪���T�����C�m�I���Y���̏d�v�����K��������B�܂��C
�����擾�ɂ��|�[�g�t�H���I�̍\�z�C�m�I���Y�̕]���C���p�ɂ��ĊT������B
67036
IP�}�l�W�����g����iIntellectual Property Management II�j
��w���@2�|0�|0�@���{�@�����@�����E���c�@����@�����E�i�c�@���q�@�u�t
�������C�Z���X�_���������ѓ������p�̎��Ԃ��u�`���C�Y�w�A�g�C�Z�p�ړ]�@�ցiTLO�j�ɂ��ĊT������B����ɁC�m�I���Y���̉��l�]���̂��߂̒m�I���Y��v�ɂ��ču�`����B
67039
���ےm�I���Y����iInternational Intellectual Property I�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@�c���@�`�q�@������
�m�I���Y���̊�b�I��������n�܂�C���ۏ��C����C�e�����x���w�тȂ���C�m�I���Y�̖����𗝉���
�Ă����B�܂��C���ۓI�Ȓm�I���Y�̗��j��U��Ԃ�C���̖����̑��l���𗝉�����B���ĉ��̎O�ɂ̊ȒP��
���x��r�����݂�B
67040
��[�Z�p�ƒm�I���Y���iHigh-technology and Intellectual Property Rights�j
��w���@2�|0�|0�@�@�����@�Ƃ��q�@�����E���{�@�����@�����E�c���@�`�q�@�������@�ق�
���C�o�C�I�e�N�m���W�[�C�r�W�l�X���f���C�\�t�g�E�G�A���̐�[�Z�p����ɂ�����m�I���Y���̕ی��
���ĉ������B
67045
�m�I���Y�W�������iPractice regarding Disputes of Intellectual Property Rights�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@���J�@�����@�q������
�����N�Q�i�ׂȂǂ̌W���Ɋւ��C���C�a���葱�C�i�葱�Ȃǂ̎������u�`����B�O���ł̌W���ɂ�
�Ă��Δ�I�ɉ������B
67046
�m�I���Y����������iPractice I for Intellectual Property Rights�j
�O�w���@1�|1�|0�@�@�����@�Ƃ��q�@�����E�H���@�Ύi�@�u�t�i���j
���W���y�ѓ������擾�̂��߂́C�o�肨��ђ��ԏ����葱�ɂ��ču�`���C��̓I����ɉ����āC�葱�̉�
�K���s���B
67047
�m�I���Y����������iPractice II for Intellectual Property Rights�j
��w���@1�|1�|0�@�@�����@�Ƃ��q�@����
�������擾�̂��߂̂�荂�x�Ȏ葱�ł��鋑�⍸��s���Ȃǂ̐R�������葱����ѐR������i�葱�Ȃ�
�тɓ������ɑ��閳���\���̂��߂̎葱�ɂ��ču�`����B����ɁC��̗�ɂ�肱���葱�̉��K���s���B
67048
�m�I���Y���i�ז@�iThe Code of Intellectual Property Rights Procedure�j
��w���@2�|0�|0�@�@���J�@�����@�q������
�����N�Q�i�ׂɑ�\�����m�I���Y�������E�i�ׂɂ��āC���_�Ǝ����̗��ʂ���u�`����B
67049
�m�I���Y���@����iIntellectual Property Rights Law I�j
�O�w���@2�|0�|0�@�@�{�_�@�@���@�q���������E�H���@�Ύi�@�u�t�i���j
�m�I���Y���@�ɂ��ĊT�����C���ɁC�Y�ƍ��Y���@�i�H�Ə��L���@�j�ł�������@�C���p�V�Ė@�C�ӏ��@�C
���W�@�ɂ��ĉ������B
67050
�m�I���Y���@����iIntellectual Property Rights Law II�j
��w���@2�|0�|0�@�@����@�@���@�q�������E���c�@���g�@�u�t�i���j�@�ق�
���쌠�@�C�s�������h�~�@�C�Ɛ�֎~�@�ɂ��ĉ�����C����ɁC�p�����ȂǏ��ɂ��ĉ������B
67051
�m�I���Y���Ǘ��iInformation Management of Intellectual Property Rights�j
�O�w���@0�|1�|0�@�@�����@�Ƃ��q�@����
�m�I���Y�֘A�����C�e���������Ȃǂ̒m�I���Y�֘A���ɂ��Ď��W�C��́C�f�[�^�x�[�X�̍쐬�Ȃ�
�̉��K���s���B
67054
���ےm�I���Y����iInternational Intellectual Property II�j
��w���@2�|0�|0�@�@�c���@�`�q�@������
�m�I���Y���߂��鍑�ۓI�������T�ς��C��Ƃ��\�z���ׂ����ۓI�����헪���l����B�܂��C�R�s�[���i��
���ᓙ��p�����O���[�v�f�B�X�J�b�V������ʂ��C��Ƃ����ېi�o���Ă����ۂ̗��ӎ����Ȃǂɂ��ė���
��[�߂�B
|
67731 |
�m�I���Y�}�l�W�����g���ʉ��K��� |
�O�w�� |
0�|1�|0 |
 |
�e���� |
|
67732 |
���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��� |
��w�� |
0�|1�|0 |
�iSeminar in Intellectual Property Management I-II�j
�m�I���Y�}�l�W�����g�̈�����v�e�[�}�ł����ƁCTLO���̒m�I���Y�擾�Ǘ��E���p�Ɋւ����X�̖��
�ɂ��āC���̉����ɕK�v�ȍl������C����ɗ��p����Z�@����@�_�Ɋւ��āC�����O�̒����E�_���̗֓ǂ�
��ѓ��c��ʂ��Đ��I�Ȓm���̏K�����s���B���ł́C���ɁC�m�I���Y�}�l�W�����g�̕���Ō�����i��
�Ă�����Ŋ�{�ƂȂ���m�����K��������B���ł́C�m�I���Y�}�l�W�����g�̕���̍Ő�[�̐��m���C
���тɋZ�p�������K��������B
|
67741 |
�m�I���Y�}�l�W�����g���ʎ������ |
�O�w�� |
0�|0�|1 |
 |
�e���� |
|
67742 |
���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��� |
��w�� |
0�|0�|1 |
�iPractical Exercise in Intellectual Property Management I-II�j
�m�I���Y�}�l�W�����g�̈�����v�e�[�}�ł���m�I���Y�̎擾�C���C�Z���V���O�C�����������̃}�l�W����
�g�ɂ��āC���K�C�������s���C���̌��ʂ̃v���[���e�[�V�����ⓢ�_��ʂ��āC�m�I���Y�}�l�W�����g
�Ɋւ��錤�����s���\�͂�{���B���C���̋�ʂ́C�w���̐i�W�ɑΉ������ď������C�̍��x����}���
�̂Ƃ���B
|
67751 |
�m�I���Y�}�l�W�����g�u����� |
�O�w�� |
1�P�� |
 |
�e���� |
|
67752 |
���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��� |
��w�� |
1�P�� |
||
|
67753 |
���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��O |
�O�w�� |
1�P�� |
||
|
67754 |
���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��l |
��w�� |
1�P�� |
�iColloquium in Intellectual Property Management I-IV�j
�m�I���Y���̕ی�C�W���C���C�Z���V���O�C���� �C���ۓI�n�[���i�C�[�[�V�����C�헪�I�Ǘ��Ȃǂ̕��삩
��I�����������e�[�}�ɂ��āC�����E���́E���������s���B