〔教 授 要 目〕
68002
国土のシステムデザイン(Socio-physical System Design for Human Settlements)
後学期 2−0−0 肥田野 登 教授
国土システムデザインの最も根源となる基本的な社会システムのデザイン(空間ではない)論理及び21世
紀の最大の社会問題の一つである幸福追求の基礎となる自己概念について深く理解をする。特にカール・ポパ
ー,デレクパーフィット,フロイト,批判的社会学,岩田慶治,クリシュナムルティを扱う。
The purpose of this lecture is to discuss the basic concept of the relationship between environment
and man. The special emphasis is given to the philosophical perception of self in order to consider
environment. The fundamental knowledge of philosophy and neo-classical economics are highly required.
68003
都市空間利用計画特論(Advanced Theories and Practies of Urban Land Use Planning)
後学期 2−0−0 中井 検裕 教授
都市の諸活動を空間利用という視点からとらえ,その計画手法と実現手法さらには計画策定のプロセスに
ついて論ずる。
This lecture discusses the theories and practices of various land use planning techniques. The
English lectures will be provided in an intensive form, separately from the Japanese class. Those
students who wish to participate the English class should contact directly to the lecturer at the
beginning of the semester.
68005
経済システムと政策特論(Advanced Theory of Economic System and Policies)
前学期 2−0−0 金子 昭彦 助教授
個人および企業の最適な経済行動を考えることにより経済成長の決定要因について学び,さらに国際社会
において各種の政策が経済成長にどのような影響を与えるのかについて学ぶ。
This cource develops core models of dynamic macroeconomics and economic growth. The topics
treated include : exogenouse and endogenous growth model ; monetary depression model.
68006
市場メカニズムと政策特論(Advanced Theory of Market Mechanism and Policy)
後学期 2−0−0 内藤 巧 助教授
経済学者は決して自由放任主義者ではない。市場がうまく働かないときには,政府が行動する余地がある。
例えば,地球温暖化問題を解決するためには,経済取引を規制したり(炭素税),新たな市場を作ったり(排
出権取引)することが有効である。この講義では,市場の失敗(外部性,不完全競争など)の経済学的帰結
を理解し,適切な政策を探ることを目指す。
68007
公共政策特論(Advanced Theory of Public Policies)
前学期 2−0−0 宮嶋 勝 教授
本講義では(1)政策形成の基礎理論,(2)政策効果の評価理論,(3)政策形成のケース・スタディを中心に講義
する。
68008
計画組織デザイン特論(Organizational Design for Planning)
後学期 2−0−0 坂野 達郎 助教授
計画組織の設計と改善を行うためには,環境条件に適応的な計画過程と組織構造の特質を理解することが
不可欠である。本特論では,不確実性と価値対立を克服する情報処理過程の視点から既存理論の紹介を行い,
変動の激しい環境に柔軟に対応できる高度な学習機能を持つ計画組織の設計理論を修得することをねらいと
する。
68010
公共空間デザイン特論(Advanced Topics of Civic Design)
前学期 2−0−0 斎藤 潮 教授
景観あるいは風景という概念を通 して人間と環境との関係を考察した上で,公共空間のデザインの意味を
論ずる。
68013
社会計画特論(Advanced Course of Social Planning)
前学期 2−0−0 矢野 眞和 教授
具体的な社会問題を取り上げて,社会経済システムの諸理論と社会計画の関係を理論的に把握し,社会的
資源の配分・分配ルールのあり方を考察する。
68014
公共性の社会学特論(Sociology of the Public)
前学期 2−0−0 土場 学 助教授
「公共性」を鍵概念として,現代社会において望ましい社会制度を構築するための基本的な論理と思想に
ついて社会学的な観点から考察していく。
68031
公共理念特論(Philosophy and Public Ideas)
前学期 2−0−0 宇佐美 誠
本特論では、公共政策の評価・提言に際して不可欠である公共的な理念・概念を取り上げ、哲学・法哲学・
政治哲学の現代の重要文献を素材として、理念の構造、他の理念との関係、政策的含意などを考察する。2004
年度の主題は平等である。
A normative study of the concept of equality. Topics include its meanings, relationship to other
concepts such as justice and liberty, and implications for public policy. Readings taken from
contemporary works in philosophy, the philosophy of law, and political philosophy.
68032
都市デザイン・まちづくり特論(Advanced Theories and Practices of Urban and Community Design)
前学期 2−0−0 真野 洋介 助教授
20世紀に大きく展開した都市デザイン・まちづくりの世界の広がりと可能性について,都市・建築の実体
的空間,デザイン手法とプロセス・仕組みを社会工学的視点から解説する。
68015
環境経済・政策特論(Frontier of Environmental Economics and Policy Studies)
後学期 2−0−0 ○増井 利彦 助教授
地球環境問題や環境リスクなどの新しい環境問題への対応,それに環境産業の成長や発展途上国への支援
の拡大など新しい政策ニーズの登場によって,環境経済学や環境政策の研究は最近になって大きな進展を遂
げつつある。本講義では,これらの研究の国際的なフロンティアをわかりやすく説明し,最新の研究トピッ
クを環境経済学や環境政策学の基礎理論に言及しながら解説する。
68027
環境経済理論特論(Theory of Environmental Economics)
後学期 2−0−0 日引 聡 助教授
環境経済学の基礎的な理論を講義する。講義は,以下の項目について,英語の論文,あるいは,大学院レベ
ルの教科書を配布し,それを解説する。
(1)外部費用と市場の失敗,(2)環境税と市場の最適規模,(3)不確実性と政策手段の選択〜価格調整か数量
調整か,(4)自動車公害対策の経済理論,(5)損害賠償責任と企業の製品品質の選択,(6)不法投棄と廃棄物政
策に関する経済理論,(7)市場の失敗と社会的割引率,(8)排出権制度と技術開発投資,(9)自主的アプローチ,
(10)スットク外部性とフロー外部性
なお,履修を希望する学生は,経済学の基礎理論および環境経済・政策論Iを履修し,単位修得済みか,そ
れと同等(西村和雄著『ミクロ経済学』東洋経済が理解できる程度が必要)の学力であることが必要である。
68028
地球環境と経済発展のモデリング(Modeling of Global Environment and Economic Growth)
前学期 1−1−0 ○増井 利彦 助教授・小林 由典 非常勤講師
地球温暖化や酸性雨などの地球規模で生じている環境問題を分析するためには,人口増加,経済成長,エ
ネルギー需給,技術革新,土地利用変化,食糧需給などとの関係に基づいて,地球環境の変化をシミュレー
トするコンピュータ・モデルの修得が不可欠となる。本講義では,世界の最先端で用いられているこれらの
シミュレーション・モデルについて,背景となる基礎理論とともにわかりやすく紹介し,これらを実際に用
いて地球環境問題の意味を数量的に理解させる。
68030
公共経済学特論(Advanced Public Economic)
前学期 2−0−0 小西 秀樹 教授
上級レベルの公共経済学の理論について論文などを輪読する。扱うテーマは,厚生経済学の基本定理,外部
性の解決策,最適課税理論,公共財の理論などである。ミクロ経済学の基礎を修得していることが必要である。
68018
リサーチデベロップメント特論(Research Methodology for Social Engineering)
前学期 2−0−0 ○土場 学 助教授・金子 昭彦 助教授・十代田 朗 助教授
社会工学における研究の方法について述べる。文献の調査方法,資料の取得方法にはじまり,研究論文の
構成,形式などの標準形を理解させる。修士課程における必修科目であり,博士後期課程においては推奨科
目である。集中講義形式で開講する。
68019
社会工学の政策と計画特論(Policies and Planning Practices in Social Engineering)
前学期 2−0−0 中井 検裕 教授・肥田野 登 教授・非常勤講師
情報,金融,中央政府官庁,地方自治体,公共企業,流通などにおける政策と計画の実際において直面す
る諸問題について論じ,社会工学的解決の実際を理解させる。
The lecture invites guest speakers and explains how social engineering is applied to problems in the
real world.
68611,68612,68613,68614
|
社会工学特別演習第一 |
前学期 |
0−1−0 |
|
各教官 |
|
同 第二 |
後学期 |
0−1−0 |
||
|
同 第三 |
前学期 |
0−1−0 |
||
|
同 第四 |
後学期 |
0−1−0 |
(Advanced Experiments in Social Engineering I−IV)
学生の希望と指導教官の助言によって決めたテーマについてまとめあげる演習,実験であり,高度の知識
と技術を実際に即して修得させる。
The aim of this cource is to master the expert knowledges and technics for each research topics.
Those who are interested in this seminar should apply to a member of the faculty who are responsible
for the curriculum.
68020
社会工学計画特別演習(Advanced Planning Exercises in Social Engineering)
後学期 0−0−2 ○中井 検裕 教授・坂野 達郎 助教授
与えられた社会経済的,地域的問題をある一定の側面から把握し,利用可能な人的時間的物的資源を効率
的に使用し,コンセプト的解決案を提示できるような開発・施設・政策・制度プロジェクトを運営していく
ためのプロポーザルを作成する。学生には実社会における活動への参加を通して,理論と実践の連携を認識
させる。
In this course, we study the modern economic theory of consumption, saving and investment. In the
latter half, we apply the theory to investigation into international trade.
68033
空間設計特別演習(Advanced Exercises in Space Design)
前学期 1−0−1 ○斎藤 潮 教授・奥山 信一 助教授・土肥 真人 助教授
空間を計画・設計するのに最低限必要な基礎知識として,空間把握・解釈法,空間の操作および統合の技法,
空間表現・空間計画の技法,方法および日本の代表的空間について講述する。また,空間を表現する道具と
しての図面について,演習を通じて学習させる。
(1)空間の把握
・身体を用いた空間計測,・空間スケール,・地形構造、・地被と地物,・要所把握,・人間活動,・歴史的意義
(2)空間の計画と表現
・現況把握と評価,・問題抽出と解決,・統合
68034
社会工学数理特別演習(Advanced Mathematical Methods for Social Engineering)
後学期 1−1−1 ○樋口 洋一郎 教授・肥田野 登 教授
社会工学における問題解決のための数理的手法である(1)統計(2)回帰分析と多変量解析(3)数理計画法の基礎を
学習する。(1)統計においては,基礎概念,推定(最尤法)と検定及び離散統計,(2)回帰分析と多変量
解析にお
いては,連続・離散的変数(量と質)の扱いに注意しつつ,重回帰分析の基礎と応用,主成分分析,クラスター分
析,判別分析,確率選択理論,そして(3)数理計画法においては,線形計画法,非線形計画法の基礎,最適化手
法等を学習する。各分野ごとにコンピュータ・パッケージを利用した演習・実験を行う。
68035
コンピュータネットワーク特別演習(Advanced Exercises of Computer Network)
前学期 0−0−1 櫻井 成一朗 助教授
コンピュータリテラシーの習得を目的とし,情報収集,分析処理,コミュニケーション・表現方法としてのコン
ピュータおよびネットワークの利用法を,ワークステーションを用いた演習を通じて学ぶ。(1)UNIXシステム
(2)文書の入力(3)電子メール(4)インターネット(5)統計分析とグラフィクス処理(6)レポートライティングとDTP
68601,68602,68603,68604
|
社会工学特別研究第一 |
前学期 |
0−1−0 |
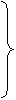 |
各教官 |
|
同 第二 |
後学期 |
0−1−0 |
||
|
同 第三 |
前学期 |
0−1−0 |
||
|
同 第四 |
後学期 |
0−1−0 |
(Studies on Special Topics I−IV)
学生の論文投稿,学会発表のインセンティブとして設け,各自の研究論文のドラフトを題材に,自己のテ
ーマが深まるよう議論する演習形式の科目である。履習希望者はあらかじめ社会工学専攻の教務担当教官ま
で申し出ること。
The aim of this study is to promote to present academic papers in academic society. A student should
apply to a member of the faculty who is responsible for the curriculum whether his/her proposal can
be eligible to this study before the course starts.
68501,68502,68503,68504
|
社会工学特別講義第一 |
前学期 |
2−0−0 |
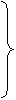 |
各教官 |
|
同 第二 |
後学期 |
2−0−0 |
||
|
同 第三 |
前学期 |
2−0−0 |
||
|
同 第四 |
後学期 |
2−0−0 |
(Special Seminar in Social Engineering I−IV)
その時々の社会的な話題について,現実世界における社会工学の実践を通じて,社会工学的問題解決のあ
り方を学ぶものである。履習希望者は,あらかじめ社会工学専攻の教務担当教官まで申し出ること。
Those who are interested in this seminar should apply to a member of the faculty who are responsible
for the curriculum.
|
社会工学講究第一 |
前学期 |
2単位 |
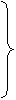 |
各教官 |
68701 |
|
同 第二 |
後学期 |
2単位 |
68702 |
||
|
同 第三 |
前学期 |
2単位 |
68703 |
||
|
同 第四 |
後学期 |
2単位 |
68704 |
(Seminar in Social Engineering I−IV)
学生の希望と指導教官の助言によって研究テーマを設定し,それに関連した文献の論講,実験,調査を通
じて研究事項の討論を行う。前期課程における必修科目であり,順を追って履修しなければならない。
The Seminars are requisites for Master course students.
|
社会工学講究第五 |
前学期 |
2単位 |
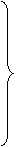 |
各教官 |
68801 |
|
同 第六 |
後学期 |
2単位 |
68802 |
||
|
同 第七 |
前学期 |
2単位 |
68803 |
||
|
同 第八 |
後学期 |
2単位 |
68804 |
||
|
同 第九 |
前学期 |
2単位 |
68805 |
||
|
同 第十 |
後学期 |
2単位 |
68806 |
(Seminar in Social Engineering V−X)
博士後期課程における必修科目であり,博士後期課程相当の高度の論講,実験,調査,製図などからなる。
The Seminars are requisites for Doctor course students.
68021,68022
| プランニングアドミニストレーション A |
前学期 |
0−1−0 |
 |
各教官 |
68021 |
| 同 B |
後学期 |
0−1−0 |
68022 |
(Planning Administration A/B)
「社会人大学院プログラム」の博士後期課程における学科目であり,AとBを合わせて履修しなければな
らない。その内容は,研究テーマに即した程度の高い論講,演習,実験を行う。