東工大ニュース
東工大ニュース
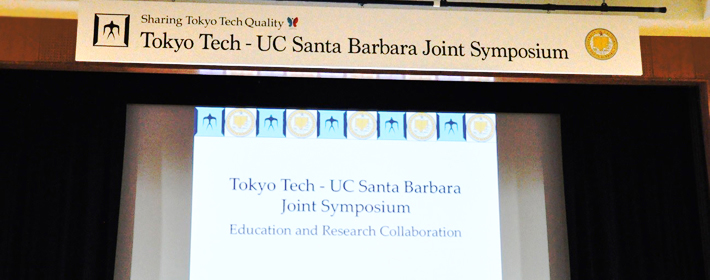
2014年4月に締結したカリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)との全学協定に基づく連携強化を目指し、同大学の学長、教員および学生を東工大に招き、2015年8月26日(水)~28日(金)の3日間の日程で合同シンポジウムが開催されました。
プログラム
1日目、この日午後から始まったシンポジウムは、東工大の三島良直学長とUCSBのヘンリー・T・ヤン学長の挨拶から始まりました。両学長が、それぞれ大学概要と両大学の交流への期待と展望について語った後、東工大の安藤真理事・副学長(研究担当)とUCSBのティム・チェン研究担当副学長補佐が、各大学における研究の強みや特徴、研究施設等について説明しました。

三島良直学長

ヘンリー・T・ヤンUCSB学長

本学のシンボルマークを指し、「ENE-Swallow」の
名前の由来について説明する伊原学教授
続いて、各大学の研究発表が行われました。東工大からは、大学院理工学研究科化学工学専攻の伊原学教授が、スマート・グリッドを利用したエネルギー管理システム「ENE-Swallow(エネ・スワロー)」とこの技術を活かした環境エネルギーイノベーション棟(EEI)を紹介しました。UCSBの電気情報工学専攻のマーク・ロッドウェル教授は、同大学における最近の半導体研究とVLSIのためのIII-Vトランジスタおよびミリ波無線システムの研究結果について講演を行いました。
1日目の締めくくりとして東工大蔵前会館で催された情報交換会には、双方の研究者が出席し、翌日の発表および分科会に向けて親交を深めました。
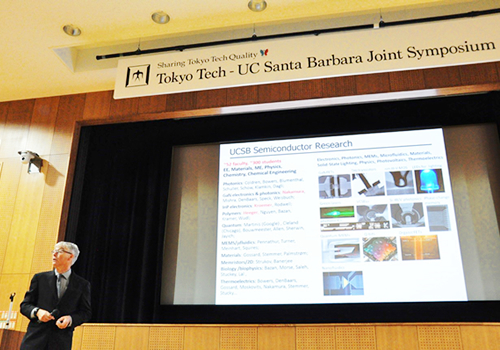
UCSBにおける半導体研究について説明するマーク・ロッドウェル教授
前日に引き続き、2日目の午前は研究発表が行われ、UCSBの教授陣が以下のテーマについて講演を行いました。
「UCSBにおける制御、通信、信号処理について」
ジョワオ・へシュパンヤ教授(電気コンピューター工学専攻)
「電気コンピューター工学、電子工学及び光通信に関する研究の概要:半導体と分子光学アンテナ」
ジョン・シュラー 助教(電気コンピューター工学専攻)
「UCSB におけるシステム設計・検証とモバイル・コンピューター・ビジョンに関する研究」
ティム・チェン教授(電子情報工学専攻)
「UCSBにおける情報科学研究動向」
アムル・エル・アバディ教授(情報科学専攻)
「UCSBにおける化学工学専攻:ナノ材料の合成、解析と応用」
マイケル・ゴードン准教授(化学工学専攻)
「二相材料の3Dプリンティング」
マシュー・R・ベグレー教授(機械工学・材料学専攻)
昼食後、関口秀俊副学長(国際連携担当)が、今後の円滑な研究者交流のために重要な日本学術振興会(JSPS)等の競争的資金を活用した本学の経済的支援の枠組みを紹介しました。前日伊原教授から紹介のあった環境エネルギーイノベーション棟(EEI)を見学した後、分科会が催され、UCSBの教授陣が各専攻の研究室を訪問し、両大学の研究者がそれぞれの研究について議論する場が持たれました。
シンポジウム最終日となる3日目の午後、午前に行われた分科会を踏まえ、参加者全員がディジタル多目的ホールに集まり、分科会の総括と、シンポジウムと並行して行われていた学生ワークショップの総括が行われました。
化学工学専攻を訪れたUCSBのマイケル・ゴードン教授は、同専攻の大河内美奈教授と共に、今後の共同研究の可能性と、両大学の学生や研究者の交流の実現に向けて話し合ったことを報告しました。

マイケル・ゴードン教授(左)と大河内美奈教授(右)
国際学術情報センターの一色剛教授は、UCSBのティム・チェン教授とアムル・エル・アバディ教授を迎えて交わされた議論について報告しました。東工大のスーパーコンピューターTSUBAME2.5についての説明の後、チェン教授とエル・アバディ教授を交え、サイバー・セキュリティー、コンピューター・ビジョン等の分野の教育や研究協力の可能性、さらに両大学の研究者や学生の具体的な交流方法についても話し合われたとの報告がありました。

一色剛教授

ティム・チェン教授

庄司雄哉准教授
電気電子工学専攻では、庄司雄哉准教授がマーク・ロッドウェル教授とジョン・シュラー助教の案内役を務めました。研究室を訪れたロッドウェル教授が、同専攻で行われている研究とUCSBが高い関心を持っている研究とに非常に重要な共通点があることに言及し、将来の共同研究の可能性について示唆したことを報告しました。
畑中健志准教授の所属する機械制御システム専攻では、ジョワオ・へシュパンヤ教授とマシュー・R・ベグレー教授を迎えて分科会が行われました。へシュパンヤ教授は、サバティカル制度(長期の教育研究休暇制度)を利用した研究者の交流は実現性が高いと述べ、交流の継続に期待を寄せました。また、べグレー教授は、研究者1対1の研究交流の可能性に言及し、自ら本学の研究者を積極的に受入れる意向を示しました。

ジョワオ・へシュパンヤ教授(左) 畑中健志准教授(右)

小林覚講師
最後の分科会報告は、UCSBの材料学専攻長であるトレサ・ポロック教授を迎えた材料工学専攻の小林覚講師が行いました。ポロック教授は、2007 年に東工大に滞在した経験から、若手研究者の交流の重要性を強調し、1ヶ月~1年程度、相手側機関に滞在し共同研究を行うことを提案しました。
材料工学の分野では、東工大の竹山教授が、UCSBのポロック教授と約10年間にわたり共同研究を行っています。ポロック教授は、東工大の環境エネルギー協創教育院(ACEEES)の活動にも協力する等、2人は両大学の懸け橋的な役割を果たしてきました。両教授は、近年の高温化材料の分野でも共同研究を実施しており、本シンポジウムではその成果発表も行われました。
ポロック教授は、分野の垣根を越えた共同研究の利点を繰り返し述べるとともに、才能ある研究者や専門の機材や装置を共有することは、両大学にとって非常に有益であると力説しました。

トレサ・ポロック教授

竹山雅夫教授
全体総括ではこの他、シンポジウムと同時進行で開催されていた学生ワークショップの報告も行われ、最後に丸山理事・副学長(教育・国際担当)の挨拶をもって、3日間のシンポジウムは閉会しました。
今回のシンポジウムにより、両大学の研究者が共同研究の可能性を見出し、また学生ワークショップにより、研究と教育の双方において、今後の更なる交流が期待される結果となりました。今回のシンポジウムを起点に、両大学の間でより幅広い分野での交流が進むことが期待されます。