東京工業大学のビジョン
世界最高峰の
理工系総合大学の実現
科学技術の新たな可能性を掘り起こし、
社会との対話の中で新時代を切り拓く
3つの目標
- 世界に飛翔する気概と人間力を備え、科学技術を俯瞰できる優れた人材の輩出
- 科学技術のファシリテーターとして、客観的な知見を社会に提供しながら、社会と共に未来をデザイン
- 人間社会の持続可能な発展を先導する革新的科学技術の創出と体系化
本学のミッションと目標、それに向かうビジョンを達成するため、アクションパッケージを制定しました
アクションパッケージは、本学のミッションと目標、それに向かうビジョンをもとに、第4期中期目標期間(2022~2027年度)に、あるいはそれに続く数年間を含めて、われわれの「ありたい未来像」を実現するための戦略を列挙したものである。
このうちのいくつかは、文部科学省の提示した大綱目標と組み合わせて、中期計画として文部科学大臣の認可を得ている。それ以外の戦略については、それぞれの取り組みの進捗状況や効果・コストとの関係を踏まえつつ、本学教職員・学生、本学のステークホルダー等との対話を通して、適宜・適切に見直しながら実行していく。
記されている戦略には、従来の国立大学法人の枠を超えた意欲的・挑戦的なものが含まれており、国立大学法人群の中で一頭地を抜く存在となるだけでなく、世界の有力大学に伍する大学として、本学の「高み」を世界の人々に認識してもらうために必要な戦略として加えたものである。この結果、本法人は近い将来、他の国立大学法人とは異なった佇まい・位置づけの存在となっているかもしれないが、本法人はそれを恐れない。我々は「ちがう未来を、見つめていく。」人々の集まりであるから。
(アクションパッケージ前文:一部抜粋)
2022年3月版の構想イメージ
本学が目指す方向性に基づき、中長期的な観点から戦略的に取り組む22の水準と99の方策を策定しました。Team 東工大として社会とも共創しながら取り組むことで、豊かな未来社会を引き寄せ、本学と世界の持続的発展を目指します。
1. Student-centered learningの推進
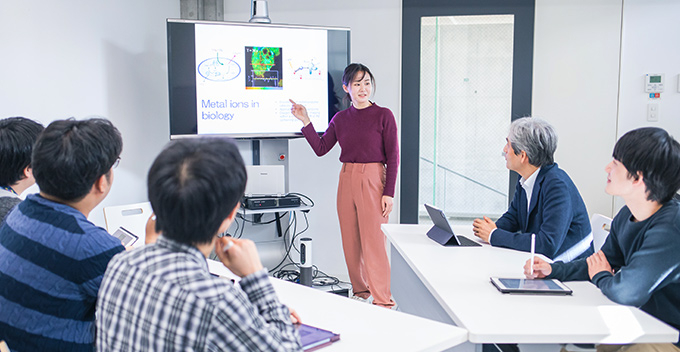
学生の心に世界を変える「志」を育み、俯瞰力やリーダーシップが身につく卓越した教育を行います。
水準
学士課程では、社会課題の解決につながるような多様な視点をもち、専門力を発揮できる基礎的な能力を養成する。(関連する中期計画【3】)
評価指標
学士課程学生が多様な視点をもって専門力を発揮できる基礎を築くように、自身の専門分野以外も系統立てて学ぶ学士課程向けの広域履修制度を新たに設け、第4期中に複数プログラム設置する。
方策
- 1.
- 異なる専門分野を系統的に学修するプログラムを学士課程に開設する
- 2.
- 専門分野の基礎学力を向上させることはもとより、多様な経験を選択できるように、学士特定課題研究と、特定課題プロジェクトの履修のあり方を変更する。
- 3.
- オンライン教育を含んだ多様な教育を実施するためのDX環境を整備する。
- 4.
- 多様性を育んだり、主体性を育てたりする融合科目、全学横断科目に基づく複合領域コース科目、他大学との連携科目、国際経験プログラムなどを提供する共通組織を設置する。
- 5.
- 学士課程におけるアントレプレナーシップ教育を立ち上げる。合わせて、学士課程から大学院課程への接続性を考えて、大学院課程におけるアントレプレナーシップ教育の充実化を図る。
- 6.
- 学生同士の学び合い・教え合いを通じた多様性を育む教育を推進する。
- 7.
- 学士課程から大学院課程までの一連の教育について適切な能力開発になっているか検証し、必要な改善を行う。また、研究教育の効果を可視化する。
2. 大学院課程の教育 開く閉じる
開く閉じる
大学院課程では、修士課程において高度理工系人材の基礎的な素養と社会課題を解決できる実践力、専門職学位課程において特定の職業分野でリーダーとなる技術経営に関する専門力とイノベーション実践力、博士後期課程において社会課題解決でリーダーシップを発揮する力と多様な方面で活躍できる高度な専門力・独創的な研究遂行能力を養成する。(関連する中期計画【4】)
評価指標
- 1.
- 卓越大学院の教育プログラムを引き継ぐために、複合系コースを第4期中に新たに少なくとも2コース設置する。
- 2.
- 学生が身に付けた能力を、学術の観点に加えて様々な価値観からも適切に評価できる外部審査員が参加した学位審査で審査される博士後期課程学生の割合を第4期中に15%とする。
方策
- 1.
- データサイエンス/AI等の高度理工系人材の基礎的な素養として必要な大学院レベルの教育を全学的に実施する。
- 2.
- 多様な学外機関との連携による教育を通して、社会課題の解決までを視野に入れ、専門力を発揮できる人材を育成するために、大学院課程において学生が産業界等、社会で学ぶ機会を増加させる。
- 3.
- 異分野間の連携や異分野融合による教育を推進するとともに、社会の多様な方面で能力を発揮し、イノベーションをもたらすことができる人材を育成するため、大学院課程の複合系コースを新設・拡充する。
- 4.
- 将来にわたって、リベラルアーツ教育の進化を進めるとともに、他者との対話・協働、社会課題への意識など、理工系人材のためのリーダーシップの基礎的素養を身に付ける大学院レベルの教育を行う。
- 5.
- オンライン教育を含んだ多様な教育を実施するためのDX環境を整備する。
- 6.
- 多様性を育んだり、主体性を育てたりする融合科目、全学横断科目に基づく複合領域コース科目、他大学との連携科目、国際経験プログラムなどを提供する共通組織を設置する。
- 7.
- 学士課程におけるアントレプレナーシップ教育を立ち上げる。合わせて、学士課程から大学院課程への接続性を考えて、大学院課程におけるアントレプレナーシップ教育の充実化を図る。
- 8.
- 学生同士の学び合い・教え合いを通じた多様性をはぐくむ教育を推進する。
- 9.
- 学士課程から大学院課程までの一連の教育について適切な能力開発になっているか検証し、必要な改善を行う。また、研究教育の効果を可視化する。
- 10.
- 教育質保証のための、卒業生の追跡調査のための体制を整備する。
- 11.
- 卒業生がさらに社会で活躍できるようにするため、キャリア教育の一層の充実を図る。
3. 博士後期課程学生の育成 開く閉じる
開く閉じる
次代を担う教育者・研究者として博士後期課程学生を遇し、自律した高度な理工系人材として活動できる能力を高める。(関連する中期計画【6】)
評価指標
早期に自律した研究者を目指す人材を育成するB2Dスキームを履修する学生数を、第4期最終年度において全学年で合わせて80人以上とする。
方策
- 1.
- 学士課程の早い段階から博士学位修得に向けて研究指向の学修を行う教育プログラム(B2Dスキーム)を拡充する。
- 2.
- 博士後期課程学生が学内外で教育する機会を作り、教育研究指導能力を高める。
- 3.
- 博士後期課程学生の経済支援の充実を図る。
4. 博士後期課程学生やポストドクターのキャリアパス 開く閉じる
開く閉じる
産業界等との連携・共同によりキャリアパスの多様化や流動性の向上を図り、博士後期課程学生やポストドクターを含めた若手研究者が、産学官の枠を越えた国内外の様々な場において、自らの希望や適性に応じて活躍しその能力を最大限発揮できる環境を構築する。
評価指標
博士後期課程の充足率100%近くを毎年度達成する。
方策
- 1.
- 産業界と連携して博士後期課程学生の育成を進め、能力を産業界に対して見える化し、博士の学位取得者が産業界で適切に雇用される仕組みを構築する。
- 2.
- 博士後期課程学生やポストドクターへの起業家教育や起業支援を組織的に行う仕組みを構築し、起業家も若手研究者の重要なキャリアパスであることを明確にする。
5. グローバル人材の育成 開く閉じる
開く閉じる
国際的な視野を育てる教育を拡充し、グローバルな人材の育成を推進する。(関連する中期計画【5】)
評価指標
グローバルな視点をもつ大学院学生を育成するために国際的な活動への参加を促し、修士課程修了までに「国際経験」を経た学生の割合を第4期中に90%以上とする。
方策
- 1.
- 大学院授業の英語化を確実に推進するとともに、学士課程の高学年教育にも予備的な英語による教育を導入する。
- 2.
- 日本人学生の海外派遣・国際化支援を一層進めるとともに、外国人留学生と協働する教育プログラムを充実させることにより、修士課程修了までに「国際経験」を経ることを定着させる。
- 3.
- ポスト・コロナにおける新たな国際教育、国際連携の実施方法を検討し、開始する。
- 4.
- 海外拠点「Tokyo Tech ANNEX」や国際的な大学間コンソーシアム等を通じて戦略的な国際連携を推進し、参加学生の将来のネットワークづくりにも資する学生交流等を実施する。
- 5.
- ダブルディグリー(DD)プログラム、ジョイントディグリー(JD)プログラム、博士共同指導プログラムを順次拡充する。
主に理工系分野で活躍する社会人が、社会の変化に対応するために必要な高度な知識、リテラシー、研究力を身に付けることができる仕組みを構築、強化する。(関連する中期計画【7】)
評価指標
- 1.
- 第4期中に、社会人を博士後期課程に受け入れる新しい仕組みを構築し、博士後期課程に受入れ、教育を開始する。
- 2.
- 第4期最終年度における社会人向けプログラム開講数を50件にする。
方策
- 1.
- 産業界等で活躍する社会人を博士後期課程学生として受け入れる新しい仕組みを整える。
- 2.
- 卓越教育院における社会人教育及び部局が実施するリカレント教育により社会人教育を強化する。
- 3.
- 本学の子法人である「Tokyo Tech Innovation」が実施する主に社会人向けの教育プログラムに本学教員を講師として派遣する。
- 4.
- 中学生・高校生などの若い世代のみならず、シニア世代を含む社会人に向けて、本学の教育研究のアウトリーチ活動を積極的に展開する。
世界で活躍する真の科学技術人材の育成を目指し、高大連携等による高校教育の高度化を推進する。さらに、その成果を他の高等学校等に展開する。(関連する中期計画【10】)
評価指標
研究開発事業による教育効果の検証等を踏まえ、大学における理工学の理解に資する授業科目を本学開講科目から精選し、当該授業科目を高校生が受講できる仕組みを第4期中に構築する。
方策
- 1.
- 研究開発事業による教育効果の検証や海外理数系高校との連携強化を推進する。
- 2.
- 附属科学技術高等学校の大岡山キャンパスへの移転を機に、更なる高大連携の強化を図る。その一つとして、本学の授業科目を高校生が受講できる仕組み(アドバンストプレイスメント)を理工系大学の特色に合わせた形で構築し、本学の次世代人材教育と連携した高校教育を行うとともに、他の高等学校等に展開する。
- 3.
- 附属高校の教育環境の改善について検討する。
8. 他機関との連携(四大学連合) 開く閉じる
開く閉じる
複雑化する社会問題に対し分野融合的解決をもたらすとともに、高度な協働力・課題解決能力を持った人材を育成するために、四大学連合(東京医科⻭科大学、東京外国語大学、東京工業大学、一橋大学)の協働により研究・教育・社会連携活動等を幅広く企画・展開する。(関連する中期計画【9】)
評価指標
四大学連合の協働で実施される教育・研究・社会貢献連携活動(連携講座、講演会、共同研究・教育事業活動など)の件数や参加者数などの量、活動形態の多様性や内容などの質を第3期の水準より向上させる。
方策
- 1.
- 四大学連合の精神を維持・強化するため、担当理事等の連絡会を定期的に開催する。
- 2.
- 四大学で連携して行う活動を拡充するとともに、その内容を多様化する。
- 3.
- 融合科目等を提供する共通組織の設置に基づき、四大学連合憲章による複合領域コース科目の履修者を増加させる。
9. 入学者選抜の改革 開く閉じる
開く閉じる
多様な人材を効果的に受け入れる入学者選抜制度を構築する。
方策
- 1.
- 多様な学士課程入学者を受け入れる方策について検討を行い、可能な方策から実施する。
- 2.
- 修士課程及び専門職学位課程の入学者選抜のあり方について検討する。
2. 飛躍的な研究推進で社会に貢献
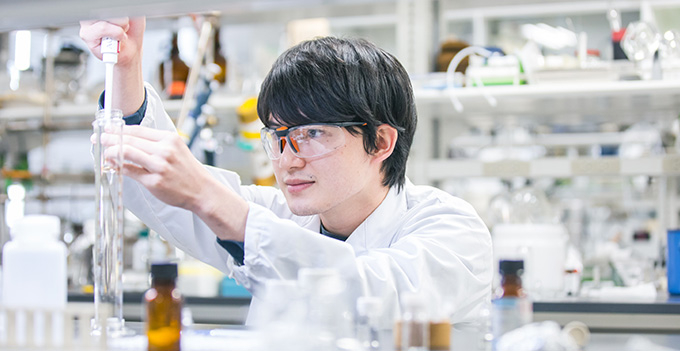
研究者が生き生きと研究できる環境を提供し、その中で、人々が目をみはるような、そして将来の社会基盤となるような革新的な研究成果を数多く生み出していきます。
水準
1. 本学の研究力向上と研究成果の社会への発信 開く閉じる
開く閉じる
科学と技術の最前線において真理の探究と智の開拓に挑戦心と気概を持って挑み続け、その価値を社会に発信し続ける。特に、科学技術の再定義ともなる真の理工連携や文理共創の研究手法を構築し、社会変革をもたらすような総合知を創造する。(関連する中期計画【8】)
評価指標
- 1.
- 総論文数(査読有り)を第3期平均に比べ増加させる。
- 2.
- 科研費の教員当たりの採択件数・獲得金額において最高水準を維持する。
- 3.
- 第4期中のプロジェクト予算100万円以上の社会課題解決型の融合・文理共創研究プロジェクト数の総数を30件以上とする。
- 4.
- 産学連携研究の実績を第4期最終年度までに年36億円程度とする。
- 5.
- 研究成果型の東工大発ベンチャー数の第4期末時点での累積を110社程度とする
方策
- 1.
- 組織・分野ごとの適切な研究戦略と人材育成も含めた人事戦略に基づいて世界最高水準の研究を推進し、研究の意義を大学として社会に示していく。
- 2.
- 研究ユニット制度を活用した新領域・融合領域の研究を推進し、その中から、研究センターへ発展するような厚みと深みを持つ分野への発展も目指す。
- 3.
- 研究者が目指す研究プロジェクトを、研究支援人材とともに実現できるような研究環境を構築する。さらに、研究成果でもある研究データの活用方針を策定し、それを実現するための情報環境を整備する。
- 4.
- ありたい未来社会像からのバックキャストにより研究課題を見出し、その解決から新たな研究の開拓や研究の深化を進める科学技術の手法を構築し、それを実践する。また、文理共創により、社会との対話の中から、社会課題を同定・解決し、それを社会実装し、検証するまでを実現する科学技術の手法を構築し、それを実践する。
- 5.
- 研究成果の社会実装を目指した産学連携研究を推進する。さらに、研究成果をもとにしたベンチャー育成・創出・支援を本格的に行う拠点を形成し、スタートアップエコシステム東京コンソーシアムと連動した大学連携・ベンチャーキャピタル(VC)連携により、アントレプレナー教育からベンチャー創出、そして成⻑支援まで連続的・持続的な支援を行う。
- 6.
- 本学の研究者に関する情報を適時・適切に発信し、本学の研究の見える化を推進する。
- 7.
- 強力な国際研究者ネットワークを様々な分野で構築し、それを本学の研究力強化に活用する。
2. 世界最高水準の拠点形成 開く閉じる
開く閉じる
国際通用性のある教育・研究環境のもと、指定国立大学法人構想で設定した重点分野・戦略分野を中心に、新たな知や価値の創出に貢献できる人材を学内外から集め、科学技術の飛躍的発展を目指す世界最高水準の拠点を構築する。(関連する中期計画【1】)
評価指標
国際先駆研究機構における第一線級研究者の参画数を第4期最終年度までに年間100人程度(国際先駆研究機構が擁する研究拠点にPIもしくは研究協力者として所属する学内研究者を除く)とする。
方策
- 1.
- 全学的な研究組織として、本学の研究戦略に基づき、国際的な連携のもと未開拓・革新性の高い研究に挑戦する世界最高水準の研究拠点を複数擁する「国際先駆研究機構」を設置する。
- 2.
- 国際的な研究者ネットワークとの共創も活かした人事戦略により、学⻑裁量の教員人事ポストを活用しつつ、多様性にも配慮して最適な人材を国内外から招聘・雇用する。
- 3.
- 卓越した人材を適切に処遇し、海外から研究者を招聘しやすくする人事制度やスタートアップ支援制度の構築、それらを可能にする財源を確保する。
- 4.
- 採用選考時・業績評価時の評価基準を改善し、それに基づいた評価を実施する。
- 5.
- 多様な構成員の活躍を促す支援サービスと研究の国際化、オープン化に伴う安全保障輸出管理/研究インテグリティの担保を組織化して実施する。
- 6.
- 学外からの着任後ただちに教育・研究に着手できるよう最先端研究設備、計算基盤、そして学術・研究データ基盤の効率的活用を推進する。
3. 国内外の研究機関との連携 開く閉じる
開く閉じる
個々の大学の枠を越えた研究連携を推進することにより、単独の大学では有し得ない人的・物的資源の共有・融合による機能の強化・拡張を図る。
方策
- 1.
- 国内外の研究者コミュニティを活用して研究連携を推進する。
- 2.
- 研究基盤の共同利用を通しての研究連携を推進する。
- 3.
- Tokyo Tech ANNEXを拠点に、海外大学・企業等との連携教育研究を実施する。
- 4.
- 本学発展のフロンティアの一つとして、社会の人々が求める健康・ウェルビーイング分野の推進を目指し、医学系大学等と協働した「連携研究所」の設立を検討する。
4. 研究設備に基づく研究環境の維持・向上 開く閉じる
開く閉じる
世界最先端の研究にもつながる研究設備を効果的かつ効率的に提供する。(関連する中期計画【12】)
評価指標
- 1.
- 研究基盤戦略に基づき設備共用拠点を複数設置する。
- 2.
- 共用設備の第4期平均利用収入を第3期に対して増加させる。
- 3.
- TCカレッジにおいて、令和4年度から研修等を本格的に開始し、テクニカルコンダクター(TC)の称号を令和5年度から毎年度平均で2名以上に付与する。
方策
- 1.
- オープンファシリティセンターの下で研究基盤戦略に基づき高度な共用設備の導入・提供と技術支援を推進する。
- 2.
- スーパーコンピュータTSUBAME4.0を中心に強力な計算資源を提供する。
- 3.
- 高度技術支援人財育成を行う「TCカレッジ」において、技術職員等に対してスキルアップ及びキャリアアップに役立つ研修等を提供し、高い技術力・研究企画力を持つ「テクニカルコンダクター(TC)」として養成・称号付与する仕組みを構築する。
- 4.
- 研究も含め大学運営の基盤となる全学共通の情報基盤のための設備を適切に維持・管理する。
3. 創造性を育む多様化の推進

自由な場、個人が尊重される場、学びたい者が集まる場としての東工大。東工大に集う人々が、自分の考えを述べ、相手の考えを聞き、創造性を育むことができるような場を提供します。
水準
1. 学生・教職員の多様性向上 開く閉じる
開く閉じる
本学で学ぶ学生が、国籍や文化、個性の違いを超えて切磋琢磨し、グローバル社会の課題に関心を持ち、その解決に貢献できる能力を養えるよう、学生の多様性を高める。教職員・研究者については、年齢・性別・国籍・人種などの外形的な多様性に留まらず、教育研究のスタイルや価値観などの内面的多様性を含めて、教員・研究者の多様性を相互によい影響を与えあえる程度まで高める。さらに、多様な人材がそれぞれの能力を活かして活躍できる環境を構築する。
評価指標
関連:指定国構想の指標
- 外国人留学生比率 2030年~:25%
- 女子学生比率 2030年~:20%
- 女性教員比率2030年~:20%程度
- 外国人教員比率 2030年~:30%
- ※
- 上記数値目標のみに捉われず、互いの価値観や能力などを尊重し、すべての構成員が活躍できるような体制・制度の整備や意識の醸成、環境の構築に努めていく。
方策
- 1.
- 本学における外国人留学生の割合、日本人の留学経験者の割合をさらに高める。
- 2.
- 本学における女子学生比率を飛躍的に高める。
- 3.
- 教員・研究者個々の外形的・内面的双方の多様性を尊重できるよう、環境整備を推進するとともに、採用選考時・業績評価時の評価基準を改善し、それに基づいた評価を実施する。
- 4.
- 文化的背景や言語、性差、ライフステージによって教育研究活動が制約されることがない環境を実現する。
- 5.
- 多様な学生・教職員がのびのびと活躍できる環境を提供するため、いわゆるハラスメントを根絶する体制を強化するとともに、メンタル面を含めたケアを充実させる。
4. 経営基盤の強化と運営・経営の効率化

教育研究活動の効果を定量的に社会に発信し社会の信頼を得るとともに、メリハリある業務運営によって教職員の自由な発想と活動を促進するための時間を確保し、「世界でもっとも高い付加価値を生む大学」であり続けます。
水準
世界水準の教育研究活動や法人経営を行うために必要な経費を確保するため、財源を多元化するとともに、トップダウンによる戦略的・重点的な資源配分を実現する。(関連する中期計画【14】)
チャレンジ水準
経営基盤の強化と好循環による新たな成⻑資源の獲得
世界水準の教育研究活動や法人経営を行うとともに、期待に応えるべく大学が成⻑していくために必要な経費を確保し、財務基盤の強化と新たな成⻑財源の獲得を推進する。法人の財政規模(キャッシュフロー)を持続的に成⻑させていくことにより、ゼロサム経営からの脱却を図る。
評価指標
- 1.
- 産学連携等収入、寄附金収入及び財産貸付料等収入額の合計額を、令和9年度に令和元年度の20%以上増加させる。
- 2.
- 国立大学法人運営費交付金の収入割合を、令和9年度に令和元年度の2.5%以上減少させる。
- 3.
- 「次の知的資産」を生み出す源泉となる教育研究基盤へ戦略的に投入する資金額を第4期最終年度までに年間20億円程度にする。
方策
- 1.
- 財務見通しと経営戦略を立案し、エビデンスを重視した財務マネジメントを確立・活用しつつ、戦略的・重点的な資源投入等を推進する。
- 2.
- 産学連携活動を通じた資源獲得のみならず、東京工業大学基金の増強やキャンパス等の保有資産の有効活用等の多角的な方法により財務基盤を強化する。さらに、田町キャンパス土地活用事業に伴う収入をシードとして、投資額より大きなキャッシュフローを生む取り組みに戦略的に投資を行い、得られた利益の一部を投資に積み増す好循環による成⻑戦略を立案し、実行する。
- 3.
- 本学のもたらす効果や本学の魅力を社会に発信し、それによって得られる社会からの信頼を背景に人的・財政的投資を呼び込むとともに、得られた経営資源を教育研究等の基盤に戦略的に配分する。
2. キャンパス再開発を通じたイノベーションの創出 開く閉じる
開く閉じる
新たなイノベーションを起こしていくため、キャンパスの再開発を通じて、本学が生み出す知、人及び資金が3つのキャンパスを循環し、さらにキャンパス外との有機的、発展的な産学官連携のネットワークに繋がる、本学ならではの「キャンパス・イノベーションエコシステム」を戦略的に構築する。
評価指標
- 1.
- 令和12(2030)年度頃の田町キャンパス供用開始に向け、令和8(2026)年度を目途に大学施設及びインキュベーション施設の基本設計を完了させる。
- 2.
- 令和13(2031)年度のすずかけ台キャンパス再開発事業完了を目指し、令和9(2027)年度を目途に事業化を図る。
- 3.
- 田町のCIC2階~4階において、起業環境整備を実施し、令和4(2022)年度後半を目途に、ベンチャー企業等に貸し出しを開始する。
方策
「キャンパス・イノベーションエコシステム構想2031」に基づき、創立150周年を目処に田町・すずかけ台両キャンパスの再開発とそれに続く大岡山キャンパスの再整備を推進し、新産業創出に繋がる教育・研究・社会連携のための拠点等を形成するとともに、学内外の産学官連携ネットワークを拡大する。
3. 施設の整備・活用による教育・研究環境の維持・向上 開く閉じる
開く閉じる
施設の機能強化や再生、⻑寿命化等に必要な投資を確保し、老朽化の拡大傾向に⻭止めをかけるとともに、戦略的なスペースマネジメントにより、保有施設を有効活用する。(関連する中期計画【13】)
評価指標
- 1.
- 施設の老朽化率を、整備を実施しなかった場合と比較し、令和9年度に5%以上抑制する。
- 2.
- 学内スペースの移管・転用等の数を第4期中年平均800単位以上に増加させる。
方策
- 1.
- キャンパス・イノベーションエコシステム構想のもと、田町新キャンパス構想の策定(令和4年度目途)及びそれに続く大岡山・すずかけ台キャンパスの再開発構想の検討を進め、第4期中にキャンパスマスタープランの改定を行い、施設の機能強化・再生・⻑寿命化等を計画的に推進する。また、「3キャンパスの総合的利用方針」(平成26(2014)年度)に基づき、各キャンパスの役割、求められている機能、施設の老朽化やスペースの状況、立地条件等を踏まえつつ、施設やスペース等のゾーニングや再配置等を計画的に推進し、機能的で質が高いキャンパス環境を確保する。
- 2.
- 学内スペースの配分・負担金システム等を整備・活用し、保有施設の有効活用と戦略的なスペースマネジメントを推進する。
- 3.
- 地球温暖化対策・省エネルギー対策を推進し、カーボンニュートラルに貢献する。
- 4.
- 方策3をさらに推し進め、世界最高峰の理工系総合大学としてのプレゼンスを示すため、本学のキャンパスをカーボンニュートラル化する工程表を作成し、これを実施する。
4. 自治体等との連携 開く閉じる
開く閉じる
自治体等との組織的な連携を推進することにより、人的・物的資源の共有・融合による機能の強化・拡張や自らが有する教育研究インフラの高度化を図る。
方策
連携協定に基づき自治体の発展に寄与するとともに、各種規制の緩和を求め、キャンパス・イノベーションエコシステムを持続的に発展させるなど、本学が有する教育研究インフラの高度化を図る。
5. 内部統制とガバナンス 開く閉じる
開く閉じる
世界最高峰の理工系総合大学の実現に向けて、学⻑のリーダーシップのもと、6年の中期目標期間はもとより、指定国立大学法人として、それを越えた継続的発展を目指す法人経営を実現する。(関連する中期計画【11】)
評価指標
⻑期的な展望に基づく法人経営を実現する先進的なガバナンス体制を維持する。
方策
- 1.
- 第3期中期目標期間までに強化したガバナンス体制に基づき、内部統制機能を働かせながら、社会からの信頼と支援を受けて財源の多元化を図るとともに、教育研究の高度化や業務運営の効率化等のための各施策を推進する。
- 2.
- ⻑期的な展望に基づく法人経営を実現する先進的なガバナンス体制を維持していくために、専門人材の知見を活用するとともに、法人経営を専門的に担える人材の継続的な育成を図る。
- 3.
- 教育研究・組織運営を担う人材を拡充するため、承継教職員の外部資金直接経費等での雇用を推進するとともに、エフォートの明確化を前提に複数組織での業務担当制度(学内クロスアポイントメント、兼務発令等)を活用して、教職員の能力を最大限発揮させる。
- 4.
- 本学の活動、特に対外活動を継続的に発展させるため、本学の子法人を効果的に活用する。
- 5.
- 最有力のステークホルダーである学生が大学の運営に携わる機会を作り、学生が主体的に大学に係る方法を学生と一緒に構築する。
- 6.
- 世界最高峰の理工系総合大学としてのレピュテーションを向上させるため、本学の修了者や、本学の実施する教育研究・社会貢献等に関与した者とのネットワークを強化し、本学のサポーターとなってもらう施策を実施する。
6. 自己点検評価と情報提供 開く閉じる
開く閉じる
自己点検・評価やエビデンスに基づく法人経営を推進するとともに、学生や産業界を中心に情報発信を強化し、社会から更なる信頼を得る。(関連する中期計画【15】)
評価指標
自己点検・評価の結果や戦略的経営オフィスによるコスト・効果分析の結果を踏まえて統合報告書を定期的に発行するとともに、アドバンスメントオフィスを中核として学生や産業界等との対話の機会を年1回程度設ける。
方策
- 1.
- 内部質保証体制に基づき、全学・各部局等において継続的に自己点検・評価を行い、その結果等を踏まえて業務運営の改善や教育研究の質の向上を図る。
- 2.
- プロボストを⻑とする「戦略的経営オフィス」の活動等を通して、法人経営や各部局等の教育研究にかかるコストと効果の多角的な分析を行う。
- 3.
- 学⻑主導で大学のブランディング・レピュテーション向上のための広報戦略を立案し学⻑自身のトップセールスを企画する「アドバンスメントオフィス」の活動等を通して、本学のもたらす効果や本学の魅力を社会に発信する。
- 4.
- 本学の実績と社会貢献について財務情報・非財務情報を合わせて発信する統合報告書の発行と学生や産業界との対話を継続的に実施する。
- 5.
- ステークホルダーの意見等を分析し、それに基づいた効果的な法人経営・大学運営を実現する。
7. 教育研究の高度化のための好循環システム 開く閉じる
開く閉じる
産業界を中心に本学への投資を獲得し、指定国立大学法人構想及び経営改革ビジョンに掲げた「卓越した教育・研究による学知の創造と戦略的社会連携による学知の社会実装の『好循環』」の駆動力を格段に向上させる。その上で、競争的資金、産学連携資金、寄附金等の獲得に努めるとともに、本学の有する資産を有効に活用して財政的資源を確保する。
さらに、こうして得た資源を何に投資をして次の信頼に繋げるかの方向性を明確にする。(関連する中期計画【2】)
評価指標
「次の知的資産」を生み出す源泉となる教育研究基盤へ戦略的に投入する資金額を第4期最終年度までに年間20億円程度にする。
方策
- 1.
- 本学のもたらす効果や本学の魅力を社会に発信し、それによって得られる社会からの信頼を背景に人的・財政的投資を呼び込むとともに、得られた経営資源を教育研究等の基盤に戦略的に配分する。特に社会との連携による直接経費が得にくい分野の教育研究や国際連携などの知と人材創出のインフラストラクチャーに相当する領域への投資を行う。
- 2.
- 人材輩出、知の創出、社会課題解決等、いずれの視点でも「最も高い付加価値を生む」組織として本学を認知してもらい、それに基づいた社会からの投資を呼び込む。
- 3.
- 田町再開発に留まらず、本学の有する資産を有効に活用して財政的資源を確保する方策を検討する。
- 4.
- 優れた人材を輩出する大学、基礎的・基盤的な知を創出する大学という「公器」としての役割を高めることは当然として、社会との対話・ステークホルダーからの意見を基に「最も高い付加価値を生む」領域を特定し、それに繋がる人材・環境等への⻑期的投資戦略を立案する。
- 5.
- 好循環の源泉は教職員・研究者の日々の活躍にあることを念頭に置き、教職員が常に新しいことにチャレンジできる精神的余裕と時間を確保する。
8. ICTを用いた業務運営の効率化 開く閉じる
開く閉じる
ICTを高度に活用し、社会環境に応じ効率性・透明性・安全性・業務継続性を適切に保った体制のもとで業務運営を実施する。(関連する中期計画【16】)
評価指標
令和4年度中に、包括的なDX推進基本戦略とアクションプラン等を策定し、令和5年度から計画的に実施する。
方策
- 1.
- ICTを高度かつセキュアに活用するための以下の方策を包括したDX推進基本戦略とさらに詳細なアクションプランを策定し、全学的な推進体制のもとで計画的にDXを推進していく。
- 2.
- 大学運営の効率化や安全性向上等を支援する基盤コミュニケーションシステムを整備し、適切な活用規範に沿って業務で幅広く活用する。
- 3.
- 業務システムの整備・運用の統一的な指針を策定し、システム間のデータ連携の効率性・安全性を確保する仕組みを導入する。
- 4.
- 強靭な情報セキュリティ環境の維持・向上のため、システム上の対策だけでなく、大学運営の現場で適切な情報セキュリティ管理ができる人材の育成・配置を進める。
- 5.
- デジタル技術の活用を想定しての業務プロセスの見直しや業務改革を計画的に進める。
- 6.
- 大学運営の基盤となる全学共通の情報基盤システムを適切に選択し、運用する。
- 7.
- DX推進も含め、情報基盤に対する統合的かつきめの細かい支援体制を構築する。
-
指定国立大学法人構想
-
各部局等の将来構想
-
経営改革構想など


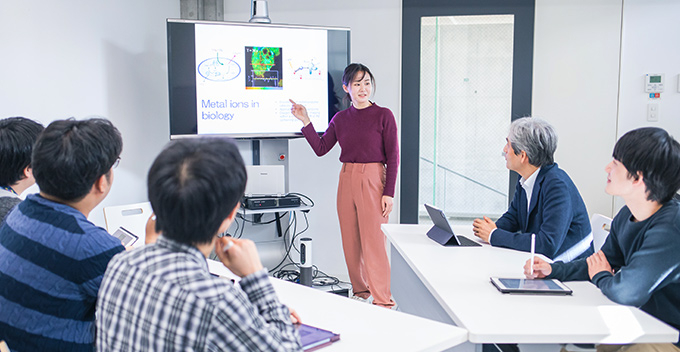
 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる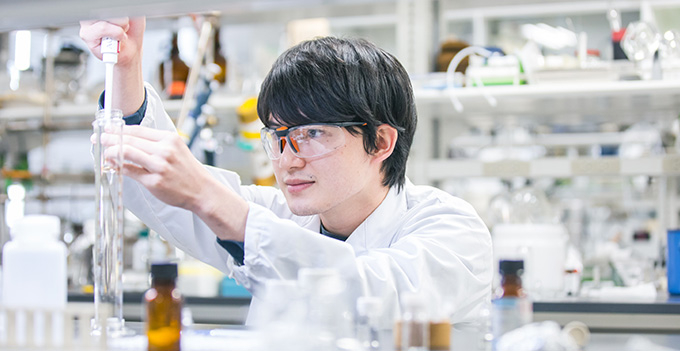
 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる
 開く閉じる
開く閉じる
 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる 開く閉じる
開く閉じる