東工大について
東工大について
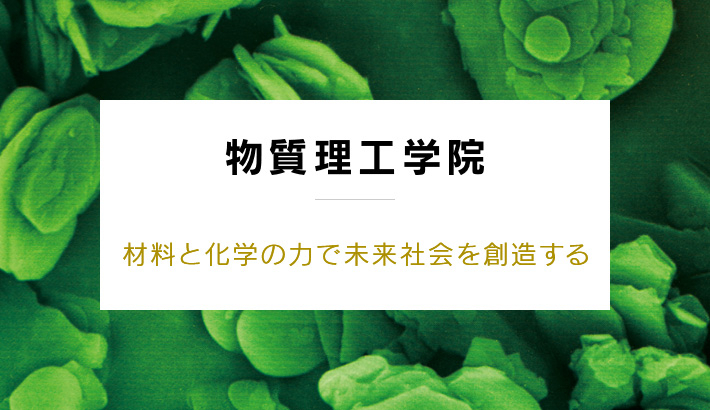
東工大は、材料や応用化学の分野で世界トップレベルの研究陣容を誇り、これまでに素晴らしい実績を挙げてきました。物質理工学院では、新しい物質や社会に役立つ材料を創りだすことで、環境・資源・エネルギー・健康医療等の課題解決を図ると共に私たちの生活の質を向上させ、未来社会の構築に貢献します。とくに、持続可能な開発目標SDGsに重要なカーボンニュートラル社会の実現を目指します。本学院は、固体材料に基盤をおく材料系と分子・化学に基盤をおく応用化学系で構成され、扱う対象も原子・電子からデバイス・プラントまで広いスケールにわたります。また情報科学と融合させた革新的な物質開発も進めています。そしてこのような最先端の研究を通して、将来の物質・材料開発を主導できるグローバルな研究者・技術者を育成します。
![]()
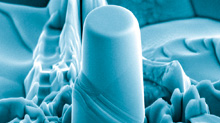
その可能性を知ることで、物質の研究の面白さが味わえます。
大学の研究は基礎の部分でブレークスルーを狙うもの。そのため、まったく予想もできなかった材料や物質が見つかることがあります。面白い物質を見つけると、その研究がいかに面白く、しかも社会に与えるインパクトが大きいか、実感できるはずです。

好みに合う専門を見つけやすく、将来の選択肢も幅広い。
物質・材料の研究は、理学に近いテーマから工学らしいテーマまで大きな多様性があります。ですから社会では、自動車、機械、電子機器、衣服、医療からエネルギーまで、ありとあらゆる分野で物質・材料のプロフェッショナルが必要とされています。

基幹産業とつながる分野なので、就職の心配はありません。
将来の選択肢が広いことに加えて、この分野は日本の産業を支えている基幹産業とつながっており、そこでは多くの先輩方が大活躍しています。「しっかりと勉強すれば、就職の心配はする必要はない」と言っていいでしょう。それも魅力の一つです。
物質理工学院 |
学士課程(1年目) |
学士課程(2~4年目) |
大学院課程 |
|---|---|---|---|
物質理工学院 |
|||
※ 複数の系に関連しているコース

大学教育においてもグローバル化が急速に進む中、工学院、物質理工学院、環境・社会理工学院では、国際的な研究ネットワークやプロジェクトへの参加促進、学生・教員・研究者間の交流の活性化などのサポートに注力しています。海外の世界トップレベル大学の部局と上記3学院との間で50件以上の部局間協定を締結しており、そのうちのいくつかの協定校と奨学金を伴う派遣交換留学プログラムを実施しているほか、EUのErasmus+の支援により国際交流協定を締結しているパートナー大学への留学支援も行っています。

アジア、オセアニア地域のトップレベルの工学系12大学間の多角的交流を促進する目的で設立された大学連盟AOTULE(The Asia-Oceania Top University League on Engineering)の活動には、国際学生会議、本学キャンパスで実施されるワークショップ、アジア・オセアニア地域で開催されるワークショップ等のほか、研究活動のための海外派遣等があります。

工系部局間交流協定の結ばれている大学(ウィスコンシン大学マディソン校、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、ウォーリック大学、サウサンプトン大学、パリ第6大学、アーヘン工科大学、マドリッド工科大学等)へ2~3か月程度の留学支援を行っています。
ワクワクが研究を加速
光反応による新規物質の創成を目指して
物質理工学院 応用化学系
下世明日葉さん(修士課程1年、2023年度)
学士課程2年次から本格的な研究スタート
世界最高レベルの環境で二次電池の先端研究
物質理工学院 応用化学系
山中一輝さん(学士課程3年、2023年度)
将来は教師?研究者?
学びを通して自分を磨けば 多様な選択ができる
物質理工学院 材料系
磯岡美里さん(修士課程1年、2023年度)
学院を超えた人間交流
サイクルサッカーがキャンパスライフを豊かに
物質理工学院 材料系
浅野光輝さん(学士課程4年、2023年度)
中学校教諭一種免許状(理科)
高等学校教諭一種免許状(理科・工業)
中学校教諭専修免許状(理科)
高等学校教諭専修免許状(理科・工業)