東工大について
東工大について


東京工業大学未来社会DESIGN機構(DLab)は「人々が望む未来社会とは何か」を社会の一員として考えデザインすることを目的として、2018年9月に設置されました。これからの科学・技術の発展などから予測可能な未来とはちがう「ありたい未来」とはどんな未来なのか。そしてその未来を実現するには、何をすべきなのか。そんなワクワクする課題について、学内の教職員、学生だけでなく、学外の方も含めた多様なメンバーで楽しく、真剣に語り合っています。
DLabではワークショップ等の参加型のイベントを積極的に開催しています。
これまでのイベントを通して参加者の皆さんから得られた「ありたい未来」は100以上にもなり、DLabはこれらの「ありたい未来」をもとに24の「未来シナリオ」を作成しました。その中から4つのシナリオを選び、DLabが初めての未来社会像として描き出したのが「TRANSCHALLENGE社会」です。
DLab初の未来社会像 TRANSCHALLENGE社会
場所や身体、距離等に起因する物理的な制約は、もはや人々にとっての「困難」を意味しない。誰であろうが、どこにいようが、あるいは貧すれど、等しく「挑戦」する機会に恵まれる。VRやARによる(疑似)体験、着脱可能な五感を用いた共感体験は、人々の生活の一部となっている。いくつになっても富士山に登れるし、近しい人やペット、花木の気持ちさえ分かる。そうして拡張された体験や共感は、将来の不確実性を前に尻込みする人の最初の一歩を後押しする。現状に満足し、そこに留まりたいと考える人にすら、思いがけない可能性との遭遇をもたらす。それでも後ずさりせざるを得ない心の傷がある人は、それをアンインストールすることだって可能である。
科学・技術は、かねて人を人足らしめ、未来の原動力となってきた「挑戦」を支援する。そして社会、わけても大学はその結果として生じるかもしれない失敗(「困難」)を高く評価する。覆水はかつての盆に返らずとも、別の盆がそれを受けとめる。このとき、人々にとっての“Challenge<困難/挑戦>”は、それまでよりもずっと前向きで、社会的にも価値あるものになっている。

ありたい未来から未来社会像の作成まで

TRANSCHALLENGE社会を構成する4枚の未来シナリオ

ありたい未来から未来社会像の作成まで

TRANSCHALLENGE社会を構成する4枚の未来シナリオ
DLabが描く「未来社会像」はこれで完成ではありません。今後も社会の皆さんと対話を続けることで「TRANSCHALLENGE社会」をブラッシュアップするとともに、別の「未来シナリオ」をもとにして第二・第三の「未来社会像」を描いていきます。
また、百年記念館1階には24の「未来シナリオ」を実現の可能性があると思われる年代順に並べた「東工大未来年表」を展示していますので、ぜひお越しください。皆さんが未来について考え、想像し、語り合うきっかけとなる場として活用されることを期待します。

東工大未来年表
DLabの活動はまだ始まったばかりであり、今後も「ありたい未来」の実現に向けて活動を推進・展開していきます。3月7日(土)には、大岡山キャンパスにて共創ワークショップ「覆水、別の盆−思い通りにいかないことの先に「ちがう未来」が見えてくる」を開催しますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。
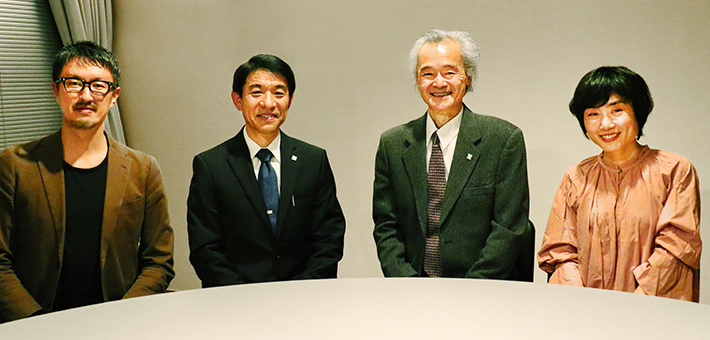
佐藤:2018年3月、東工大は「科学技術の新たな可能性を掘り起こし、社会との対話の中で新時代を切り拓く」という構想のもとに、文部科学大臣から指定国立大学法人の指定を受けました。DLabは、この構想を実現するための推進役を担う組織の一つです。
大竹:東工大では、大隅良典先生がオートファジーの研究でノーベル生理学・医学賞を受賞するなど、個々の教員により世界レベルの研究が進められていると言っていいと思います。一方、指定国立大学法人の申請をする際に、外部委員の方から「研究を進めるにも、社会とのつながりを考えるという視点が必要ではないか」という指摘をいただいて、新たな研究推進の方策が求められているのではないかと考えさせられました。
佐藤:大学全体で「社会が望むものは何か」を共通認識として持った上で、社会課題の解決につながるような知見を積み重ねていく。そうすることが社会に貢献するステップになるのではと考えて、DLabを創設することを決めました。

川名:近年の社会と科学技術の一般的な関係というのは、「まず技術はラボで生まれ、次にその技術を社会の側が“発見”し、そこから次なる社会が形成されていく」というものだったと思います。でもDLabでは「第一に社会の課題があって、その解決に必要な技術を考える」という“課題解決主導”のスタイルで未来を考えています。私の専門は国際政治学ですが、これは難しいものの大変意味があることだと考え、ぜひ協力したいと思いました。
伊藤:どんなに専門的な研究をしていても、手元だけ見ていては痩せていくと思います。革新的なアイディアを得るためには、今やっている研究がどこにつながっているのかという大きなビジョンが必要です。個人的な話で恐縮ですが、私が大学で最初に専攻していた生物学を離れ、文系に転じた理由の一つも、理系の学問があまりに細分化されていたことにありました。東工大が社会でより大きな役割を果たすためにも、理工系の先生方と一緒に未来の社会のあり方を考えていきたいと思ったんです。
大竹:DLabでは多くの方と議論しながら、まず「こんな未来がいい」という理想の未来像を考えていきます。そしてその未来像を起点に、どんな技術が必要になるかを検討していきます。この「バックキャスティング」という手法はかなり一般的になりましたが、200年先まで視野に入れた長いスパンで実施している例は珍しいのではないかと思います。

佐藤:当初想定していたのは、30年、50年くらい先まででしたが、理工系の人間はどうも頑ななところがあって、飛躍した発想で未来を考えるには遠い先を見ざるを得なかった面がありました。今ある物理法則に基づかない形で「仮説に基づく仮説を立てる」ようなことを近未来でやろうとすると非常に居心地が悪いんですよね。
大竹:どうしても今の科学技術をもとに、断定的にYes、Noを言ってしまいがちになりますね。
川名:社会科学の分野から見ても、社会的な問題や人間の本質にまで関わるようなことを変えるには、長い時間が必要です。ですから100年単位のスパンというのは、やはり必要だったかなと思いますね。
伊藤:未来について自由に考えるといっても、つい現在の延長線上で物事を考えがちですよね。バックキャストで重要なのは、「未来を描くこと」それ自体ではなくて、「何十年、何百年後の視点に立ってみる」ということだと思うんです。自分の孫の孫とかの視点に立った自分と、今の自分を対話させる作業が大切なんですよね。
川名:学術機関として未来像を考えようとする場合、「未来とはこういうものだ」と大上段に提示するという方向性も、もしかするとあり得たのかもしれません。ただDLabでは、一般の方も含めてさまざまな方との対話を通じて「ありたい未来」というものを考えて、長い期間をかけてその最大公約数を検討、濾(ろ)過したものを形にしている。そこが特徴的ですよね。
伊藤:「人文系の女性研究者として、マイノリティーだと感じることはない?」と聞かれたりもするのですが、DLabでは文系・理系、男性・女性さまざまな方がいて、どちらが少数派だという感じを受けることもない。システマティックに考えながら、対話のなかで生まれたものを育てて行くというスタンスがあって、いろいろな考え方が活かされていると思います。

大竹:右脳と左脳の両面から、複眼的な議論ができているのがいいところかなと感じますね。その議論の結果を24の「未来シナリオ」とし、そして川名先生がその中の4つのシナリオからひとつの「未来社会像」として表現してくれた。「覆水はかつての盆に返らずとも、別の盆がそれを受け止める」という言葉を見たときには、こんな表現の仕方があったかと感じ入りました。
川名:私は皆さんで議論されたことを、ただ、言葉に直しただけなんです。「失敗は成功のもと」ではありませんが、ただ「返す」のではなく別の盆で受けようと。
佐藤:科学技術の力によって、身体や距離などの物理的な制約を受けることなく、誰でも等しく「挑戦」する機会に恵まれ、失敗しても評価され、再起できる—。そんな「TRANSCHALLENGE」が可能になる社会というのは、DLabの考える未来社会の重要な特質です。川名先生がそうした議論のエッセンスを、印象的なフレーズで表現してくれました。
川名:これまでのおよそ1年強の活動で大きな方向性が見えてきて、次はいよいよこれを具体化していくフェーズですよね。伊藤先生は昨年半年ほど、マサチューセッツ工科大学(MIT)にいらして、研究をされてきたわけですが、研究への取り組み方で違いなどは感じましたか。
伊藤:MITというと理工系でも「華やか」というイメージが強いと思うのですが、実際は現実に社会で起こっている課題を、リアリスティックに分析し、本気で解決しようとしているという印象が強かったです。その意味では、あまりバックキャストという感じではないのかもしれません。例えばアフリカの健康問題というと、つい衛生状態の改善やワクチンの摂取ということをイメージしがちですが、実際には成人病の対策が大きな課題になっている。想定でものを言うことを許さない雰囲気がありましたね。
大竹:MITのテクノロジーレビューは、伊藤先生がおっしゃったことがまさに具現化されていますよね。
伊藤:そうですね。ただMITは、というかエンジニアの性なのかもしれませんが、課題に対して何にでも最先端技術で対応しようとする。ほうきで十分なところに、最新鋭の掃除機とドローンが合体したものを持ってくるような面があるんです。社会課題を解決するのは必ずしも最先端の技術ではない。実態に即した解決法を探すことも大切だと感じましたね。
佐藤:MITと東工大の組織としての違いもあると思います。MITメディアラボは、研究資金を私企業からの寄附でまかなう運営モデルなので、どうしても先端技術が求められるようになります。DLabではそれほど最先端にこだわらず、「社会の課題にどう応えるか」をきちんと考えていける。東工大も放っておくとどうしてもテクノロジー主導で進みがちになりますから、DLabでは社会的な視点を重視しながら、課題解決主導を意識して進めるべきだと考えています。
川名:ただ、現実として理工系の研究大学から「ほうき」を出せるのかという点が、試されるところではありますよね。
大竹:先進的な研究でなければ科学研究費が出にくいという事情もありますし、日本の大学の99%は掃除機とドローンが合体したような先進技術を研究しています。それはもっともですが、技術のなかには歯車やネジなど、今はほとんど研究されていないけれど忘れてはいけない大切なものもある。東工大にはそうした技術を守っていく役割もあるのかなと感じました。
伊藤:私の専門の芸術分野では「再発見」というものが非常に重要で、絵画も音楽も彫刻も再発見を繰り返しながら創造活動を行ってきました。それを考えると、物事を再発明するというのは、純粋な発明と同じくらいのインパクトを社会に与えるものだと思います。

佐藤:技術が急速に進化する一方で、先ほどは「人間はそう変わらない」というお話もありましたが、川名先生は人間と技術の関係についてどうお考えですか。
川名:仮にある地域の課題を解決するために、先進的な技術を導入しようとします。しかし、それが既得権のバランスを崩すようなことになる場合、コミュニティ全体の福利が増大することは分かっていても、おそらくその技術は受け入れられないでしょう。これが人々の絶えざる緊張関係を含んだ社会の特徴だと思います。この部分についての分析が欠けてしまうと、良い技術をせっかく開発しても社会に着地できないという事態が起きてしまうでしょう。
伊藤:人間には技術によって変わる部分、変えたくない部分の両面がありますよね。例えば最近の子どもは、画像を双方向的なものと捉えていて、テレビの画面でさえタブレットのようにスワイプしようとします。技術で人の行動は変わるわけです。一方、手話を使って日本語では伝えきれないことを表現してきた方のなかには、「人工内耳などの技術を使うことで自分たちの文化を失いたくない」という方も少なくない。技術とどう向き合っていくかは難しい問題です。
大竹:技術的には人間の遺伝子も改変できるようになった今、人間が自分の意思で変わるのか、科学技術に変えられてしまうかの境界の判断は際どいですね。ただ、DLabでは「科学技術で人の遺伝子を変えることを前提とした未来社会の提案はやめましょう」と最初の時点で決めました。読んで違和感がない、受け入れやすい未来社会像になっているのは、その点が大きいと思っています。
佐藤:技術がソリューションとして生かされるかは社会側の問題で、議論にかけてみるまで分かりません。その方法を持っておかないと、研究者が本当の意味で社会に貢献するのは難しくなる。DLabはその一つのチャネルになると考えています。
川名:技術へ向き合う時、無条件でそれを善と見てしまうのは危ういわけで、大学での講義などでも教員として、あえて逆の見方を提示することは大切だと思っています。ただ、今の社会は「変化」というものに対する見方があまりに悲観的で、「どうすれば変われるか」という発想がほとんどないのが問題。人文社会の分野で行き詰まっていた問題に、科学技術など異分野の知見が加わることによって、考えもしなかったソリューションが生まれる可能性もある。ナイーブな見方かもしれませんが、そうした掛け合わせは必要だと思います。

伊藤:今の学生くらいの年代だと「変化すること=悪化」で、現状維持が一番だという考え方の人が多いですよね。でも、変化をよりよい方向へ向けた挑戦と捉えられるようになってほしい。例えば東工大のキャンパスの中に、社会実装される前の技術を体験できるショーケースのような場所をつくって、訪問された方が先端技術を実験的に体験できるようにすると、「変化=悪化」ではないことを分かってもらえるのかなと考えています。
大竹:不透明な時代のもとで、とりわけ科学技術については「AIがここまで進化して人間は大丈夫か」と不安が先行して見られているような状況があります。そんななか、私たちが科学技術を活かした明るい未来像を見せることで、科学技術に対する皆さんの見方も変わっていくと思うんですよね。科学技術は「ありたい未来」を実現するためのもので、マイナスのものではないんですというのは、僕自身がDLabでの活動を通じて一番伝えたいことでもあります。
佐藤:DLabでは未来を俯瞰するため、「未来シナリオ」を実現可能と思われる年代順に並べた「東京工業大学未来年表」を発表しました。今、未来を描く年表を作る組織は少なくありませんが、日々科学技術の研究に取り組んでいる東工大が出す年表として、最新の研究成果や進捗状況を反映しながら、常にバージョンアップされ続ける年表にしていきたいですね。
川名:実際に年表を見てもらえたら、「こんな技術あったらいいよね」「こんなこと起こっちゃいけない」など、刺激されるところがあると思います。そこで未来について考え、議論をしてくれたら嬉しい。東工大が責任をもって、本気でやっていることが伝われば、足を止めて考えてくれる人は多いのではないかと期待しています。
大竹:あとはここで提示された未来社会をどう実現するかですね。今、一つ動き始めているのは、若手研究者への働きかけです。東工大には若手研究者の人材育成を行う基礎研究機構という組織があるのですが、そこの広域基礎研究塾のメンバーに自分の研究と未来社会のつながりを考えるワークショップに参加してもらっています。「参加して良かった」という感想も多く、当日の議論をもとにした研究計画を練って研究費を申請する人も出てきました。こうした動きを支援していければと考えています。
川名:全学的な動きをどう創るかは重要ですよね。伊藤先生は本年2月に開設される東工大の「未来の人類研究センター」のセンター長としても活動を開始される予定ですよね。
伊藤:「未来の人類研究センター」では、「未来」というより「人類」の方に力点を置いた研究が中心になると思います。一つ中心的なテーマに掲げているのが「利他」で、これを突き詰めて考えていくと、現代社会で当たり前だと思われている能力主義や功利主義といった仕組みを相対化することにもつながる。そんな形で「人間とは何か」といった根本的な問いについて考えていく予定です。
大竹:AIを使っても解が出ない、AIが人間に絶対に勝てない部分ですね。
佐藤:これは私見になりますが、センターではそうした人間のあり方にフォーカスしながら、今までの社会規範を外したところでの人間の本質は何なのかを突き詰めていってほしい。そしてDLabとの両輪で、人間の未来について考えていけたらいいですね。
伊藤:新たな視点を入れることで、多面的に議論を進めていけそうですね。
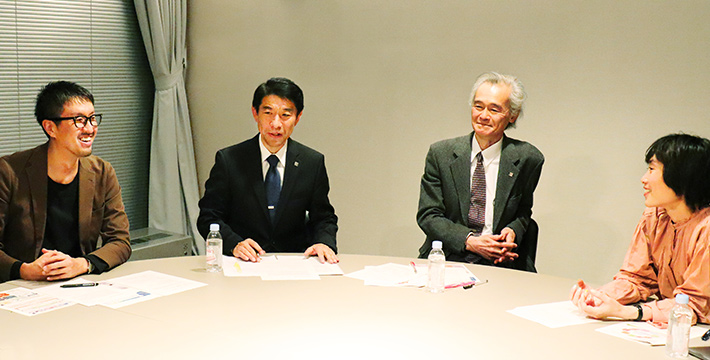
佐藤:今後の対外的な展開については、皆さんどうお考えですか。
伊藤:DLabの未来社会像を社会全体に訴求力のあるものにすることを考えると、「未来社会を実現するのに必要な技術は何か」という視点に加えて、その技術をどう管理して、社会に届けるかという部分の設計もしていく必要があるでしょうね。もう一つ、MITのキャンパス周囲には沢山のベンチャー企業が集まってコミュニティを形成していますが、そうした地域的なつながりも重要になるかもしれません。
川名:学外の社会科学系の研究者からは「東工大って東京にあって物理的な距離は近いはずだけれど、心理的には遠いね」と言われてしまっています。東工大を、行政の方、メディアの方など科学技術にも関わりを持つ、いわゆる「文系」の方にもっと来てもらいやすい場所にしていけたら、と思っています。
大竹:海外では地域の産業がピンチになった時、大学は新しい事業を創出するといった役割を果たしている。DLabはそうした窓口にもなり得ると思います。
佐藤:さまざまな方に来ていただきやすい雰囲気を醸成しながら、自由に議論ができる場になっていけばいいですね。日本の技術者には「技術さえ優れていれば世界は認めてくれて、国際標準にもなる」と信じているようなところがあると思いますが、そうとは限らない。今後、科学技術によって社会に貢献していくには、社会の声を聞き、社会と議論をし、時には外部の技術も取り入れ、創り出した技術に共感を持って使ってもらうという、社会に根づいた課題解決型のアプローチが必要です。DLabの未来社会像は、私たちが今ある技術をもとに「こうあるべき」だと考えたものではなく、社会のさまざまな方にうかがった「ありたい未来」の姿を集約して作り上げたものです。引き続き学内外に幅広く意見を求めながらさらに活動を進め、その成果を国内のみならずグローバルに発信していきたいと思います。DLabの活動にこれからも多くの方に参加していただきたいですね。
スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。
2020年1月掲載