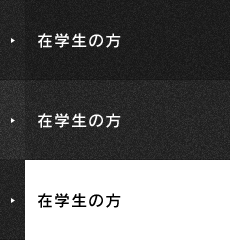キャンパス・アジア 清華大学セメスタープログラム(Tsinghua Spring Semester Program)2018年2月20日~2018年7月15日
留学時の学年: |
修士課程1年 |
|---|---|
所属: |
環境・社会理工学院 融合理工学系 地球環境共創コース |
留学先国: |
中華人民共和国 |
留学先大学: |
清華大学 |
留学期間: |
2018年2月20日~2018年7月15日 |
プログラム名: |
留学先大学概要
清華大学は、北京大学に次いで中国国内第二位と評価され、世界大学ランキングにおいても上位に位置する。北京大学に比して、科学、工学分野での活躍が目立つが、人文学や社会科学といったいわゆる文系の研究院、あるいは図書館も有し、幅広い分野で研究を行うことができる大学である。
留学前準備
半年近く留学する以上、正規の年限での修了と就職は難しいと考え、卒業時期を先延ばしすることにした。この半年の延長分を、余裕を持って使えるように、留学先では修士論文の一部を完成させることを目指した。また、現状あまり一般的ではない九月卒業予定となるため、帰国後できるだけ早い段階で就職活動を始める予定を立てた。
留学先の情報は事前に入手し難い部分もあったため、実際に現地に赴いた後に、どの授業を履修するか、研究室はどこに所属するか、を決めようと考えた。ビザ取得や寮の手続き等は、本学留学生交流課と清華大学の担当部署の指示に従い、滞りなく進めることができた。
留学中の勉学・研究
授業は専門科目を一つ、中国語の科目を一つ、合計6単位を履修した。
専門科目は中国語での講義であり、かつ学生の発表が主体のゼミのような授業あったが、7、8人ほどしか履修者がおらず、英語での発表を許可していただいたため、問題なく参加できた。しかし、一人当たりおよそ一時間、毎回二人の学生が発表するというスタイルはこれまでに受けたことがなく、当初はかなり戸惑った。自分自身が発表するときも、ほかの学生の発表を聞くときもかなりの集中力が要求された。現地の学生に聞いたところ、このような発表は中国の大学院では一般的であるとの話を聞いた。中国語のため細部まで理解が及ばなかったが、しかし、このやり方はどの程度“専門の授業として”妥当であるのか、という疑問はいまでも残る。すなわち、量と質のバランスが釣り合っていないように感じた。
中国語の授業では、これまで意識していなかった発音などを教えていただき、矯正することができた。ある程度の下地は必要だが、現地で、現地の言葉で授業を受けることは、語学力の飛躍的な伸びにつながると感じた。
研究は、留学先では研究室に所属しなかったため、毎日図書館に通い自主的に行った。各種論文、文献にもスムーズにアクセスできたため、ストレスは全くなかった。そのまま継続して研究を行いたいと思ったほどである。
留学中に行った勉学・研究以外の活動
留学中、北京市内だけではなく、天津や上海にも足を運んだ。それぞれの都市の違いを感じた。特に上海と北京は、同程度の規模であり、知らない人から見れば同じような都市であると思われるかもしれないが、外国人の多さや街づくりに対する姿勢の違い、あるいはそもそもの文化の違いを感じた。一つ一つを語ればキリがないためここでは差し控えるが、中国国内南北の温度差を感じた次第である。
留学を終えて、自分自身の成長を実感したエピソード
留学中は自身の研究で大いに迷った。いま立てている仮説が間違っているのではないか、そもそも研究の立ち位置があやふやなままなのではないか、この研究は先があるのか、などなど。留学期間の中頃まで、先に述べた専門の授業が立て込んでいたこともあるが、それ以上にウジウジとしていたために、5月くらいまでは進捗があるようでなかった。
捗が“ない”と断言するのではなく、“あるようでない”とするのには、理由がある。留学をして一人の時間が増えた分、様々な事柄について深く考えるようになったからだ。詳細は割愛するが、この事柄というのは“なぜ研究するのか”という根本に触れるものであって、やはり考え続けなければならない。しかし同時に、考え続けることと、研究を進めることとは、まさに別の次元にあるのである。私はそんな簡単なことを見落としていた。
そんな折、ある一人の中国人にかけられた言葉が、私の意識を大きく変えた。曰く、「とりあえず前に進めばいいじゃない」である。まさにその通りである。仮説は間違えているかもしれないから仮説なのであり、研究の立ち位置など無限にあるし、世に知られていない研究などおそらく星の数ほどある。勝手に考えて勝手に悩むことほど、ある意味馬鹿馬鹿しいことはないのだ。
そこからは、怒涛の巻き返しである。考えたことは一度置いておき、とにかく論文を読み、書くことを大事にした。読んで読んで読んで、書いて書いて書いて・・
すなわち、この留学を通じて私は“とりあえず進む”ということを強く学んだというエピソードである。
留学費用
今回の留学は中国政府奨学金を得られ、渡航費の支援もいただけたため、保険料(約7万円)のみ自分で支払った。
中国政府奨学金は月額3,000元である。日本円にしておよそ5万円ほどだ。一見微妙な金額に思えるが、中国での物価を勘案するとおそらく日本で10万円ほどもらっている感覚と言っても過言ではないと思う。質素に暮らせば1500元ほど、かなり贅沢に過ごしても300元ほどは余ると思われる。これに加え、奨学生は寮費が免除されるため、経済的にかなり恵まれていたと言える。
留学先での住居
留学先では寮に滞在した。キャンパスアジアプログラムでは、特段申し込みなどをする必要はないが、寮に滞在するか否かという意思は、メールの返信で送る必要がある。
寮は二人一部屋であった。とはいえ、ルームメイトと共有するのはシャワーとトイレ、客間だけであり、それぞれに個室が与えられている。留学生のルームメイトは中国人学生と決められているようである。私のルームメイトは江西省出身の修士学生であった。
留学先での語学状況
文系の専門に入るなら、授業は全部中国語であると思ったほうが良い。英語は学生間のコミュニケーションくらいに使用するが、お互いネイティブではないのでだいたいで大丈夫である。
生活は当然全て中国語である。寮の管理人の方々もほぼ英語を話すことはできないため、中国語で意思表示をする必要がある。全く勉強したことがないならば、人に依存するほか手段はない。
単位認定、在学期間
先方で履修した科目は東工大に類似した科目が見当たらないため、単位の認定は見送る方針である。在学期間は半年延長する予定である。
就職活動
留学先では就職について全く考えず、研究に集中していた。帰国後のいま、9月卒業は就職先が限られるのではないかと感じているため、まずは東工大の学生支援課にお世話になることを考えている。
留学先で困ったこと
大学の外に出ると、いろいろな人がいろいろな中国語を話すため、会話が成立しにくい。したがって、質問してもその答えの意味がわからないことが多々あった。中国語の経験不足である。
留学を希望する後輩へアドバイス
当たり前だが、どこへ行こうと英語が普遍的な言語であると思って渡航しないこと。