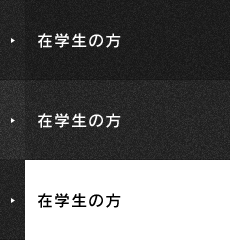キャンパス・アジア TKT CAMPUS Asia Online Research Symposium 韓国科学技術院(KAIST) 2020 年 12 月 4 日 ~ 2020 年 12 月 5 日
留学時の学年: |
修士課程2年 |
|---|---|
所属: |
生命理工学院 生命理工学系 生命理工学コース |
留学先国: |
大韓民国 |
留学先大学: |
韓国科学技術院(KAIST) |
留学期間: |
2020年12月4日~2020年12月5日 |
プログラム名: |
参加プログラムの概略
TKT Campus Asia Research Symposiumは清華大学(中国)、KAIST(韓国)、東工大の学部生と大学院生が二日間にわたって各々の研究成果について発表する場です。他のシンポジウムと大きく異なる点の一つが、発表する分野の枠組みの制限がないということです。参加者は多様な分野の研究について知見を深めるとともに、分野外の聴衆に対して自身の専門分野をわかりやすく説明する機会を得ました。また、このシンポジウムの進行は有志でstudent chairを務める学生により取り仕切られ、最終日には参加学生による投票で優秀発表者が選出されました。
活動内容及び感想
事前に、発表者は英語で400単語を上限とする発表要旨を作成しました。発表者の要旨は要旨集としてまとめられ、プログラム参加者に配布されました。また、student chairとして当日のプログラム進行を担う学生は事前にミーティングに参加し、円滑にイベントを進行するため準備しました。シンポジウム初日の冒頭に、Jihan Kim教授(KAIST)による特別講義が行われました。AIを用いた材料の設計を行うプロジェクトの目的やその詳細な研究方針について解説していただきました。深層学習の原理についての解説もされていたため、本分野に馴染みのない参加者にとっても興味深い発表であったと思います。発表終了後には、参加者から多くの質疑応答がされました。
続いて、参加学生による発表のセクションに移行しました。清華大学、KAIST、東工大から合計16人の学生が二日間にわたるシンポジウムで発表を行いました。若干の時間の前後はあったものの、発表者一人当たり発表時間15分、質疑応答5分が割り当てられました。事前に決められたstudent chairの学生の進行に沿って全日程のプレゼンテーションが行われました。参加者は自分以外のプレゼンテーションを30点満点で採点し、合計点を競う形で優秀発表者を決定しました。
プログラム1日目、2日目共に学生によるプレゼンテーションが終了したのちにクイズ大会が行われました。Kahoot!というサイトを用いて、当日行われたプレゼンテーションの内容に基づくクイズが出題されました。クイズの得点が高かった参加者は表彰がなされました。
プログラム2日目に全過程が終了したのちに、表彰がなされました。best presentation awardに加えて、best chair award、best audience awardの対象者が発表されました。最後に、参加者全員から一言ずつシンポジウムの感想を共有したのちにプログラム全過程が終了しました。参加者はシンポジウム終了後1週間以内に、testimony reportを作成し、提出しました。
このようなinternational symposiumで発表する機会は私にとって初めての経験だったので、非常に緊張しました。残念ながらbest presentationやbest chairには選出されなかったものの、積極的に質疑応答を行ったことでbest audienceに選出されました。韓国や中国の優秀な学生の発表は研究内容が充実しているのみならずユーモアも交えたものであり、今後別の機会で口頭発表する際に非常に参考になるであろうものでした。
プログラム参加を終えて、自分自身の成長を実感したエピソード
本プログラムを通して、一参加者という立場に甘んじることなく自分事としてシンポジウムを積極的に盛り上げることの大切さを学びました。本シンポジウムで私はプログラムの司会進行係であるstudent chairの一人として立候補しました。私は他のstudent chairの人のやり方に倣い自身が割り当てられた時間内で、全てのプレゼンテーションが予定時間通りに進行できるように心がけました。一つのプレゼンテーションが終わるごとに、chair personは他の参加者に対して質疑応答を募ります。しかし、時に誰も挙手しないことがありました。無言の時間をなるべく避けるために、このような場合には基本的にchair personが質問を切り出します。円滑にシンポジウムを進行するためのタイムキープをしながら発表内容に対する質問を考える経験はこれまでなかったため、予想したよりも多くのエネルギーを要しました。新型コロナウイルスの世界情勢の影響でいまだに対面での交流がかなわない昨今ですが、私はstudent chairの役割を通して多くの学生と意見交換を積極的に行うことができたので、この役職に立候補した価値は十分にあったと思います。シンポジウム終了後、私がchairを務めたセッションでプレゼンテーションをした学生の一人からメールで感謝の内容の連絡をいただきました。オンラインという形で開催されたシンポジウムですが、このように他大学の優秀な学生とつながることができたという事実は私にとって大きな財産となりました。 イベントに対して受け身の立場で臨むのではなく、自分の力でより良いものを作ろうという意識を持ったことで多くの収穫を得ることができたのだと確信しております。
プログラム参加経験を今後どのように活かしたいか
本プログラムを通して、自身の分野外の研究発表を聞く際の姿勢に変化が生じました。専門用語等に対する知識が欠如しているがゆえに一部理解が困難な場面があるものの、発表者に対して質問をする前提でプレゼンテーションを聞くと頭の中で情報を整理しやすくなることに気づきました。研究室内のミーティングでもこのような意識を持つことで、プレゼンテーションの時間を有意義にできると考えました。また、清華大学やKAISTの学生がノンネイティブとして英語を話す様子や分野外の学生に自身の専門分野を説明する方法は非常に目を見張るものがありました。自分の中の「当たり前」を客観的な視点で捉えることで多くの視聴者が理解できるようなプレゼン技術を身につけたいと思いました。
オンラインで苦労した点(もしあれば)
自分がプレゼンテーションを行うときに、視聴者の反応の様子が見えにくい点について苦労しました。参加者がカメラをoffにしていると彼らが私の発表を理解できているのか目で見てとりにくいと強く感じました。これを受けて、私は今後オンラインでプレゼンを聴講する機会があれば少し大げさにリアクションを示すことが大切だと学びました。
同様のプログラムへの参加を希望する後輩へアドバイス
コロナウイルスの影響で、昨今は大学での対面での交流が難しい状況にあると思います。そのような中でも、みなさんが想像する以上にオンラインで国内外を問わず交流をする機会で溢れています。東工大生という貴重な立場を生かして、在学期間中に積極的に活動範囲を拡大してみてはいかがでしょうか。
その他(あれば)
今回、東工大生の参加者は私一人だけでした。もう少し東工大生が多いと心強いと思いました