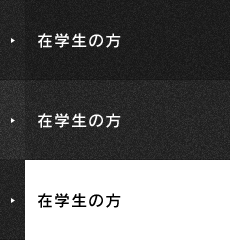TASTE 海外短期語学学習(中国語)春派遣 2025年2月24日~3月19日

留学時の学年: |
B2 |
|---|---|
所属: |
環境・社会理工学院融合理工学系 |
留学先国: |
台湾 |
留学先大学: |
国立台湾大学 |
留学期間: |
2025年2月24日~3月19日 |
プログラム名: |
留学先の概略
私が今回参加したNTU Plus Academy のChinese Language&Culture は、かつて帝国大学の1つであった国立台湾大学が主催するプログラムで、約3週間という期間の中で中国語力の向上と文化体験・理解を目指すものである。参加者の多くは日本人だったが、中には韓国、アメリカ、中国などにルーツがある人もいた。中国語力は不問であったため、一度も勉強したことがない人もいれば、ネイティブと問題なく会話できるレベルの人もいて、中国語専攻の人はそれほど多くなかった。
留学先での授業内容

試飲しながらの台湾茶の授業
留学中はまず午前に中国語の授業が行われた。クラス分けは留学の1か月ほど前にグーグルフォームで提出した文法、読解、作文の力を測る筆記試験と、スピーキングテストの成績に基づいて5クラスに分けられ、私は初め真ん中のクラスに所属していた。そのクラスでも日常生活でよく使う表現などを教えてもらえたのはよかったのだが、クラスの人数が多すぎることもあって授業中のスピーキングの機会が少なく、また文法や単語もほぼすべて既習事項で物足りなさを感じていた。このままだと台湾に行って会話力を伸ばすという目標を達成できないと考え、2回目の授業後にクラス変更を申し出た。上のクラスで体験した後、「あなたのリスニング力とスピーキング力はかなり低いので、負担が非常に大きくなると思うが大丈夫か」と該当クラスの先生から念を押されたが、クラス移動の意思が強かったので、頑張れますと答えて1つ上のクラスに移動させてもらうことになった。
移動先のクラスでは課題が非常に多いうえ、毎日のように听写というディクテーションテストか、演讲という1,2 分程度のミニプレゼンがあり、常にその準備に追われていた。一方で、人数が少ないこともあってか発言の機会が格段に多く、一人一人発音や文法のミスを細かく指摘してもらえたため、これまで独学する中では気づかなかった自分の悪い癖や間違いを自覚することができた。授業自体は、教科書の新出文法や単語を活用して、日常生活や社会問題に関する意見を述べるのをひたすら繰り返すのが主で、つたないながらも中国語で意見を表明できるようになったのは大きな自信につながった。また、内容に付随した雑談で、先生が台湾社会の実情を教えてくれるのも非常に興味深かった。
中国語の授業のうち成績評価で大きなものを占めるのは、中間テスト・期末テスト・成果報告であるが、中間テストはリスニング試験、筆記試験に加えて個別のスピーキングテスト、期末テストは筆記試験と事前に用意した3分程度のプレゼンの発表によって評価された。成果報告は最終日に複数クラス合同で行われ、セミフォーマルの指定で司会者と審査員もいたため、和やかな雰囲気ながらも程よい緊張感があった。私のクラスでは、複数人での発表か1人での発表かを選ぶことができ、私たちは相談の末、3人で中国の中秋節に基づく故事の劇を披露することになった。台本を含め1から自分たちで劇を作り上げるのは大変だったが、発表に向けて議論する時間は非常に充実したもので、良い思い出になった。
午後には、チューターステーションという台湾大学の学生による授業のフォローが行われるか、台湾文化に関する講義・体験が実施された。チューターステーションでは、教科書のロールプレイのパートをやるか、宿題をやりながら学生と自由に会話するかで、1度授業の枠で夕飯に出かけたこともあった。台湾文化に関する講義では、故宮博物院・音楽・お茶といった興味深いテーマが取り上げられ、文化体験では客家伝統の傘やうちわづくりなどを行った。講義や体験の多くは、後述する課外活動とリンクしており、いずれもリラックスして参加できるものだった。
留学先での課外活動

レールバイクからの景色(龍騰斷橋)
課外授業は留学期間に計3回行われ、2回は中国語の授業がある日の午後に、1回は丸1日の校外学習として実施された。まず、1回目の台湾有数の観光地の1つである淡水付近に位置する關渡への訪問では、關渡宮という媽祖廟や台湾で最初の自然公園を見学した。2回目の丸1日の校外学習では台中付近の苗栗を訪れ、料理や博物館を通じて客家文化に触れた。この日特に印象深かったのは、台湾の潜在的世界遺産の1つとされる臺鐵舊山線である。現在は廃線となっている線路の上を4人乗りのレールバイクで走りながら景色を楽しむことができ、忘れられない時間になった。3回目は、新北市の文山農場でお茶摘みと摘みたての茶葉を加工する工程を体験した。
いずれも、旅行ではめったに行かないような場所だったため、台湾の新たな一面を知ることができ台湾の文化への認識が深まった。
留学から何を学び、それを今後どのように活かしたいか
今回の留学で私は人生初の一人暮らしを海外で経験することになった。寮で生活する場合と違い、一歩学校の外に出てしまえば、すべて1人で解決しなければいけない環境だったため、その中で学んだものは非常に大きいと思う。特に、今回の留学中はこれまで遭遇してこなかったような些細なトラブルが頻発し、そのたびにつたない中国語で状況を説明したり助けを求めたり必要があった。日本にいるときは、極力トラブルや周りとのコミュニケーションを避けていたが、留学中には「外国人なんだから失敗して当たり前」「問題が起きたら中国語を練習するチャンス」とトラブルに積極的に立ち向かえるようになり、結果として授業外でも中国語を練習する機会を多く持つことができた。
また、私は中国に超短期の留学をしたことがあるのだが、その時の体験と今回の留学を比べてしまい、初めの数日は「前回の方が良かったな」と後ろ向きに考えてしまっていた。しかし、途中で今回の留学の環境自体を変えることはできない、より良い経験にしたいなら自分が変わっていくしかないと気づき、その1つの行動としてクラス変更も申し出た。初めは周りのレベルの高さやプレッシャーの大きさにくじけそうになることもあったが、親身になってくれた先生や周りのクラスメートに自分の成長で恩返ししたいという思いで必死に勉強した。結果、小テストや中間・期末テストではよい成績を残すことができ、最終日の先生からの講評でも「クラスを移動してきて、話すのがあまりにも遅いので初めは心配していたが、非常に熱心に勉強してくれたし、よく話せるようになった。文法や語彙に問題はない、発音は依然として課題だがこの3週間でかなり良くなったと思う」との言葉を頂けて、これまでの努力が報われる思いだった。
また、今回の留学で語学力には文化や生活習慣の理解も含まれることも痛感した。文法や語彙の習得は日本にいながらでも十分可能だが、留学中にところどころで日本では見受けられないような台湾の生活習慣に遭遇して、中国語上の意味は分かるが行動が理解できない、自分がどうすればいいか分からないと戸惑う場面があった。逆に、現地の人の習慣を知っていれば、中国語がすべて聴き取れなくても自分が何をすべきかわかることも多かった。どれだけインターネット上で情報を得られたとしても、文化・風習に関しては現地に行かなければ真に理解しているとは言えないので、今回の留学での体験が自分の語学力の中で欠けている要素の1つを補ってくれたように思う。
高校生から念願だった国立台湾大学への留学を実現し、今よりもさらにレベルアップした状態で再び中華圏に戻ってきたいという気持ちが一段と強くなった。今後も、専門科目の学習と並行して中国語に関しても日々研鑽を積んでいき、自然な発音と表現を追求したい。
留学前の準備
留学情報は主に台湾大学のプログラムホームページと事前に送られてくるStudent Manual を参考にしていた。また、以前同じプログラムに参加した東工大生(科学大生)の体験談を読むことでイメージがわいた。航空券は合格が分かってすぐ、普段家族旅行の際に利用しているサイトから自己手配した。台湾は90 日以内の滞在であれば、留学目的であってもビザは不要である。中国語は第二外国語の授業もとっていたが1年生の秋から主に独学で進めていて、毎日中国語作文(日記)と音読をしていたほか、中国語のYouTube 動画や映画もよく観ていた。留学直前の資格試験のスコアはHSK5 級239 点だった。
留学費用
渡航費は4 万6 千円、プログラム参加費は登録料と学費を合わせて約20万円、現地の生活費はお土産等も含めて約8万円、住居費はAirbnb 経由で手配したアパートで1人暮らしをしていたため約20万円、保険料は約8千円、奨学金はJASOO の従来の6万円に加え、臨時の留学継続特別奨学金2万円が支給された。これらを相殺すると、留学費用としては約45万円となる。私は、週末に新幹線で遠方に出かけたり多額のお土産を買ったりしたほか、大学手配の寮を選択しなかったためこの値段となったが、寮に泊まったうえで節約するように努めれば30~35 万程度に収まったと思う。
留学先での住居
今回の留学では大学手配の寮もあったのだが、諸事情によりAirbnb で大学近くのアパートを自己手配した。宿泊費は大学手配の寮場合の約2倍してしまったが、大学、飲食店街(夜市含む)、スーパー、MRT 駅に近い交通至便な環境で、風呂・トイレ・キッチン・洗濯機なども含め完全に貸し切りだったため、快適性が極めて高かった。Airbnb は最近では短期留学における宿泊先の選択肢の1つとなっており、スーパーホストという信頼性が高いホストの物件を選べば、安全性を過度に心配する必要もない。現在でも掃除機を使わず代わりに粘着クリーナーと雑巾で掃除をする、ごみ集積所がなく毎日決められた時間にゴミ収集車に直接ごみを出す必要があるなど、寮生活では気づかなかったであろう日本と台湾の生活習慣の差異も体感できたので、快適性を確保したい、現地人と同じような生活を体験してみたいという人は、一考の価値がある選択だと思う。
留学先で困ったこと
台湾は全般的には日本と同じような環境で快適に生活できる国だが、いくつか人によっては気になるであろう点があったので、紹介しておきたい。
まず、1つ目は長袖長ズボンでも蚊に刺されることがあり、意外と厄介な影響があるということ。私も実際留学中に2回耳の後ろを刺され、いずれも以前に日本の皮膚科で処方された薬を塗ることで治ったのだが、中には日本から持参した市販薬では対応できず、痛みと腫れに耐えかねて現地の病院に行っている人もいた。日本の市販薬では台湾の虫に対応できないことがあるそうなので、医師に処方された薬を持参するか、現地で虫よけのアイテムをそろえるのが良いかもしれない。
2つ目は、台湾のトイレ事情だ。水圧の関係から多くの場合、トイレットペーパーを流せないのは有名だと思うが、それよりも観光地を外れると洋式トイレがほとんどないことに驚いた。特に、大学構内では一部の新しい建物を除いてはすべて和式で、和式トイレの経験がほとんどない人はかなり困っている様子だった。また、1 食200 元未満程度のローカルな飲食店ではたいていトイレが設置されていないので、心配な人は大学や駅などで済ませておく必要がある。
留学を希望する後輩へアドバイス
よく短期留学は意味がないという言葉を耳にするが、短期であれ長期であれ経験に意味をもたらすのは本人の意識と努力だと思う。私が台湾に滞在したのはわずか24 日間だったが、「必ず中国語のリスニング力と会話力を伸ばす」という強い意識で、英語で話しかけられても中国語で返答するくらい、徹底して中国語を使うことにこだわった。結果、語学力に関しては想定を上回る成果を出すことができたし、帰国後日本の生活習慣に戸惑うほど台湾の生活習慣が体になじんだ。留学は決して安くないお金を投資して行くものなので、気楽な気持ちで参加せず、必ず自分に課した目標を達成して帰ってくるという強い意思を持つべきだと思う。