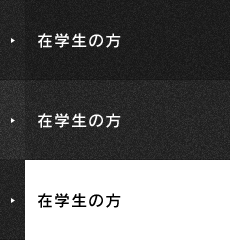マサチューセッツ工科大学-東工大 原子力系学生交換プログラム マサチューセッツ工科大学 2019 年 8 月 26 日 ~ 2020 年 1 月 31 日

留学時の学年: |
学士課程4年 |
|---|---|
所属: |
環境・社会理工学院 融合理工学系 |
留学先国: |
アメリカ合衆国 |
留学先大学: |
マサチューセッツ工科大学 |
留学期間: |
2019年8月26日~2020年1月31日 |
プログラム名: |
留学先大学の概略
マサチューセッツ工科大学(MIT)は1861年4月10日に創設された私立大学。所在地はマサチューセッツ州ケンブリッジで、約5000名の学部生と約7000名の大学院生が在籍している。学部生は二年次から各学部に配属されるシステムとなっており、各学部定員があるわけではなく、希望すればどの学部にも所属することができるようだ。各学部には番号が振られており、番号を聞けば何専攻なのかが分かるようになっている。2019年秋の時点では、コンピュータサイエンス学科(Course 6)が一番大きな学部で、機械工学科が二番目であった。研究施設はもちろんのこと、キャンパス内の福利厚生施設も充実しており(寮、スポーツセンター、病院等々)、部活動や有志団体による活動も盛んである。マスコットキャラクターはビーバーのTIM。

MIT中央にあるドーム

キャンパス内にはパブリックアートがいくつかある。

形が独特なキャンパスの建物
留学前の準備
学士課程で留学した場合
融合理工学系の研究室配属は年明け前にされており、1月から3月にかけては学士特定課題研究に向けて準備をしていた。留学の話が紹介されたのが1月の初旬で、留学の選考が1月中旬、決定したのが2月の初旬だったと記憶している。選考は、英語エッセイ+英語面接であったが、応募することを決めてから締め切りまで時間が無かったので、急いで応募書類をそろえた。選考の準備と同時並行で「トビタテ!」の書類選考へも応募した。トビタテへの書類応募の締め切りを勘違いしており、締め切り3時間前から書類の準備をはじめるという騒ぎもあったが、担当者様のご厚意で受理していただいた。
留学の採用通知があってから7月にかけては、留学のための書類準備(東工大への書類、MITへの書類、留学用のVISA申請)、トビタテ二次への準備、TOEFL対策、学士特定課題研究を同時並行で行った。幸運にも大学院入試はA日程だったため、準備にはあまり時間を使わなかった。トビタテの事前研修への準備は、研究の隙間時間を使って間に合わせた。8月は学士特定課題研究の提出とプレゼンの準備で手一杯であったため、荷造りはプレゼン後急ピッチで行った。MITでの生活に必要なもの(銀行口座、携帯等)は現地調達できるもの以外は日本でそろえた。銀行については現地で簡単に開設できるが、開設するまでに数週間かかるので、それまではクレジットカードまたは現金でしのいだ。携帯については、端末を日本で買い、SIMカードを現地調達した。FreeWiFiが至る所にあるため、最初の数日はSIMカード無しでしのいだ。しかし、諸々の登録に電話番号が必要だったため、早めに入手した。
プログラムに応募してから出国するまでバタバタとしたため、出国するまでの準備はしっかりとしていたものの、出国してから日本でしなければならないこと(大学院への入学意向確認書や、奨学金の手続きなど)まで手が回らなかった。そのため、留学中に連絡を受けて焦る場面が多くあった。
その他
MITのシステムについてはオリエンテーションで説明があったため、そこで紹介されたウェブサイトで情報収集をした。科目のシラバス、UROPのポスト等を見つけることができた。しかしながら、WEBページの情報と実情が異なるということはしばしばあるので、参考程度に考えていた。
一番の障壁だったのが、英語の条件(TOEFL iBT100点)であった。学士特定課題研究の合間に単語を覚えたり、演習をして形式に慣れたりした。特にスピーキングについては、タンデムという語学プログラムに参加して英語の会話を練習した。タンデムとは、学びたい言語を話す留学生とペアを組み、日本語を教えたりその言語を教えてもらったりできるプログラムで、英語の条件の突破に大いに役立った。また、タンデムのパートナーになった学生がMITからの留学生だったので、準備中に質問することができた。
ビザはJ1ビザを取得する。ビザ申請に必要な書類は早めに入手しておくことをおすすめする。英語要件を満たすとMITから受け入れ許可書が送られてくるため、それまでに他の書類をそろえておくとスムーズだろう。書類の他にもアメリカ大使館のWEBページで入力しなければならないフォームが複数あるので、こちらも忘れずに提出する。書類をそろえ、フォームを提出した後、領事館まで行き面接をすれば申請完了。

ほとんどの寮にはビリヤード台があり、気分転換によく遊びました。
寮はMITのキャンパス内にある寮か、キャンパス外にあるIndependentLiving Group、もしくは自力で探すかの三択になるだろう。キャンパス内にある寮が最も便利ではある。MIThousingのWEBページから各寮の情報と抽選へのエントリーができる。抽選結果やどこに入寮することになったのかなどについては問い合わせなければ通知されないのでMIT housingに再三問い合わせるべきだ。仮に返信があっても、その内容通りに事が進むことは稀なので、期日になっても連絡が来ない場合は問い合わせをするべきだ。私の場合、入る部屋が決まったのが搭乗の直前であり、当該の寮に到着しても入寮者リストに名前がないという状態だったので、MIThousingには再三問い合わせて、言質を取ることを徹底することをおすすめする。キャンパス外のIndependentLiving Groupについては各グループにそれぞれ問い合わせる必要がある。キャンパス内の寮に空きがない場合はMITのInternational Student Office(ISO)からIndependentLiving Groupを紹介するメールが来るので参照することをおすすめする。OnCampusの寮より家賃が安いことが多いので、事前に確認すると良いだろう。
滞在にはMITの保険に加入することが必須になる。また、寮に滞在する場合は、入寮の条件として健康診断といくつかの予防接種を受ける必要がある。英語でのリサーチ及び申し込みになるが、なかなか聞き覚えの無い医療用語と対する必要があるため、根気強く準備する必要がある。また、アメリカで歯医者に掛かると非常に高額になるので、時間に余裕をもって検診を受けることをおすすめする。
UROPについては、学期開始から締め切りまでだいぶ時間があるのであまり焦らなくても良いが、日本にいるうちからどのような活動があるのかをざっと把握しておいた方がスムーズ。余裕があるのなら、募集がかかっているポストにメールを送って話を聞いてみるのも良いだろう。
留学中の勉学・研究
学期中は3講義+UROP(Undergraduate Research Opportunity Program)の合計42単位を履修した。

元学長曰く、“MITで教育を受けることは消火栓から水を飲むようなもの”
講義
22.01Introduction to nuclear engineering and radiation interaction
このプログラムの必修科目で、原子核工学の基礎を講義と実験を通して理解する授業であった。毎週課される宿題、毎授業ごとあるリーディングなどなど、情報量とやることがとても多い科目であった。
宿題は大体7~8時間ほどかかった。問題の難易度はそこまででもないが、データを探したり整理したり、考察したりと手数がとても多いため時間がかかった。苦労して揃えたデータを使って計算した値が単位の変換を間違えていて不正解、というようなことがあると非常にストレスフルではあるが確実に深い理解が得られる良い実践であると思う。特に面白かったのは、自分の爪にどんな元素が入っているかをガンマ線のスペクトルから解析するというもの。残念ながら自分の爪からは珍しい元素は見つからなかった。
リーディングは大体短い論文か教科書の一章分程度。これも各々は難しくないが、量が多い。他の科目のリーディングもあったため、基本的に何か読んでいるという生活がしばらく続いた。英文の論文を読むという機会がこれまであまりなかったため、論文を読むこと自体に若干抵抗を感じていたが、そんなものを感じる余裕もなく読まなければならなかったため、今ではその抵抗も感じなくなった。とにかく量が多い。
実験では非常に珍しい体験を多くさせてもらった。Carbon Pileに燃料を手で挿入して、臨界に近づける実験や、アクセサリーが本物の金かどうかEMS(Electron Microscopy)を使って判別したり、ガイガーカウンターを組み立てたり、原子炉の出力を上げ下げする体験をさせてもらったりと、他ではあまりできそうにない体験を多くさせてもらった。特に原子炉の運転はMITが原子炉を持っているからこそできる実験で、少し羨ましさを感じた。
講義を担当するMike先生は本プログラムの担当教員でもある。非常に話が上手い先生で、講義を聞いていて飽きることはなかった。最も印象に残っている講義は、ネットに転がっているデマ記事のどこが間違っているのかをどこが正しいのかを見極める講義だ。原子核工学は最も不安を煽りやすい分野であるため、データや科学的知見をもってきちんと説明できるようになりましょうというのが趣旨であった。今まで実践したことがないことだったので、実際に元の論文を読んで記事が正しいかどうか検証することは良い経験になったと思う。
22.12Radiation Interactions, Control, and Measurement
学期の後半にのみ開講される講義。22.01の講義内容と被るところもあるがより詳細になったという印象を受けた。ステップバイステップの解説と、手厚いオフィスアワーのおかげで、難解な内容も理解することができた。他の科目に比べて、あまりリーディングは課されなかったが、その分授業の復習としての演習があった。22.01に比べ、毎週の宿題の難易度は高くなかったが、その分問題数が多かった。
4.341 Introduction to photography and related media
昨年まで写真部に所属していたほど写真が好きなので、この科目は初めから履修しようと決めていた。授業は2時から5時までの三時間を週二回。定員12名のところを教授の裁量で13名履修できるようにしてもらったため、最後の一枠に入れてもらった。授業内容は大きく分けて実技と講義で、実技ではフィルムカメラの使い方から、フィルムの現像、暗室でのプリント、Photoshopの使い方までアナログとデジタル両方を用いて作品を製作した。講義では写真の歴史、芸術論、アーティストの作品紹介やリーディングを通して写真という媒体への理解を深めた。
また、日々の実践として、毎日日記をつける課題が課された。ある人は絵を描き、ある人は詩を書いて、日々の感情の機微等を各々が各々の形にしていた。今回の講義では、全体を通して「日常」がテーマとなっており、単調になりがちな日常をより豊かなものにするための方法としてこの日々の実践が重要なコンテンツとなっていた。また、蓄積された物の中から、最終作品のヒントを見つけられたり、普段は意識しない自分の視点を振り返って発見できたりと、意外な発見が多くあった。文献を通して写真へ対する理解を深めるとともに、物事の捉え方を豊かにするヒントを発見できた。非常に楽しい科目であった。
学期の最後には制作した作品の発表会があり、一学期の集大成を発表することができた。
UROP
UndergraduateResearch Opportunity Program(UROP)では、Forget教授研究室所属のPh.D.課程の学生に指導していただいた。内容は核データの評価手法(WMP)においての誤差伝搬についてであった。OpenMCというモンテカルロシミュレーションコードを用いてのサンプリングとその解析を行うというのが元々の計画であったが、NES所有のクラスターへの開発環境のインストールが難航し時間切れとなってしまった。最終的に達成できたのは、各核種における共分散マトリックスの計算手法の把握だけである。UROPの難易度にはどうやら当たりはずれがあるようだ。同じようにUROPをやっていた別の交換留学生には毎週のようタスクが課されており、授業と両立するのが大変といった様子であった。一方で私は、週一回のミーティングで宿題を出されるという形式だった。学部学生一人に対してPh.D.学生一人が付くというスタイルはほとんどのUROPで採用されているようだ。
IAP
IAPとは一月に履修することができるプログラムで、理工系に限らず、語学から映画まで様々な活動を行うことができる。ほとんどの科目では単位を取ることができるが、単位のない科目も多くある。
1月中の寮への滞在の条件が「単位ありのIAPクラスを履修する」とのことであったので、スペイン語基礎を履修した。三時間の授業が週5日あるという集中講義であり、講義スピードは非常に速く、MITの学生にとっても速いそうだ。MITでの言語クラス、特にIAP期間中のものは一学期分の内容を一か月で学習するので量が多い上にスピードが速い。拘束される時間も多く、授業の準備にも時間がかかるが、確かに自分の言語能力が伸びることを感じた。自分は知っているフレーズが”Buenos días”しかなかったが、一週間でスペイン語の文がなんとなく読めるようになった。

原子核工学科の建物にある核図表
留学中に行った勉学・研究以外の活動
Japanese Association of MIT(JAM)のイベント企画に参加し、イベントの運営、企画に携わった。日本文化を紹介する趣旨のイベントで、けん玉ブースを担当し、けん玉の調達から実演、指導までを他のボランティアの人達と協力し行った。意外にも多くの人がけん玉に興味をもってくれたようで、どうやって遊ぶのか?コツを教えてくれ!など、ひっきりなしに質問をされた。こういう技があって、こういう風にするとうまくいくと教えると飲み込みが速い人が多く、初めてやるにも関わらずいくつかのトリックを成功させている人もいた。
コロンブスデーの連休ではNYに行った。小さいころにNYに行ったことがあるようだが、記憶があるうちで行ったのは初めてだった。ボストンからバスに揺られて4時間ほどでNYに行くことができる。観光名所をいくつか回った後で体調を崩してしまい思うように動くことができなかったが、Charging Bullなどの有名スポットを回ることができたので満足している。
サンクスギビングの連休ではWacchusettsという場所にあるスキー場へ行き、スノーボードをした。シーズンのはじめということもあり、コンディションは微妙であったが、勘を取り戻しつつ楽しく滑ることができた。ボストンから1時間強で行けるゲレンデだったので、日帰りの観光にはちょうど良い。
年末にはトビタテの同期が訪ねてきたのでボストンの街を一緒に観光したり、料理を作って振舞ったりした。ちょうどクリスマス当日であったので、ボストンのトリニティチャーチのミサに参加したり、他の交換留学生も呼んでクリスマスパーティをしたり、翌日にはビール醸造所の工場見学をしたりした。
ボストンには美術館や博物館が多くあり、MITの学生であれば無料で入場できるところが多い。Museum ofFine Artsは何回か通った。宗教画からコンテンポラリーまで幅広く展示されており、絵画だけでなく工芸品等もあるため、一日ではまわりきれない。MFAの近くにはIsabella Stewart Gardner museumがあり、こちらもMITの学生なら無料で入場できる。MFAほど大きな美術館ではないが、展示の仕方が独特で他の美術館にはない体験ができる。日本の芸術品も多数展示されており、洋画の間に浮世絵が飾ってあったりして面白い。Museum of Scienceには世界最大のヴァンデグラフ起電機があり、それを使ったショーが楽しめる。一日で回り切れるほどの大きさだが、おなじみの実験から目新しい実験まで多くを楽しめた。

某映画の聖地

ボストン美術館
留学を終えて、自分自身の成長を実感したエピソード
英語圏の国なので、自分の英語力が鍛えられたという感覚がある。特にスピーキングとリーディングの能力は伸びたと感じている。スピーキングについては、伝えたいことが上手く言えずにあわあわするくらいから、伝えたいことは大抵伝えられる程度にはなった。また、簡単な雑談もあまり引っかからずにできるようになった。リーディングについては読むスピードがだいぶ速くなった。学期のはじめに本を買ったのだが、学期が終わってから読むと内容をすっと理解できるようになった。
ヨーロッパ、北米出身の人が多いため、日本の文化等をあまり知らない人が多かった。そのため、彼らとする会話の中で日本についての質問が投げかけられることがあり、自国の説明をする機会が少なからずあった。興味をもって聞いてくれる人が多かったので助かったが、うまい説明はあまりできなかった。特に政治の話となると用語がほとんどわからないので苦労した。
滞在中、多くのトラブルに見舞われた。例えば、入居者リストに名前が載っていなかったり、MITのデータベースに登録されている情報が間違っていたり、私の滞在期間がMITと東工大側で食い違っていたり、等々。幸いにも多くの方々の協力を得ることができ、それらすべてを解決することができた。解決に取り組む中で、わからなかったらとにかく誰かに聞くという習慣がついた。わからなかったらメールして問い合わせる、不安があったら誰かに相談する、そんな習慣が滞在中についた。また、留学前は周りに遠慮して聞きたいことを聞けないということがしばしばあったが、滞在後はあまりそういうことは無くなった。個人的にはこれが一番大きく変わったと思うことだ。
MITの講義はタフだ。一科目につき、週五時間分の授業に加え、平均7時間以上かかる課題が毎週課され、加えて予習のリーディングが山ほど出る。MITの学生はこれを5つも6つも履修するらしいので驚いてしまう。私は3つ+UROPをとるので精一杯だったが、学んだ知識は確実に自分のものになっている。学んだ知識、また厳しい学期をやり抜いたことは自分の自信につながっている。

雪が降った翌日のグラウンド
留学費用
- VISA申請料等:4万円程度
- 渡航費:往復25万程度
- 予防接種等:100,000円程度
- 保険料:半期$1300
- 家賃:月$1000程度
- 食費:月$400~
- 交際費:月$250
- 観光等:月$150
- 交通費:月$100
- その他:月$100
- 出費総額:月平均$2000
- トビタテ!:月16万円支給+留学準備金25万
留学先での住居
滞在はキャンパス内にあるTang Residence Hall。大学院生用の寮で寮生同士の交流はあまりない。フラットを数人で共有するスタイルで、各自部屋が一つ与えられる。風呂トイレ、キッチンは共有。部屋の明かりのスイッチが部屋の外についていたり、洗面台の蛇口から出る水が白濁していたり、いろいろツッコミどころはあるが、部屋は十分以上に広かったので不満はない。家賃は月$1000+Taxで支払いはMITPAYというMITのオンライン支払サービスを使って支払っていた。
申し込み方法は、MIThousingのWEBページから希望申請、八月初旬の抽選結果を待って他の選択肢を検討するというのが当初考えていたプランであった。しかしながら、八月初旬の抽選結果がなかなか出ず、結局選択肢にすらなかった大学院生用の寮にアサインされた。MIThousingには再三抽選結果の開示を要請してきたが、結局返信があったのが出国後、出発ロビーで搭乗を待っている時だった。MITに着いたものの住むところがないといった状況にならないためにもMIThousingからの返信を待っている間に他の選択肢(Independentliving group)の検討もするべきだ。
ルームメイトは同じ交換留学生であるスロバキア人。日本食を作ると喜んだので、よく親子丼を作った。パスタの作り方を教えてもらう代わりにお米の炊き方を教えた。Tangには自分も含めて交換留学生が五人滞在していたため、この五人でよくビリヤードをしたり、バーでビールを飲んだりした。ほとんどがクリスマスを待たずに帰国してしまったので、年末年始は一人で過ごすことが多くなった。
留学先での語学状況
TOEFLiBT:100点はプログラム参加に必須であった。6月までに取得できないとプログラムに参加できなくなるという綱渡りだったが、ギリギリ間に合った。結局TOEFLは2回目のチャレンジで要件である100点を突破することができた。
英語を母国語とする人達+ヨーロッパ圏の人達は文化圏が同じということもあり、非常によくしゃべる。私自身そもそも話すことが好きでない上に、英語もカタコト、まして文化圏が異なるので共通の話題もないという三重苦に最初の数週間は直面した。リスニング、スピーキングは場数をこなせばある程度のレベルまでは到達できるため、数週間もすると会話のほとんどを聞き取れるようになったうえに、会話の輪の中での発言も多くなった。しかしながら、会話好きでないという点はどうしようもなく、周りと比べると社交的でないことは否めない。それでも良い友人に恵まれ楽しい時間を過ごせたのは幸運であった。
単位認定(互換)、在学期間
もともと単位互換はできないと聞かされていたのでするつもりはなかったが、担当の先生のご尽力でできることになった。帰国後に単位申請の手続きを進めることになる。専門の科目と教養の科目で一枚ずつ申請書を書く必要があったり、煩雑ではある。
就職活動・進学
もともと大学院へ進学する予定だったので、現地で就職活動はしなかった。ただ、その機会は多くあった。ボストンキャリアフォーラムやMITのキャリアフェアなど、大きな就職活動の機会が滞在中にあったので、様子見がてら参加した。就職する予定が無くてもインターンなどの機会がある可能性があるので、参加してみても良いと思う。特にCSの分野であれば、求人が山のようにあるので行ってみる価値はあるだろう。
大学院の合格通知書は米国へ渡航してから郵送されるので、実家もしくは協力者に届くようにしておくべきだ。米国滞在中にするべき手続きは入学意向確認書の提出のみであるので、締め切り前までに必ず提出できるように日本にいる協力者と連絡を密にするべきだ。また、学部在学中にJASSOの奨学金を受給している人は奨学金関連の手続きを米国滞在中にすることになるので、協力者と連絡を密にするべきだ。さらに、大学院でJASSOの奨学金を受給しようとしている人は、米国滞在中に採用申請をする必要があるため、こちらについても協力者と連絡を密にするべきだ。入学後、在学採用という形で申請することもできる。
以上の点の大半はTitechメールに通知が来るので、見逃さないように転送設定などをきちんとしておくと良いだろう。
留学先で困ったこと
単独での派遣であったため、最初の数週間は話す人が少なく心細かった。特に銀行口座の開設等の手続きが多い時期で、情報を共有しつつ進めることができればもう少し楽だったと思う。同じ境遇の人と確認しつつ進めることができなかったため、不安なことが多かった。また、交換留学生の中でも同じ学校から来ている人は各々のグループで情報をやり取りするため、そのグループでシェアされている有用な情報にアクセスできなかったのも不便だった。また、留学プログラム日程の認識が東工大側とMIT側で異なることが滞在中に発覚し、その調整結果を待つストレスフルな時期があった。また、MIT関連のWebサイトは恐ろしく情報を見つけづらいので、日本にいるうちから慣れておいた方が良いだろう。
また、MIT、アメリカ側の事だけでなく、日本で起こっていることにも困ったことはあった。当然ながら留学中は日本で起きていることに対応がしづらい。特に4年生の後期は大学院入試の結果と手続き、奨学金関連の手続きなど、重要なタスクが多い。それらの書類が郵送されてきても受け取ることがまずできない。窓口に取りにいかなければならないものもあったため、非常に不便であった。関東圏出身ならまだしも、地方出身であるとそれらの書類にアクセスできる協力者が非常に限られてくるため、滞在中それらの書類の処理に非常に困った。
留学または本プログラムを希望する後輩へアドバイス
留学の準備、留学中の諸々、留学後の手続きすべてにおいて言えることだが、わからないことがあればすぐに質問することを推奨する。どんな些細なことでも確かでなかったら分かる人に聞く。待っても返事が来なかったら図々しくもう一回聞く。そうすると、見落としていた点が見つかったり、新しい視点から物事をみられるようになったりすることが意外にも多い。質問する習慣をつけておいたほうが良いだろう。
また、言語の障壁は思っている以上に高いので、ボキャブラリーを増やし、使えるフレーズを覚えておくと便利だろう。海外ドラマを英語字幕でみるのは推奨できる勉強方法だ。完全に主観だが、スピーキング能力も向上する気がする。
アメリカでの生活で大切なのが、細かいことはあまり気にしないということだ。大事な書類には細心の注意が必要だが、それ以外の場面ではあまり気にしない方が良いだろう。いい意味でも悪い意味でもアメリカは多様な国なので、細かいことを気にしていると疲れてしまうだろう。バスの中で音楽をかけようが授業中にフライドチキンを食べようが、気に掛ける人は少ない。最初はストレスを感じることが多いかもしれないが、気にしない方が良いだろう。
最後に最も重要なのが、好奇心を大切にするということだ。MITでは学びの機会が十分すぎるほどにある。専門だけに限らず、他の文化的活動も盛んだ。また、街全体に学生を応援するような雰囲気がある。そのため、街にも学びの機会は多くある。それらを最大限に生かすには好奇心が必要だ。無機質な部屋に閉じこもっているよりは、外へ出て好奇心に従って行動した方が、充実した日々を送ることができるだろう。幸いにもボストンは文化的活動をするにはもってこいの場所だ。キャンパスからほど近い場所には美術館や科学館があり、街の中心にはアメリカの歴史を堪能できるスポットがいくつもある。好奇心に従って大いに学べば、この留学は非常に実り多いものとなるはずだ。

チャールズ川とボストンの高層ビル群
この体験談の留学・国際経験プログラム情報
他の関連する体験談
-

Tokyo Tech-MIT Student Exchange Program 2023年8月~2023年12月
- アメリカ
- マサチューセッツ工科大学
- 2023年8月27日~2023年12月27日
- 研究
-

Tokyo Tech-MIT Student Exchange Program 2023年8月~2023年12月
- アメリカ
- マサチューセッツ工科大学
- 2023年8月27日~2023年12月27日
- 研究
-

Tokyo Tech-MIT Student Exchange Program マサチューセッツ工科大学 2022年 9月 ~ 12月
- アメリカ合衆国
- マサチューセッツ工科大学
- 2022年9月6日~2022年12月22日
- 授業履修、研究