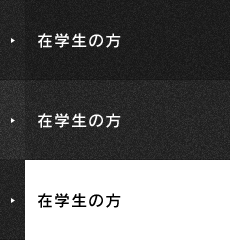Tokyo Tech-MIT Student Exchange Program 2023年8月~2023年12月
留学時の学年: |
学士4年 |
|---|---|
所属: |
物質理工学院 応用化学系高分子フォーカス |
留学先国: |
アメリカ |
留学先大学: |
マサチューセッツ工科大学 |
留学期間: |
2023年8月27日~2023年12月27日 |
プログラム名: |
留学先大学の概略
【概要】
マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology : MIT)は、1861 年 4 月 10 日に創立された私立大学。マサチューセッツ州ケンブリッジにキャンパスがあり、約 4500 人の学部生と約 6500 人の大学院生、約 1000 人の教員が在籍している。留学生の割合は約 30 %と、アメリカ国内でも高い割合となっている。現時点(2023 年秋 )では、コンピュータサイエンス学科(Course 6)が最大の学部で、全学部生の 3-4 割が Course 6 に所属している。学部生は二年次から各学部に配属されるシステムとなっており、一年次にはある程度決まった教養科目や共通の講義をとることになっている。また、一年次の成績は合否のみで判断されるようになっており、GPA に響かないことから、一年生でも GPA を気にせずに積極的にレベルの高い講義を履修できるようになっている。さらに、学部生でも自由に大学院講義をとることができる。
【キャンパス】
キャンパスは町と一体化したような感じであり、キャンパス内に学部生用の寮が 10 個ある。一年次は全員がこれらの寮で生活することになっている。研究施設はもちろん、スポーツセンターやジム、診療所などの福利厚生施設も充実しており、部活動や融資団体による活動も盛んである。
留学前の準備
【学士課程で留学した場合】
応用化学系の研究室配属は基本的に 4 月からであり、留学は配属希望を提出する前に決定していたため、研究室見学の際に、教授に留学に行きたい旨をあらかじめ伝え、学士特定課題研究との兼ね合いは大丈夫かなどについて尋ねて確認していた。留学の準備と学士特定課題研究、大学院入試が重なり、とても忙しかったが、ビザの取得や T2APPs での留学願などの提出は自分の予定だけではどうにもならないので、前もって準備をした。
【留学情報について】
ネットで調べたり、MIT と東工大の語学交換プログラムに参加した際にできた友人などに話を聞いて集めた。また、前年に留学に行った先輩の連絡先を入手できたので、先輩にも話を聞くことができた。専門分野に関しては一通り学部の授業で学んでいたため、MITでは大学院講義を履修したが、そのための準備は特にしなかった。
【英語について】
この交換留学プログラムに参加するにあたり、MIT 側から TOEFL iBT100 点を取得することを求められていた。最初は TOEFL iBT の試験形式に慣れることが大変だったが、夏休み中に重点的に練習することで、無事達成することができた。また、東工大の学生と MIT の学生がオンラインで語学交 換 す る プ ロ グ ラ ム に も 参 加 し 、 少 し ず つ 英 語 を 話 す 練 習 を し た 。 ま た MIT に はOpenCourseWare があり,MIT の過去の講義 をネットで視聴できるようになっている。
【研究活動について】
Course 10 の 研 究 室 に UROP(undergraduate research opportunityprogram)で参加した。渡航前からホームページでどの研究室の研究に興味があるかについて調べ、目星をつけておいた。渡航前に研究室の教授にメールで連絡をしたが、返信をもらうことができなかった。しかし、その研究室に所属している PhD の学生に連絡を取ったところ、面談を行ってもらうことができた。その結果、参加が決まったので、教授と連絡が取れなくても、学生に直接連絡を取ってみるというのも一つの手だと思う。その後は、研究についての詳しい説明を受け、research proposal を UROP 事務局に提出し、研究を始めることができた。
【ビザの取得について】
大使館に予約をとるところから始まり、準備しなければならない書類も多かった。基本的にネットで情報収集したが、必要書類を揃えたが、戸籍謄本や戸籍謄本の英訳、財務残高証明書などは実際には使わなかった。しかし、MIT への書類には財務残高証明書(英語)は必要であり、銀行や郵便局で取得するのも時間がかかった。
【ワクチン接種ほか】
ワクチン接種についても、間隔をあけて何回か接種しなければならないので、早めに準備しておけばよかったと思っている。寮にはキッチンがついていたが、料理ができないのでミールプラン(125 回分)に入っていた。食事は体調を良好に保つための基本なので、加入してよかったと思っている。携帯については、アメリカで使える SIM を日本で購入し、使っていた。MIT の中では,Wi-Fi が使えるので、データ使用量について心配する必要はなかった。
留学中の勉学・研究
講 義 は 22.01(Introduction to nuclear engineering and ionizing radiation, 12 単 位 ) 、3.941(Statistical mechanics of polymers, 12 単位)を履修した。
【講義について】
MIT ではスライドには講義の説明で用いる図のみを掲載し、先生が板書をしていた。また、講義前に予習として、教科書を読んでくることが課される。私は東工大では復習を重点的に行っていたが、MIT では予習が重要視されていると感じた。また、課題についても大きな違いがあった。東工大では講義内容を理解していれば解答できる課題が多いが、MIT の課題は、講義内容に関連してはいるものの、自分で調べたり、講義を理解しているだけでは解答できないような問題が多く出題されていた。新しい知識や疑問を掘り下げていく貪欲さ、自分が持つ知識や自分の頭を問題解決のためにどのように使うかを問われている気がした。特に大学院講義である 3.941 の課題は難しかったが、オフィスアワーがしっかり設けられているので、行けば教授が質問を受けてくださるのと、たいてい他の学生もいるので、何とか乗り越えることができた。
【グループワークが多い】
さらに、MIT ではグループワークをする機会が多いと感じた。私が履修したどちらの講義でもグループワークが設けられており、みんなの予定を合わせて時間を作らなければならなかったので、限られた時間の中でどのように最大限の結果を得るかというところにみんな注力していたように感じた。最初はあまりグループワークはやりたくないなと思っていたが、ここはこうなのではないかと思うところや、自分が意見を持っているところは主張をしたくなるため、グループワークを通して自分の言いたいことを英語で言うという訓練ができたと感じる。グループワークのテーマは、提示されたものから自分たちで選ぶことになっており、そういったところも、東工大と異なると感じた。また、講義中に質問する学生が多く、どんなに些細なことでも教授に尋ねていたのが印象的で、ここは東工大生と決定的に違うポイントだと思った。テストの対策として課題の復習ばかり行っていたが、実際には教科書や授業の内容自体の復習のほうが重要だったと感じた。また、周りの学生が全員院生だったので、様々なことを知っていたり、学ぶ意欲やモチベーションが高く、非常に刺激をもらった。
【UROP(研究プロジェクト)】
学部生のプロジェクトなので難しいことはやらせてもらえないのではないかと思っていたが、PhD の学生が 3 月に学会でポスター発表する予定の研究に参加させてもらうことができた。ポリマーネットワークにおいてどのようにクラックが進展していくかについて粗視化シミュレーションを用いて研究した。クラックの生成は局在しているのか、非局在しているのか、また、クラックを意図的に生成したネットワークを伸長した時にどのようにそのクラックが進展していくか、ネットワークがマクロな破断に至るまでの時間について導入したクラックにある臨界的な大きさがあるのか解明することを目標として研究を行っていた。週に一度の教授とのミーティングにも参加し、どのような方向で進めていくかについて話し合った。MIT 在籍期間にこのプロジェクトを終わらせることはできなかったが、あともう少しで結果がでそうだ。帰国後も研究に参加し続けることは可能だと言われたので、このプロジェクトが終わるまで参加し続けるつもりだ。
留学中に行った勉学・研究以外の活動
MIT 日本人会(JSU)が開催するほとんどのイベントに準備の段階から参加した。月見イベントやカレー作り、餅を提供するイベントなど、日本食を紹介するようなイベントが多く、日本食に興味を持っている人が多いことを実感した。 JSU のイベントや MISTI が開催する Japanese LunchTable に参加することで、人の輪が広がった。また、旅行やインターンシップなどで日本に来る予定だという学生も多く、私が帰国してからも連絡を取り続けられる友人ができた。日本語のクラスをとっている友人がクラスプロジェクトをしていたので、その友人と一緒に四字熟語のミニゲームを作成した。また、UROP の研究室の先輩方にもリンゴ狩りに連れて行ってもらったりした。個人的には旅行にも行きたかったが、思った以上に忙しく、行くことはかなわなかった。
留学を終えて、自分自身の成長を実感したエピソード
MIT の PhD の学生を間近で見て、研究への情熱をとても感じた。そんな中で、自分の成長を感じたのが、UROP の研究について教授や PhD の学生とディスカッションしていたときだ。シミュレーションのサイズを大きくする際、計算コストが高くなってしまうため、新しいアリゴリズムを探すか、セルリストを用いるか何かしらの修正を加えなければならなくなった。しかし、すでに比較的新しいアルゴリズムを用いており、また、セルリストは MD シミュレーションでよく使われる手法であり、粗視化シミュレーションに適用できるかは不明だった。しかし、系全体ではなくクラスターを緩和させていけばいいのではないかと思い、その考えを PhD の学生に伝えたところ、そのアイデアで研究を進めていくことになった。このように、研究について自分の考えや主張したいことを伝えられるようになったこと、それを活かして研究を進めていけることができたのが、最も成長を感じた点だった。
留学費用
私はアメリカに銀行口座は作らなかったが、作る場合多くの学生は Bank of America を使うようだ。寮費やミールプランの代金、保険料などは flywire を通して支払った。留学中は業務スーパージャパンドリーム財団から給付型奨学金をいただいており、留学準備金 25 万円、月額 20 万円の計 105 万円をいただいた。全体的な収支は下記のようになった。
【①準備費用】
飛行機(往復) 33 万円、予防接種 8 万円、海外保険 7 万円
【②生活費用】
住居費 100 万円、ミールプラン(125 回分) 30 万円、MIT 医療保険 20 万円、その他の生活費 15 万円
【③給付型奨学金】105 万円
差額(①+②-③) 108 万円
留学先での住居
私は留学中は MIT のキャンパス内の寮に住んでいたが、留学前に MIT から希望調査のメールが送られてくるので、調査フォームに希望する寮を入力し、8 月後半にどこに入寮できるかが決ったので、もしキャンパス内の寮に入居する予定なら、自分で探す必要はないと感じた。ルームメイトの有無は寮によるが、私が入った寮(MacGregor Dorm)は基本的に一人部屋だった。寮によってルームメイトの数や料金、ダイニングホールやキッチンの有無、イベントなども異なるので、希望を提出する前にしっかりホームページで調べた。ほとんどの寮では毎週 StudyBreakが開催され、忙しい勉強の間におやつを食べながら同じ寮の住人達とおしゃべりするというイベントだが、ここでも知り合いが増えるのと、英語を話す練習ができるので、参加してみるといいと思う。
留学先での語学状況
授業、研究、生活すべてにおいて英語を利用した。留学前の TOEFL iBT は 107 点(R : 29, L :29, W : 28, S : 21)、TOEIC は 930 点(R : 465, L : 465)であったが、講義を聴くのは最初から問題なかった。専門用語に関しても、予習の教科書を読む段階で出てくるので、わからない単語はその段階で調べておけば特に問題はなかった。ネイティブスピーカーと話すことが最初は難しかったが、2 週間くらいで慣れてきた。さらにグループワークによって自分が主張したいことを主張できるようになった。日常会話では、基本的に相手が話している内容が聞き取れ、笑顔でいれば問題ないと感じた。
単位認定(互換)、在学期間
単位互換は東工大で行う予定だ。在学期間の延長は行っておらず、2024 年 3 月に卒業する予定だ。
就職活動
MIT にいる間、ボストンキャリアフォーラムに行くことを考えていたが、忙しくて行くことができなかった。しかし、MIT への留学経験は確実にアドバンテージになっていると思うので、英語力や研究から得られたプログラミングスキルなどをこれからの就職活動に活かしていきたい。
留学先で困ったこと
MIT に到着してから 2, 3 週間目くらいからひどい風邪を患い、講義中に教室を出ていかなければならないほど咳がひどかった。日本から風邪薬を持って行っていたので服用していたが、1 カ月くらいは完治せずかなりつらかった。また、深夜(明け方?)4 時に就寝し、午前 10 時に起きるというような睡眠のサイクルになってしまったので、睡眠不足に陥っていた。
留学を希望する後輩へアドバイス
留学をする準備をしているときが最も不安に感じると思う。深く考えずに実際に行ってみてしまえば、それなりに何とかなるものである。ここまで留学の準備や大変だったこと、自分の成長を感じた点などを書いてきたが、この間、精神的につらいことも多く、くじけそうになったこともあった。自分が履修している講義の単位が取得できるかなど心配事も多かったが、諦めずに頑張り続ければ何とかなる。また、頑張っていれば運が向いてくる。特に MIT は求めれば与えられる環境なので、人との出会いや学びの機会など、色々なチャンスが転がっている。忙しさや精神的負担に負けず、この機会をつかんでほしい。