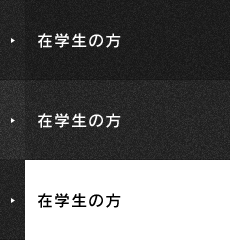協定校シーズンプログラム (リンシェーピン大学) 2024年7月1日~7月26日

留学時の学年: |
B3 |
|---|---|
所属: |
工学院電気電子系 |
留学先国: |
スウェーデン |
留学先大学: |
リンシェーピン大学 |
留学期間: |
2024年7月1日~7月26日 |
プログラム名: |
プログラムの概要
私はスウェーデンの大学であるリンシェーピン大学のサマープログラムに参加した。リンシェーピン大学はエンジニアリングやコンピュータサイエンス、医療の分野で特に高く評価されており、また世界中から多くの留学生が集まり、多文化環境が整っていることからも留学するには最適の大学である。リンシェーピン大学のサマープログラムは様々なコースの中から一つの授業を選び、約三週間にわたって授業を受講することで知性の習得を目指すプログラムである。私は”High tech meets people meets processes quality improvement in healthcare”という授業を選択し、医療の発展と技術の関連を様々な視点から考察した。
また、サマープログラムでは授業の他にも留学生に向けていくつかの課外活動が開催されており、その中で他の留学生たちとの交流を深め、またスウェーデンの文化や自然の特色について学んだ。
日程
リンシェーピン大学のサマープログラムでは、基本的に平日は授業があり休日は休みということが多かった。また、課外活動がほとんど毎日開催されており、私は積極的に参加した。空き時間には他のサマープログラム留学生と国際交流を行ったり、買い物や自室で作業をしていたりすることが多かった。
プログラムに参加する目的
私が留学を希望した動機は大きく分けて二つあった。
一つ目は、異なる文化を持つ人々と共に勉強することで異文化理解や国際的な視野を獲得することが出来ると考えたからだ。多様なバックグラウンドを持つ学生やスウェーデンならではの授業を通じて異なる考え方や問題を解決するアプローチを学ぶことで、柔軟な思考を養い、これにより将来グローバルな課題に対しても取り組むことが出来るようになることを目的としていた。その点で世界各国から生徒が集まり一つの場所で勉強する枠組みが出来ているリンシェーピン大学は私にとって留学先として非常に合っている大学だったといえる。
二つ目は自己成長としての機会を留学で得たかったからだ。留学生活は言語や生活様式、文化、教育システムなど多くの面が日本とは異なり数多くの挑戦が伴うことが予想され、これらを克服する過程で得られる自己成長が今後新しい環境や見慣れない問題などを解決するにあたって大いに役立つことになると考えた。
活動の内容

ストックホルム
はじめに学業面での活動を振り返る。私はサマープログラムで医療の発展と様々な技術の関連についての授業を受講した。具体的な授業の進行として、一回目の授業では講義形式の授業を行い、二回目の授業でそのテーマについてディスカッションを行うといった、二回の授業を一セットとして取り組むものであった。授業の基本としては対話が非常に重要視されており、講義形式の授業が行われている間も先生が頻繁に生徒に問いかけを行ったり、自身の考えをクラスメートと話し合う時間が与えられたりと対話をする機会が非常に多かった。また、生徒の自主性も非常に大事にしており、二回目のディスカッションの際には先生は一切口を挟まず生徒だけでディスカッションを完結させる方針であった。いくつかのグループに分かれたのち、何を話し合うか、テーマについての自身の考え、それに対する評価、そしてそこから新たなテーマを考える、といったディスカッションのループを時間の限り行い、最後には話し合った内容と出た結論を一枚のポスターに手書きでまとめ、他のグループに向けて発表するというような授業形式であった。
総じてまとめると、スウェーデンの授業は対話を行うことと生徒の自主性を尊重することを非常に重要視していることがわかる授業であったといえる。日本の大学では講義形式で先生が生徒にただ話をするだけといった授業が多く、私はこのような対話が尊重される授業を受けたことがなかったため非常に新鮮な経験であった。実を言うと、サマープログラムの初めの期間は授業方式に慣れず、そこで積極的に発言するクラスメートに圧倒されてしまったが授業を重ねるにつれて発言が出来るようになり最終的には自分の考えをはっきりと伝えることが出来るようになれたと思える。
具体的な講義内容に関しては医療が抱える様々な課題について知識を深めディスカッションで解決を探ることで医療の質の改善を目指した。例えば訪問診療の質の低下という課題への解決を目指してディスカッションをした。その他にも、慢性的な病気を持つ患者への診療、病院内での衛生管理の低下による感染症の発生など様々な問題が議題にあげられ、それらをどう解決することが出来るかについて知識を深めそれぞれの考えを共有し合った。この授業ではそれぞれの生徒が異なる国からきているので、国の医療制度など病院や病気に対する考え方などが違っているため、多様性のある意見が飛び交っており視野を広げるという点では非常に興味深いものだった。特に印象深かったのは、ヨーロッパの国々と中国の医療制度の違いだろうか。ヨーロッパの人々は欧州健康保険証という保険証が配られ、多くの地域で地元の人々と同じように保険適用で診療を受けることが出来るのに対して、中国では住む地域によって所謂かかりつけ病院が定められており、それ以外の場所で保険適用の診療を受けるにはたとえ中国国内であっても紹介状などの手続きが必要という制度の違いだ。最初はお互い自国の制度が当たり前で当然他の国もそうであると思っていたのだが、ディスカッションを進めるにつれていくつかすれ違いが起こり、その結果このような制度の違いがあることが明らかになったので非常に驚いたことを覚えている。また、他にも多様性が現れた理由としてお互い自身の大学での専攻が異なっていることも挙げられるだろう。医療の質についての授業であったが、それぞれの大学での専攻が電気電子工学、機械工学、生物工学、情報工学、経済学、経営学など多岐にわたっており、中には大学では作曲を学んでいるという人や、社会人を経験して大学院に入学した人、看護師の学校に通っていて今は実習期間中という人もいた。ディスカッションの中でもこのバックグラウンドは顕著に表れており、例えば情報工学のクラスメートはAIから課題の解決を図ろうとしたり、経営学のクラスメートは病院のチーム体系を改善することでより効率的な医療の提供を実現しようとしたり、それに対して社会人を経験したクラスメートや看護師実習中のクラスメートは実際に現場を経験した人ならではの知識でサポートするなどしており、結果的には何でもありの自由なディスカッションとなった。このように多様なバックグラウンドを持つ人々が集まり、意見を交わすというのは対話と生徒の自主性が尊重される教育方針ならではのものであり、非常に価値のある経験であった。
次に、国際交流など授業以外での活動を振り返る。まず、サマープログラムでの課外活動の参加についてだ。サマープログラム中はほとんど毎日課外活動が開催されており、私は積極的に参加して他の留学生と国際交流を行っていた。課外活動の内容について、例えばスウェーデンの文化やスウェーデン語について学んだり、自然公園やその他スウェーデンの特色が色濃く表れている場所へ行ったり、またはフットボールやクイズ大会などで留学生との絆を深めたり、などと多岐にわたっていた。これらの課外活動に参加することでスウェーデンについて学び、他の留学生との国際交流を行うことで自身の視野を広げることが出来たように思える。
最後に、サマープログラムの枠組みの外つまりプライベートでの活動を振り返る。私たちは大学の寮の一室を与えられてそこで生活を行っていたので、スウェーデンでの実際の生活を経験することが出来たと考える。例えば、寮の周りに飲食店があまりないこともあり基本的に私は自炊をして生活していたのだが、スーパーに行き実際に食べ物の値段を見て購入し、それを寮の共用キッチンで共用のスパイスを使いながら料理するという一連の流れでスウェーデンの物価や食生活について学ぶことが出来た。個人的に印象深かったのはスーパーの野菜や果物売り場は日本のように一個当たりの値段ではなく購入する重さから値段が決まる量り売り方式で売っていたところだ。はじめは非常に驚いたが、慣れてくるにつれてこちらの方が公平なのではないかと思うようになった。また、スウェーデンのスーパーはプラスチックがあまり使われておらず、また上述した野菜やフルーツの量り売りも紙袋に入れて行い、またその紙袋には”この紙袋は捨てずに何度も利用してください”と書いていることからスウェーデンは環境に配慮し、自然と共に生きていく国なんだなという風に実感できた。このような小さいことからの発見は実際に現地での生活を体験しているからこそのものであり、非常に有意義なものだったと思える。
もう一つプライベートの活動について、私は自由な時間が出来たときは出来る限り他の国の留学生と関わり、国際交流を行っていた。日本からの留学生は私を含めて三人しかおらずはじめは心細かったが、積極的に話しかけることで他の国の留学生とも仲良くなることが出来、最終的には友達として一緒に遊びに行ったりご飯を食べたりするようになった。中でも記憶に残っているのは留学生二十人で集まって一緒に夜ご飯を作りパーティーをしたことである。この日は中国の留学生が多かったため中国料理を作り、他の国の留学生はそれを手伝いながらみんなで夜ご飯を作った。この一連のパーティーで私は他の留学生と仲間になることが出来たような実感が湧き、非常に嬉しく感じたことを覚えている。以下にこの時に撮影した集合写真を示す。彼らとは他にも一緒にストックホルムに出かけて散策したり、湖に行き泳いだりと非常に楽しく充実した時間を過ごすことが出来た。
プログラムの参加により、どのような能力を育成できたか
このプログラムを通して私は様々な成長を達成することが出来たと自負しているがその中でも特に大きな成長を二つ挙げようと思う。
一つ目は、積極的な人間になることが出来たという点だ。一般的に日本人はシャイだといわれることが多いが、プログラム開始時は私もその例に漏れず他の留学生に話しかけたり、授業中に発言したりすることが出来なかった。しかし、周りの留学生が私に話しかけてくれ、また授業中に積極的に発言している姿を見ることで徐々に自発的に行動し気恥ずかしさを克服することで、最終的には自身から積極的に動くことが出来るようになった。恥ずかしさや失敗への恐怖から何もやらないよりも、当たって砕けろの精神で色々なことにチャレンジしたいと思えるような心持ちを備えることが出来た。
二つ目は、世界には色々な人がいると理解できたことだ。もちろん留学前も世界には多くの人がいることは知識として知っていたが、実際にサマープログラムに参加してバックグラウンドが違う人と関わり生活することで本当の意味で知ることが出来たと考える。世界には色々な人がいて文化や考え方が異なるということを実感できた。その逆にバックグラウンドが違っていても考え方や抱えている課題が共通する部分もあり、当たり前のことだがバックグラウンドが異なっているからといって何もかも異なっているわけではなく同じ人間であることを肌で感じることが出来たのは非常に有益であった。
その他所感
このプログラムに参加する中で、私は日本人であることに非常に助けられたと感じた。上述したようにサマープログラムの開始時私は英語で会話することに対する苦手意識もあり、恥ずかしいことに積極的なコミュニケーションを取ることが出来ず、勇気を振り絞って話しかけても何を話せばいいかわからないという状態だった。普通ならばそんな人間悪印象間違いなしの状況なのだが、私が出身を聞かれて”Japan”と答えるとほとんどの人が明るい顔でで”日本っていい国だよね”,”日本好きなんだ”など非常に良いイメージを持っていることを語ってくれ、加えて”この前日本行ったんだ”,”今度の〇月日本に行く予定なんだ”など実際に日本に訪れる人も多かった。ほとんどの人が”ありがとう”、”こんにちは”などの簡単な日本語の単語を知っており、中には日本語を勉強していて私と日本語で会話できる人までもいた。私はサマープログラムに参加する前まで日本という国は他の国の人々からしたら名前は聞いたことのある国くらいのイメージでしかないと思っていたのだが、実際には多くの人が日本のことを知っておりさらに良いイメージを持ってくれていたため非常に驚くのと同時に、これは今まで日本の先人方が一つ一つ行動を積み重ねた結果であり私もそれに恥じないような行動をしていきたいと強く思った。