社会連携
社会連携

「科学技術の新たな可能性を掘り起こし、社会との対話の中で新時代を切り拓く」ことを掲げて、指定国立大学法人の東京工業大学は「世界最高の理工系総合大学」を実現させるべく、教育、研究、ガバナンス改革を着実に進めています。
そのためには財政基盤の強化が不可欠であり、その要となるのが創立130周年を機に創設された東工大基金です。寄附によって構成される基金は奨学金の充実、教育や研究環境の整備など、さまざまな分野で有効に活用されています。
東工大基金は大学運営の4つの柱である「教育」「研究」「社会連携」「国際交流」の各分野で活用されています。たとえば、「教育」では奨学金の創設、「研究」では世界トップレベルとなる研究支援、「社会連携」では小中高生の理科教育の振興支援、「国際交流」では海外派遣といった支援活動が行われています。東工大基金のサポートを受けてさまざまな活動や研究に積極的に取り組む研究者や学生の声を紹介します。


教育
奨学金
大隅良典記念奨学金
別木智也さん(第1類 学士課程1年)
もともと物理や数学に興味があり、理工系に特化してグローバルに活動している本学に魅力を感じ、地元の島根県から進学を決めました。大学の講義は今まで気にも留めていなかった細かな部分まで詳しく学ぶことができ、より一層関心が深まりましたし、周囲の仲間といろいろな問題に対して質問し合うことでも理解を深められています。世間の東工大に対するイメージとは逆に社交的な人が多く、話し合いも活発です。講義に関してはやや難しいと感じる教科もありますが、それこそが学ぶ意義であり、東工大の良いところだと思います。

研究
若手研究者支援
「東工大の星」支援【STAR】
前田和彦准教授(理学院 化学系)
中学や高校の理科で習う水の電気分解では、適当な電極を電解質溶液に浸して両極間に電圧をかけることで水を水素と酸素に分解します。この反応の本質は、電気エネルギーを化学エネルギー(水素)に変換していることです。ここで、電極となる物質の選び方次第では、電気エネルギーを使わずに光のエネルギーだけで水を分解することや、二酸化炭素を炭化水素などの有用資源物質に変換することもできます。こうした光エネルギー変換反応に使われる物質は光触媒と呼ばれ、その主役となるのが無機あるいは有機の固体材料です。私はこれに興味を持ち、特に太陽光の大部分を占める可視光を有効利用できる光触媒の研究を15年以上続けています。特に、まだ誰にも知られていない未知の化合物を新たに合成してそれを光触媒として使用するほか、固体と分子の融合材料など、これまでにない光触媒システムの構築に取り組んでいます。
光触媒は学際的な研究分野ですが、10年ほど前までは他の分野との交流がほとんどないような状況でした。しかし、昨今は異分野融合が進み、光触媒の研究が大きく発展しています。私の研究で言えば、錯体化学や固体物理の研究者との連携によって数多くの成果を生み出すことができています。異分野同士の境界領域は新しいアイデアが次々と生まれるホットスポットです。
「東工大の星」支援【STAR】の採択を受けて、より自由な発想で研究に取り組めるという、ある種の安心感を得ることができました。通常の競争的資金と違って、ひらめきやアイデアをいつでも検証できるということは研究者にとって大変ありがたいことです。
今後も研究をさらに発展させていきたいと考えています。
研究者詳細情報(STAR Search) - 前田和彦 Kazuhiko Maeda![]()

教育・社会貢献
理科教育振興支援
腸内環境の全容解明と産業応用(JCHM)
千葉のどかさん(生命理工学院 生命理工学系 学士課程3年)
研究室でヒト腸内細菌と疾患の関係性などを学んでいます。学士課程1年の時に、腸内環境に関する研究と活動を知り、研究に必要な知識の習得と経験を積むため、まずは腸内細菌のことを伝えるアウトリーチ活動に参画することになりました。そのおかげで日頃サイエンスに親しみがない人にもサイエンスの面白さを伝える楽しさを感じており、この活動は続けていきたいと考えています。
将来の夢は病気や不健康を各人で予防できるような社会を作ることです。たとえば、それぞれのライフスタイルに合った食生活や運動習慣などをアドバイスできるツールが作れないかと考えています。東工大で学んだ科学の知識や有用性をそのツールに反映させたいです。
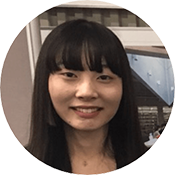
教育・社会貢献
理科教育振興支援
腸内環境の全容解明と産業応用(JCHM)
鈴木実乃里さん(生命理工学院 生命理工学系 学士課程2年)
JCHMの学生メンバーとともに小学生に向けたアウトリーチ活動を行なっています。主にボードゲーム「バクテロイゴ」を使って小学生に遊びながら腸内細菌を学んでもらう活動や、夏休みに国立科学博物館で開催される「サイエンススクエア」に参加し、独自のボードゲームや歌などを通して腸内細菌の大切さを伝える活動を実施しています。表現方法はいろいろで、アプリゲームを開発する学生もいますが、私は趣味の読書を生かして腸内細菌を題材とした物語や劇の脚本を書いています。
将来は研究職に就きたいと思っています。興味があるのは精神医学で、医師ではなく研究者という立場で精神医学の“これから”に関わっていきたいです。

国際交流
短期派遣プログラム
グローバル理工人育成コース
劉依蒙さん(物質理工学院 応用化学系 修士課程2年)
指先の摩擦現象と人間の触覚との相関性について研究しています。スマートデバイスを操作するとき、指先には摩擦と同時にさまざまな触覚が発生します。そこで、触覚に影響する因子を解明できれば、触覚の制御による操作性向上や新機能の実現が期待できます。
中国で高校卒業後、専門知識と国際的素養の両方の習得を目的に東工大への進学を決めました。グローバル理工人育成コースの留学プログラムのおかげで短期留学する機会を得て、学生同士の交流も深めることができました。印象に残っているのは修士1年のときに行ったオックスフォード大学です。ほぼ毎日を研究室で過ごし、隣接する研究室と合同で行われるランチタイムでは、穏やかな雰囲気で研究の進捗に関して議論を楽しみながら、世界各国のスナック菓子を交換するなど、英語の習得と異文化を学ぶ貴重な経験となりました。
修士課程修了後は日本の自動車メーカーに就職する予定です。大学での研究を生かして、将来は触り心地や居心地に優れた自動車の内装の設計開発に取り組みたいと思います。

国際交流
短期派遣プログラム
グローバル理工人育成コース
釜坂みおさん(工学部 高分子工学科 学士課程4年)
語学の強化や留学への興味からグローバル理工人育成コースを選択し、これにより価値観や夢が大きく変わりました。特に印象深いのは3年次に米国ライス大学へ留学したことです。5週間の研究プログラムを通して研究の面白さや難しさを実感するとともに、企業や政府関係者との対話から研究以外の方法で科学技術に携わっていく道もあると考えるようになりました。また、留学生と参加する学内のサマープログラムでは「専門分野の探求よりも、社会や生活に繋がる話のほうが面白い」ことを実感しました。
将来は当然研究職に就くものと思っていたのですが、グローバル理工人育成コースでたくさんの刺激を受けたことで、人々に役立つ多様な道があることを知りました。卒業後は世界中の科学技術を社会に役立てている総合商社に勤務し、グローバル理工人の一人として地球を飛び回ろうと思っています。
肩書、所属、学年は2019年3月時点の情報です。
東工大基金は、学生寮の整備にも利用されています。日本人学生と留学生が混住する「緑が丘ハウス」での生活は、まさに異文化体験の場。様々な国の文化や多様な価値観に触れて、相互に学び合える環境を整えています。
また、基金は子どもを持つ研究者や学生が安心して研究や教育に励めるよう、保育園の整備にも使われています。外国から招いた研究者や留学生の中には家族連れで来日する人も少なくなく、このようなきめ細かなサポートに基金が使われています。

学内保育所「てくてく保育園」

留学生と日本人学生の混住型の学生寮「緑が丘ハウス」
世界中どこにいても時間を気にせず利用できるのが東工大オンラインコミュニティの特徴です。在学中は同級生や研究室の仲間、先生たちと当たり前のように会いますが、卒業後は疎遠になりがちです。オンラインコミュニティに会員登録すると、公開情報から他の会員と連絡を取り合えるほか、掲示板を使った情報発信や情報共有が可能になります。
また、世界各地の同窓生グループ13拠点とオンラインコミュニティ事務局は定期的に連絡を取っています。コミュニティのネットワークがグローバルに広がることで、東工大の発展を支える力がさらに強化されます。オンラインコミュニティを通じて、仲間との交流を楽しみませんか。
2019年4月掲載