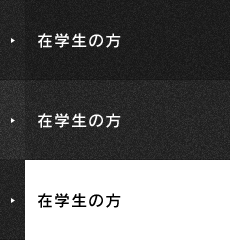Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) 香港科技大学 2023年1月~5月

留学時の学年: |
修士2年 |
|---|---|
所属: |
物質理工学院 材料系 |
留学先国: |
中国(香港) |
留学先大学: |
香港科技大学 |
留学期間: |
2023年1月18日 ~2023年5月5日 |
プログラム名: |
派遣大学の概要
香港科技大学は1991年に創設された香港の公立大学である。創立50年以内の大学を対象とした「Young University Rankings」では毎年上位に位置しており、最新のYoung University Rankings2022では3位にランクインしている。理学・工学系の学科が充実しているが、CSやMBAも有名である。約1万人の学生が在籍しており、欧米系の学生も多く見かける。しかし、アジア系の学生が圧倒的に多く、特に香港出身者よりも中国本土出身者が多いのが特徴である。
留学準備
<研究室、研究テーマ>
香港科技大学には、私自身そして指導教員にも面識のある先生がいなかったので、大学のホームページで興味のある研究を行っている研究室を調べた。興味を持った研究室が実験・計算を両方とも行っている研究室だったため、留学決定後すぐに先方の教授にメールをし、私の専門である計算系の学生を紹介してもらった。学生とのやりとりの中で、私が参加できそうな幾つかのプロジェクトの概要や関連する論文を紹介してもらい、最終的な研究テーマは留学開始後に決定した。
<寮>
留学開始の2ヶ月程前に先方の事務の方から入寮に関する案内をもらい、それに従って手続きを進めた。
<学生登録>
香港科技大学のオンラインフォームに入力する形で手続きを進めた。パスポート、成績証明書、Institution Support Form(東工大での所属や留学プログラム責任者のサイン等を記載した書類)、英語試験の成績証明書、保険加入の証明書、ワクチン接種証明書をアップロードする必要があった。
<ビザ>
成績証明書、パスポートのコピー、ビザ申請書、銀行の残高証明書の4点を先方の大学に郵送した。書類に不備がなかった場合でもビザ発行まで8週間程度かかるので早めに準備を進めると良い。
研究概要
コンピュータによる計算・シミュレーションを用いて、燃料電池の負極における水素酸化反応(HOR)用触媒材料の研究を行った。現在、燃料電池の負極用触媒には主にPtが使われているが、価格・産出量などの観点からPt使用量の削減、もしくは代替材料の開発が求められている。また、燃料電池においては正極側での酸素還元反応(ORR)が全体反応の律速段階となっていることから、ORRの方が盛んに研究されているのが現状である。今回は、留学先の研究室の実験グループから提案された新たなHOR用触媒材料に関して、第一原理計算による反応メカニズムの解明を目指した。公表前であるため、具体的な成果の記載は控える。
研究室内外での活動・体験
基本的に平日は研究室にて研究、休日は遊びに行くという生活を繰り返していた。寮、スーパー、食堂、理髪店等キャンパス内に全て揃っているので、大学の外に出なくても生活はできる。私が滞在していた寮にはキッチンがなかったため、朝はプロテインとバナナ、昼は食堂、夜はパックご飯とカレーをレンチンするというルーティーンだった。食堂は複数あり、1食あたりおよそ30HKD~(500円~)と、日本と同程度の価格帯に感じた。メニューに関しては、中華料理はもちろん、東南アジア系、洋食、日本食と種類が豊富である。ただし、なぜか野菜は必ず茹でられているため、生野菜を食べたくなったらイオンでカット野菜を買うと良い。イオンかドンキ(香港ではドンキホーテではなくドンドンドンキという)に行けば日本のものは大抵手に入るので便利である。
※写真の日本食カウンターではラーメンを注文できるのだが、Miso ramenを頼むとMiso soupをラーメンのスープに使った味噌汁ラーメンが出てくるので、これだけは食べてはいけない。
大学は郊外にあったため、街に出る際はバスやMTR(地下鉄)を使う必要がある。尖沙咀や旺角などのダウンタウンまでの所要時間は40~50分程である。香港では、交通機関の運賃は日本と比べるとかなり安いため、200円程度で中心部まで出ることができる(大学↔︎ダウンタウンは、すずかけ台↔︎みなとみらいのようなイメージで差し支えない)。香港は国土が小さいため、3~4ヶ月あれば定番の観光地は全て回れるはずである。特に100万ドルの夜景はド定番の観光地だが、その美しさは期待以上だった。写真では伝えきれないので、この体験談を読んでくれている人、留学せずとも旅行でいいので一度行ってみてほしい。
また、中国人のラボメイトに誘われて中国の深圳に行ったのだが、ぜひこちらにも行ってみることをオススメする。Simカードのキャッチがしつこかったり、バイクがヘルメットなしで歩道に突っ込んできたり(なぜか合法)、地下鉄に乗るときいつも荷物検査があったりと、これでもかというほど価値観の違いを感じられる場所だと思う。
-

ドンドンドンキ
-

日本食カウンター
-

100万ドルの夜景
留学先での住居
キャンパス内にある寮”SKCC Hall”に滞在した。寮はいくつかあるが、先方から指定され、案内に従って手続きを進めた。現地の学生からは「新しい寮だね」のようなことをよく言われたが、(ボロボロではないが)そこまで新しいとは感じられなかった。日本の築10年くらいのアパートといった感じである。何度か火災報知器が誤作動を起こしたため、突然ジリリリと鳴り出すのに慣れてしまった(よくないことだが)。共有部には冷蔵庫+冷凍庫、電子レンジ、シンクがあり、自由に使える。大学院生は基本的に1人部屋になるようである。部屋の設備はベッド、クローゼット、エアコン(冷房機能のみ)、冷蔵庫、作業用デスクという最低限のものだが、短期間の留学生活を送るには十分である。運が良ければオーシャンビューの部屋に住める。
※寮が決まったら、まず備品の確認をすること。SKCC Hallの寝具はマットレス、シーツのみが備え付けであり、毛布がなかった。いくら香港でも1月の夜は寒い。私は毛布を持っていかなかったため持ってきた服にくるまって寝ていたが、安眠できるほどの温もりは得られなかった。渡航前に先方に確認しておくと良いだろう。
留学費用
●渡航費:12万円(往復)
●生活費:3~4万円/月
●住居費:40万円
●保険料:4万円(日本)、1万7千円(香港)
●登録料:1万円
住居費は191HKD/泊で今回の留学期間3ヶ月半分を円換算している。SKCC Hallの場合、電気代、水道代はここに含まれるが、エアコンを使う場合は1HKD/分の別料金がかかる。また、洗濯は9HKD/回、乾燥機は1HKD/5分である。
今回の留学から得られたもの、後輩へのメッセージ、感想、意見、要望
短い期間ではあったが、海外で、1人で、普段と違う研究に取り組めたことは自信になった。慣れない環境の中で成果を上げるため、留学中は次の2点を意識していた。
1.週に一度は必ずメンターの大学院生とディスカッションを行い、結果・問題点を共有し、その先1週間の方向性を確認する。
2.異なるテーマで研究をしている研究室の同僚とも雑談し、周辺知識を習得する。
1.に関しては、普段の日本での研究よりもかなり早いペースである。期間が限られているというプレッシャーもあったが、自分のやるべきことが常に明確となり、研究の進捗に大きく寄与したと考えている。2.については、テーマの細かな違いはあっても、同じ研究室であれば共通する部分も多い。例えば、私は触媒材料の中でも特に燃料電池の負極用触媒の研究を行っていたが、正極材料の研究を行っている人や私とは異なる材料で負極材料の研究を行っている人もいた。彼らは私より長くこの分野に携わっているため、論文の内容を解説してくれたりもした。また、逆に私の研究について説明することもあり、自分の理解を整理することができた。の研究留学を通して材料に関する知識、研究手法の習得という専門的な部分で新たな学びを得ることができたのはもちろんのこと、研究への取り組み方という点でこれらの経験が今後の研究のための大きなバックボーンになると考えている。
また、英語力に関して今回その必要性をさらに痛感した。留学先の研究室の教授の発音にはネイティブにはない癖があり、聞き取りに苦労した。その場で聞き返したり研究室の他の学生に確認したりして大事には至らなかったが、スムーズに聞き取ることができた方がコミュニケーションが円滑に進む。また、研究者は非英語圏出身者も多いため全員がネイティブ並みの発音をしてくれるとは限らない。どのような相手であっても英語で的確にコミュニケーションをとることは今後の研究生活に重要な要素だと感じた。
最後に、私の反省点を踏まえ、今後香港留学を目指す人に向けてのアドバイスを送る。
●渡航時期
香港に限らず、中華の大学に行く場合は春節直前の渡航は避けるべきである。春節期間に入ると大学の事務が閉まってしまい、手続きに支障が出る。私は春節休みに入る3日程前に渡航したため、学生登録や学生証の受け取りが完了したのは春節明け(渡航してから1~2週間後)だった。
●Octopus
香港生活はOctopusに始まり、Octopusに終わるといっても過言ではない。Octopusは香港全土で使えるICカードで、普及率は90%を超えている。レストラン、スーパー、コンビニなど香港内ほぼ全ての施設および公共交通機関の支払いに対応している。特に大学の学食はOctopusで食券を購入するのが最もスムーズである(現金、クレジットカード払いのできる窓口もあるが、しばしば係員が不在)。Octopusは大学内では買えず、MTRの駅で購入する必要があるため、空港に着いたらまずOctopusを手に入れるべくMTRのカスタマーセンターを目指そう。
●言語
広東語、もしくは北京語の勉強をしておくと良い。香港の公用語は広東語・英語となっているが、コミュニケーションに使われるのはもっぱら広東語もしくは北京語(中国本土出身者が多いため)である。基本的に研究室内では英語で全て完結するが、食堂や寮のスタッフさんの中には英語が通じない人もいる。香港全体では、若い人には通じるが、それ以外の人には通じないと思っておいた方が良い。簡単な日常会話、数字などは分かるようにしておくと、勉強しておいて良かったと思える日が来るだろう(というより、そんな日の連続かもしれない)。
細かな反省点はまだまだあるが、以上の3点を頭に入れておけばあとはなんとかなるだろう。留学に行くと、日本では想像できなかったトラブルに巻き込まれることもあるかもしれない。留学に来たことを後悔することもあるかもしれない。しかし、そんな困難な状況さえも楽しもうという気概を持って臨むことが留学を成功させる秘訣である。Good luck!
●その他
WeChat(メッセージアプリ)のアカウントが凍結されるというトラブルに見舞われた凍結
理由は不明だが、初期にランダムに割り振られるIDを変更しなかったり、性別や身分などの詳細情報を未登録のままにしておくと凍結される可能性があるらしい。なお、このアプリ上でやり取りされる内容は全て中国政府による検閲対象であり、政府を批判するようなメッセージが検出された場合も凍結される(私は断じてそのようなことはしていない)。研究室内の連絡はWeChatを通して行われるため、このアプリが使えないのは研究に支障が出るのだが、中国人のラボメイトにお願いしてカスタマーサポートに連絡してもらうなどしたが解決しなかった。再登録には新たな電話番号を取得するしかないのだが、費用や契約期間等の条件に合うsimを探すのに苦労した。当初は英語で調べていてなかなか見つからなかったが、日本語で検索してみるとなんと日系の会社を発見。最後に頼れるのは日本語である。無事に新たな番号を取得することができ、WeChatも帰国まで問題なく使うことができた。ちなみに、香港では日本人学生を除き、LINEを使っている人はほぼいなかった。
参考までに私が使った日系の会社のURLを載せておく。
この体験談の留学・国際経験プログラム情報
他の関連する体験談
-

(Asia-Oceania Top University League on Engineering) AOTULE マラヤ大学 2023年9月~11月
- マレーシア
- マラヤ大学
- 2023年09月04日~2023年11月26日
- 研究
-
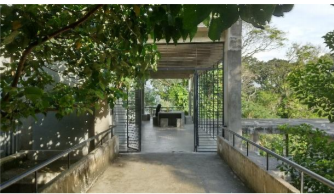
Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) モラトゥワ大学 2019年12月~2020年3月
- スリランカ
- モラトゥワ大学
- 2019年12月~2020年3月
- 研究
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) チュラロンコン大学 2016年9月~11月
- タイ王国
- チュラロンコン大学
- 2016年9月~11月
- 研究
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) 南洋理工大学 2018年6月~9月
- シンガポール共和国
- 南洋理工大学
- 2018年6月~9月
- 研究
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) 韓国科学技術院(KAIST) 2016年10月~12月
- 大韓民国
- 韓国科学技術院(KAIST)
- 2016年10月~12月
- 研究
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) バンドン工科大学 2018年8月
- AOTULE 加盟大学への短期派遣プログラム
- バンドン工科大学
- 2018年8月
- 国際交流・異文化体験、語学、授業履修
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) 国立台湾大学 2019年12月~2020年2月
- 台湾
- 国立台湾大学
- 2019年12月~2020年2月
- 研究
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) 清華大学 2019年7月~9月
- 中華人民共和国
- 清華大学
- 2019年7月~9月
- 研究