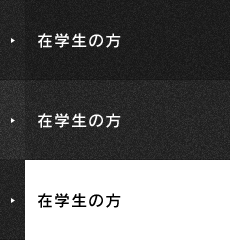(Asia-Oceania Top University League on Engineering) AOTULE マラヤ大学 2023年9月~11月
留学時の学年: |
修士2年 |
|---|---|
所属: |
環境・社会理工学 |
留学先国: |
マレーシア |
留学先大学: |
マラヤ大学 |
留学期間: |
2023年09月04日~2023年11月26日 |
プログラム名: |
派遣大学の概要(所在地、創立年、規模など)

マラヤ大学 校章
マラヤ大学は1905年にクアラルンプールにマレーシア初の大学として設立された公立大学。マレーシア随一の最高学府で2023年度のQS世界大学ランキングでは世界第65位の評価を受けている。クアラルンプール中心地にありながらその面積は3.73k㎡におよび、東京ドーム79個分、面積約0.46k㎡の東工大約8個分にもなる巨大なキャンパスを持つ。フルサイズのサッカーコートは確認できただけでも6面あった。
留学準備など
【海外で研究生活がしてみたい】
正直に言えば特別マレーシアに行きたかったわけではなく、とにかく海外で研究生活がしてみたかったという理由で留学を志望したため、ある程度研究テーマを決めた後はマラヤ大学、AOTULE加盟大学に限らずSERP加盟大学などの多くの大学の教授にメールを送った。その中で、特に自分がやりたい研究が実現できそうで、かつ許可が下りたマレーシアに行くことに決めた。教授によっては返信が1、2週間後ということも普通でいちいち待っていては時間を無駄にする可能性も大いにあるので、特にこだわりがないのであれば世界中の大学に大量にかつ早めにメールを送るに越したことはない。マラヤ大学の先生に許可を頂いた後はより詳細な研究計画書を送り、研究内容を協議した。AOTULEでは基本的に東工大で普段行っている研究とは関係ない研究を留学先で行ことになるため、その分野に関する知識が不足している場合も多く、計画を練る段階から数冊の関連書籍を読んで勉強はしていた。
【奨学金等】
また、AOTULEで留学する場合、奨学金をもらうとなると基本的にJASSOの給付型奨学金を申し込むことになるが、私の場合はそれ以上に貰うことができ、かつ奨学金という枠にとどまらず受給生同士のコミュニティがあるトビタテに申し込むため、その準備も行った。留学は9月からであったが最初の書類締め切りが2月上旬であったため、教授へのアポは当然それより早く(前年の9-11月くらい)から行っていた。さらに、6月ごろに東工大の面接もあるためそれも準備しなければならなかった。しかし、一度計画を作ってしまえば使いまわすことができ、かつブラッシュアップされていき、より充実した留学にするための準備だと思えば苦ではなかった。正式にトビタテの奨学金、東工大、マラヤ大学からの留学許可が下りた後は基本的に東工大の担当部署の方々の指示に従って準備を進めた。スーツケース、海外旅行保険、パスポートは特に高くついた。寮探しは不動産サイトから探すという手段もあったが、やり取りをするのが面倒であったためボタン一つで予約できるAirbnbから予約した。
所属研究室での研究概要とその経過や成果、課題など

TLS 本体

研究室の仲間
【研究概要】
留学先では教授の下、「岩盤斜面の非破壊検査機器を用いたハザード評価」というタイトルで研究を行った。岩盤斜面は常に崩落の危険にある。近年、そのハザード評価は非破壊検査装置を用いて行われるようになってきており、東工大にない機器を備えたマラヤ大学で非破壊検査装置の使い方や使い方を中心に学んだ。基本的には、岩石の斜面や岩石の性状を評価するための非破壊検査装置を実際に使って、使い方や仕組みを理解し、担当教授にそのプレゼンを行い議論をしたのち次の器械に進むという流れで進めた。 本来は岩盤現場を訪問し、機器を使って危険度を予測する予定だったが私の担当教授が行っている岩盤調査プロジェクトは、関係者以外は簡単にアクセスすることができず、実際に岩盤を訪れて調査を行うことはできなかった。それでも、実際に数種類の非破壊検査装置を使用し、その使い方や原理を習得することができた。岩盤だけでなくコンクリートにも使用できる器具が多かったため、主にコンクリートに対して使用した。来年4月より建設業界で働くことが決まっており、扱う機会も多くなるであろう将来に向けいい経験になった。以下に具体的な内容を示す。
【課題と経過】
最初の課題は、マレーシアと日本で土砂災害の危険リスクがどのように評価されているかを調査することだった。土砂災害には大きく分けてがけ崩れ、地滑り、土石流の三種類がある。マレーシアにおいてはその種類によらず斜面の高さ、角度、地質などの観点からリスクをスコア化するという手法が一般的である。対して日本は三種類それぞれに起こりやすい地形があることを利用し、地形図で危険な個所を特定したのち斜面と民家などへの距離などを測りながら丁寧に算出する。どちらにも一長一短があり、日本の方法は丁寧だが時間がかかりすぎるが、マレーシアの方法では簡単にできるがその精度は日本のに比べ低い。例えば、地形図判読でリスクが高い地域を日本の方法で特定したのち、マレーシア流のスコアシートを使う、など日本とマレーシアの方法を組み合わせれば精度を保ったまま効率を高めることができるかもしれないと感じた。
【成果】
その後、数種類の非破壊検査装置を実際に使い、使い方や原理を学んだ。具体的には、TLS(地上レーザースキャン)、ウォールスキャナー、鉄筋さび探知機、鉄筋探知機、Imapact Echo、UPV(超音波パルス速度)、リバウンドハンマー、GPR(地中レーダー)、AE(アコースティックエミッション)の9つの機器である。これらはコンクリートにのみ使える機器もあるが、岩盤を評価できるものも含まれ、使ってみてその精度や原理を学び、斜面崩壊のリスクを評価するのに非常に役立つことを実感した。特にTLSは盤斜面の破壊危険度を評価するために最も有効な器械の一つである。物体の空間的な位置情報を取得する計測装置でレーザー光線を対象物に当てて往復させ、距離や角度を測定する。1秒間に100万本以上のレーザービームが照射され、点群データとして測定結果が得られる。点群データは空間座標(x、y、z)で記録され、照射された物体の形状に関する正確なデータを提供する。このことは岩盤斜面など危険な場所のデータをそこに立ち入らずとも安全な位置から取得できることを意味し、岩盤斜面リスク評価に際し極めて有効な器械である。実際に装置を使う予定だったが、教授のスケジュールの都合でそれはかなわなかった。とはいえ、オンラインで実際の使い方の講習を受け、点群データを瞬時にかつ正確に取得できることを目の当たりにし、岩盤斜面の評価をより少ない時間と少ない人数でできることを学んだ。結論、実際の岩盤を見学することはできなかったが、岩盤斜面のハザードアセスメントに使用できる非破壊検査機器の原理や使い方を学ぶことができ、もともと自分で設定していた「岩盤斜面の非破壊検査による斜面崩壊危険度評価」というタイトルにふさわしい研究を行うことができた。英語でコミュニケーションをとらなければならない環境を含め、かけがえのない研究経験となった。
所属研究室内外の活動・体験(日常生活・余暇に行った事など)

学部の仲間とサッカー

インドネシア ボロブドゥール遺跡
【所属研究室内外の活動】
基本的には平日は学校、土日はマレーシア国内外を旅行した。平日は教授が10:30に来て16:30に帰るという日本では考えられないほどゆったりしていた。自分も基本的にはそれに合わせてだいたい10:00登校、17:00下校し、研究室で作業していた。部屋から学校までは45分程度で電車とバスで通学していた。交通費がとにかく安く、電車は7駅ほど乗って¥90程度、バスは1.5kmほど乗って¥30程度だった。キャンパスが広いだけあって最寄駅から研究室までが遠かった。食生活に関してランチは毎回¥300程度で学食で食べていた。学食は安価でかつ充実していた。夜ご飯は住んでいたコンドミニアムの下にあるレストランでインド系料理であるナシカンダーをこちらもまた¥300程度で食べていた。ナシカンダーはビュッフェのようなもので栄養バランスをとるのに最適だった。朝ごはんは自炊というほどではないが、白米を炊いて輸入で日本の3倍程度する納豆と、野菜サラダを食べていた。おやつなどを含めても一日¥1000程度で自炊をした方が高くつくくらいであった。また、週に一回、学部の仲間とサッカーをし、週に二回、知人が住むコンドミニアムのジムに通い汗を流した。
【週末は旅行へ】
週末は旅行に行った。高速バスは東京-名古屋間ほどの距離があっても¥1200程度だったため、バスで行きやすい場所に行く際に利用した。具体的には様々な宗教が混在するペナン島、マラッカ、チキンライスとホワイトコーヒーで有名なイポー、美しい茶畑のあるキャメロンハイランドに訪れた。またクアラルンプール国際空港からはLCCのエアアジアが多くの都市に就航しており、格安のチケットを見つけてボルネオ島や国外に訪れた。具体的にはボルネオ島の富士山よりも高いキナバル山を有するキナバル国立公園、巨大洞窟を持つグヌンムル国立公園の二つの世界遺産、半島側ではマングローブで知られるランカウイ島、国外ではシンガポール、ブルネイ、カンボジア、モルディブ、スリランカ、インドネシアに行った。宿は毎回¥1000程度の安い宿をとったが特に不満は覚えなかった。宿と交通費をできる限り削ったのでこれだけ行っても旅費は¥300,000程度で収まった。食費、交通費の安さは東南アジア(シンガポール除く)留学の醍醐味である。
留学先での住居(寮、ホームステイ等)、申し込み方法、ルームメイトなど
最初はマラヤ大学構内にある寮に申し込んでいたが、ACがなく、Airbnbに掲載されていたAC付きの部屋が安かったため、そちらに決めた。Airb&bは長期滞在の場合長期滞在割引のようなものが適用されることも多く80日で¥80,000で済んだ。部屋はベッド、クローゼット、机、椅子が配置された簡素な部屋でキッチン、バストイレは共用だった。それらは4部屋の住人が使うのだが特に困ることはなかった。しかし、ほかの部屋の住人は学生ではなく、あいさつ程度の関係でしかなかった。
留学費用(渡航費、生活費、住居費、保険料)など
予算はトビタテから頂いた¥510,000と自身の貯金からの合計¥650,000程度。渡航費は羽田クアラルンプール往復約¥70,000、住居・光熱費は¥80,000、食費、交通費等の生活費は一日平均¥1200程度で計約¥100,000、保険料は大学指定のもので約¥30,000、パスポート約¥15,000、スーツケース約¥20,000でそれらを差し引いた、約¥300,000と少しを余暇にあてた。
今回の留学から得られたもの、後輩へのメッセージ、感想、意見、要望
【環境を変えてみたかった】
そもそも留学に行こうと思ったのは環境を単純に変えてみたかったからというのが最大の理由である。これまでずっと実家に暮らし、海外に行ったのも15年以上前の家族旅行のみでずっと日本の狭い範囲で生きてきた。小中高大も言い方は悪いが似たような趣味・境遇を持つような友人とばかり付き合ってきて、インターネットでは自分が知りたい情報ばかりがカスタマイズされて表示され、環境に強く規定されてきた。それはもちろん居心地がよく悪いことではないのだが、東浩紀の言葉を借りれば「環境から統計的に予測されるだけの人生」になってしまうような気がしていた。そこでどこでもいいから海外に行きたいと思った。そうしてマレーシアやその周辺国に行き、環境を意図的に変えると日本にいたままでは決して興味がわかないようなことにも関心を持つことになる。
【環境の規定からはみ出し世界が広がる】
例えば、マレーシアは激辛料理が多く、それを中和するために飲み物が日本では考えられないくらい甘い、とか日本人は着ている私服が他人と被るとたいてい気まずさを感じるが旅先で出会ったスイス人曰く、スイス人はむしろうれしいと感じる人が多い、とか日本にいたままではまず検索もしないようなこと、ネットに載ってすらいないことを知ることができた。また、例えば横断歩道では車が止まること、トイレにウオシュレットやトイレットペーパーがあることは日本では当たり前だがマレーシアではそうではない。そのことを日本にいながらネットで知ったとしても何一つ周りの環境は変化しないが、海外生活で不便さを生身で感じると日本のよさを深く再認識することができた。環境の規定から少しでもはみ出し世界が広がったという感覚や「検索ワード」の変化、日本のよさの再発見。それらが最大の成果だったように思う。日本とは全く異なる文化の下、研究生活を送ることは必ず有意義になるのでぜひ少しでも興味があれば短い期間でも海外に渡ってほしいと思う。最後に、心よく送り出し、サポートしてくださった国際交流支援チーム、留学生交流課の皆様、先生方に深く感謝申し上げます。おかげさまで無事に充実した留学生活をおくることができました。ありがとうございました。
この体験談の留学・国際経験プログラム情報
他の関連する体験談
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) 香港科技大学 2023年1月~5月
- 中国(香港)
- 香港科技大学
- 2023年1月18日 ~2023年5月5日
- 研究
-
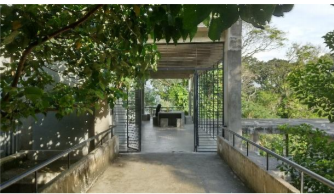
Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) モラトゥワ大学 2019年12月~2020年3月
- スリランカ
- モラトゥワ大学
- 2019年12月~2020年3月
- 研究
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) チュラロンコン大学 2016年9月~11月
- タイ王国
- チュラロンコン大学
- 2016年9月~11月
- 研究
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) 南洋理工大学 2018年6月~9月
- シンガポール共和国
- 南洋理工大学
- 2018年6月~9月
- 研究
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) 韓国科学技術院(KAIST) 2016年10月~12月
- 大韓民国
- 韓国科学技術院(KAIST)
- 2016年10月~12月
- 研究
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) バンドン工科大学 2018年8月
- AOTULE 加盟大学への短期派遣プログラム
- バンドン工科大学
- 2018年8月
- 国際交流・異文化体験、語学、授業履修
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) 国立台湾大学 2019年12月~2020年2月
- 台湾
- 国立台湾大学
- 2019年12月~2020年2月
- 研究
-

Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) 清華大学 2019年7月~9月
- 中華人民共和国
- 清華大学
- 2019年7月~9月
- 研究