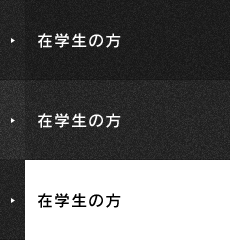派遣交換留学 ワシントン大学 2024年9月25日~2025年3月21日

留学時の学年: |
学士3年 |
|---|---|
所属: |
工学院情報通信系 |
留学先国: |
アメリカ合衆国 |
留学先大学: |
ワシントン大学 |
留学期間: |
2024年9月25日~2025年3月21日 |
プログラム名: |
留学先大学(期間)の概略
ワシントン大学はアメリカ・ワシントン州の最大都市であるシアトルに本キャンパスを構える総合大学であり、世界大学ランキングにも毎年100位以内にランクインする名門大学です。欧米地域だけでなく、アジア、アフリカ、オセアニアなど、文字通り世界中から学生や研究者が集まり、国際的な学究活動が盛んに行われる場となっています。
総合大学ということもあり、取れる授業の分野にほとんど制限がなく、演技や音楽といった普段学ぶことのない分野の授業も取ることができます。授業内容も独特で実践的なものが多く、歴史上の人物の選挙広告動画を協力して作る課題や、分析したデータを基にどの地域に食料雑貨店を建てればよいかを考察する課題など、内容を本質的に理解し、実際に応用する能力まで身に着く授業形式となっています。
学問以外にも人と交流する機会が豊富にあります。Dawg Dazeと呼ばれる新歓期間や季節ごとのイベント、自由に参加できるクラブ活動など、大学生活を充実させる活動が数多く行われています。アメリカの文化として、どの人種の人でも、どの国から来た人でも、英語を話している間は会話を盛り上げようとする雰囲気があります。そのため、グループワークやクラブ活動に参加すればすぐに仲の良い友達を作ることができます。

留学前の準備
学士課程で留学した場合
情報通信系では、3年次前期までに必修の専門科目をすべて取得し、研究プロジェクトを1Qに開講してもらい、その他の単位条件を満たしていれば、3年次の後期を丸ごと留学に使えるカリキュラムとなっています。4年次の後期に教養卒論、情報通信実験4,5を履修することで、卒業期間を遅らせることなく派遣交換留学を実現することが可能です。私は、2年次の10月頃から留学について調べ始め、12月上旬にTOEFL iBTを受験し、同月に締め切りとなる秋出発追加一次募集に出願しました。かなりギリギリの申し込みとなり、TOEFLの勉強も2、3週間ほどしかできませんでした。しかし、とりあえず今の自分の能力でできるところまでやってみて、そのまま流れに乗ってしまえば、「ここまで準備を進めてきたのだから」と、家族も納得してくれるだろうと考えていました。結果的に行きたい大学が見つかり、要件も満たしていたため、本格的に留学に踏み切ろうと決断しました。
出願と同時に留学奨学金の申し込みも進めました。留学の動機、取りたい授業とその理由、留学の結果を将来どのように活かせるか、などの事柄をまとめました。3年生になり留学が正式に決定してからは、住居探し、予防接種、航空券の予約、保険関係、ビザの申し込みなどの詳細な手続きを進めていきました。
留学中の勉学・研究
主に、専攻している情報系の授業と、教養として世界史の授業を取りました。
ウェブサイトを設計しデータを管理する授業や、データサイエンスを実社会で使う実演をする授業など、科学大では学ぶことのできない実践的な授業を履修しました。Web Programmingの授業の最終課題として、2人のペアとなり、家具販売サイトを作るプロジェクトを行いました。HTMLやCSSなどの言語を用いてウェブサイトの外観をデザインし、JavaScriptを用いてユーザがウェブサイトに干渉できるようにしました。また、Node.jsやSQLを用い、サーバ上でデータの保管・整理を行いました。結果として、商品検索、詳細閲覧、ユーザーログイン、商品購入、購入履歴の確認など、実際にインターネット上で見かける販売サイトとほぼ同等の機能を持つウェブサイトを作ることができました。Intermediate Data Programmingの授業では、Pythonというプログラミング言語を用いて統計的分析や画像処理といった実社会ですぐに使える実用的な技術を学びました。最終課題として、機械学習を用いて今年の男子大学バスケットボールの試合結果表を予測するプロジェクトを掲げ、3人のグループになって進めました。結果として今年の優勝チームであるフロリダを的中させ、その他の多くの試合結果の予測に成功しました。
歴史の授業として、ローマ帝国の歴史と中世世界の歴史を取りました。どちらの授業もただ史実や人物について学習するのではなく、当時の人が書いた文献を現代語に翻訳されたものを読んだり、複数の出土品を観察したりして、当時の様子を考察し、レポートにまとめるといった課題がほとんどでした。また、遺物自身になりきって自己紹介をするObject Autobiographyや、グループになり、カール大帝がフランク国王に相応しいことを説明する選挙広告動画を作る課題など、アメリカならではの踏み込んだ課題もありました。また、論文を読み、それについて考察したレポートを提出する課題が毎週出されたので、語彙力や表現力、そしてライティング力も非常に身に付きました。
以上のように、ワシントン大学では実践的で探究的な授業が多く、様々な分野の学生と有意義な議論ができる学習環境であったと思います。
留学中に行った勉学・研究以外の活動
留学生活の醍醐味は授業だけではありません。ハロウィン、感謝祭、クリスマス、旧正月など、季節の行事がある度にイベントが開かれ、新しい人と交流する機会がたくさんあります。ワシントン大学には世界中から学生が集まるため、世界各地から来た人たちと交流することができ、お互いの文化を共有することもできます。特に、シアトルはアメリカでも多様化が非常に進んでいる地域なので、日本食も含めた世界中の料理店が多く立ち並んでいます。
私自身はテニスクラブに参加していました。キャンパス内で行われる週3回の練習のうち好きな時間にコートに出向き、そこにいる人たちと仲良く話しながらテニスをする活動です。日本の部活やサークルのように正式に入会する必要はなく、列に並んでいるときに色々な人と話すというような形でした。アメリカではどんな人でも初対面の人と仲良くする文化があるので、ここでたくさんの友達を作りました。
近場であるカリフォルニア州やオレゴン州、そしてカナダにも旅行に行きました。近くであってもその地域によって価値観や文化に若干の違いがあるので、そうした違いを知ることも楽しめました。

ワシントン大学のアメフトスタジアム
留学を終えて、自分自身の成長を実感したエピソード
授業で学習した実践的な知識が身についた他に、活発にディスカッションする能力が身に着いたと感じます。科学大の授業は、授業を聞き、課題を解き、テスト受験やレポート提出をこなして単位を取得していくことがほとんどだと思います。しかし、ワシントン大学ではそれらに加え、チームで頻繁に議論を行い、プロジェクトを完成させるよう努めたり、オフィスアワーに行き分からなかったことを質問したりと、学究的かつ主体的に目標達成に取り組む必要がありました。こうした経験を積み重ねたことで、留学終了間近の頃には、グループ内での意見交換やアイディアの提案が活発に行えていたり、分からなかったことを隅々まで理解しようとしたりしていることを実感できました。日本に帰ってからも、研究活動などにおいて、分からなかったことについて積極的に質問できるようになったと感じます。
また、クラブ活動やイベントにおいて、アメリカ流の友好的なコミュニケーションを体験したことで、人との交流、特に初対面の人と交流する能力が上達したと感じます。アメリカでは初めて会った人や、店や道端で会った人とでも世間話をすることが頻繁にあります。こうしたコミュニケーションを繰り返してきたことで、日本に帰ってからも、出会いの場で会話をリードできるようになったり、友達との会話を積極的に盛り上げられるようになったりできました。
さらに、当然ながら英語力の上達も実感できました。ディスカッションやクラブ活動を通してリスニング力やコミュニケーション力が身に付き、レポートやエッセイを通してライティング力や論理的思考力が身に着いたと思います。また、バイト先で海外の方を接客する際にも正確な接客英語で対応できるようになりました。
留学費用
6ヶ月間のシアトルでの留学生活において、必要経費のみで合計300万円ほどかかりました。留学初期費用として、ワクチン代、海外保険料、ビザ関連費用などで約35万円、飛行機代が往復で約35万円かかりました(格安航空を選べば往復20万円以内で行けると思います)。私は、キャンパス内学生寮で2クォーター分過ごしましたが、住居費は160万円くらいでした。食費は、週4日ほど自炊をし、1ヶ月で5〜7万円ほどかかりました。外食をする場合は、学内の食堂で一食1500円、一般の料理店で2000〜2500円以上かかります。その他に、教科書代、電車やバスなどの交通費、荷物の海外輸送費などが必要となり、結果的に2クォーター分の留学でやはり300万円ほどかかってしまうと思います。
私は、業務スーパージャパンドリーム財団より計145万円の奨学金を頂いていました。残りの必要経費は両親と自分の間で工面することで同意を得ました。
アメリカのように物価の高い地域ではお金がかかってしまうことは不可避ですが、奨学金等を利用し、ここまで準備をしてきたのだからと、一生に一度のチャンスである留学のメリットを最大限に伝えることにより、金銭的な問題を解消していくことができると思います。
留学先での住居
ワシントン大学では主に、キャンパス内学生寮、キャンパス外学生寮、その他一般のアパートメントやホームステイの3つの選択肢があります。当初は、金銭的にも比較的安くなるキャンパス外学生寮を選ぼうとしていたのですが、現地で一般の住居を探すこととほとんど同じ労力を使うことになり、交通費や通学時間などがあることにも気付いたため、最終的に大学内学生寮に住むことにしました。現地でも、地元の学生以外のほとんどは学内寮に住んでおり、留学生もほぼ全員学内寮に住んでいます。そのため、個人部屋よりも家賃が安くなるシェアルームを選べば、留学生や現地の人たちとルームメイトになり、授業が始まる前に友達を作ることができます。また、探せばあるのかもしれませんが、留学生はルームメイトを選ぶことができなかったと思います。ルームメイトは2〜6人のところが多く、トイレからベッドまで全て共有である代わりに比較的安い家賃で提供されている寮もあれば、ベッド、クローゼット、勉強机などは自分専用の部屋に配備されており、キッチン、冷蔵庫、バスルームなどは共有することになっている寮もあります。私は、最初のクォーターは4人のシェアルームで個室のある寮に住み、最後のクォーターでは6人のシェアルームで個室のある寮に住んでいました。前者は$6500、後者は$4000ほどかかりました。また、前者の$6500のうちの$1500は強制的に学生証に入金させられるもので、学内のお店や食堂などで使えるお金になりました。どちらの寮も学内にあるので通学は非常に楽で、授業後に自分の部屋で静かに勉強することもできました。また、ルームメイトがいると、ルームメイトと仲良くなれるのはもちろんのこと、時々パーティーや食事会が開かれ、新しい友達を作る機会もあります。共有のキッチンとバスルームも綺麗で住むのに問題のない住居であったと思います。
留学先での語学状況
ワシントン大学に留学するためにはTOEFL iBTで76点以上が必要でしたが、私は89点を取ったので英語要件は満たしていました。アメリカ英語で聞き慣れているということもあり、現地の英語の聞き取りに関してひどく困ったことはありませんでしたが、アメリカのスラングや、地名、商品名、店名などの固有名詞などの知識は十分でなかったので、覚えていくのに時間がかかりました。シアトルは多様化が非常に進んでおり、様々なアクセントを持つ人が住んでいるため、その人たちが速く話すと聞き取れないことがしばしばありました。また、授業中の英語に関してですが、コンピュータサイエンスの授業では、スライドが充実しており、使われる単語も聞き慣れているものがほとんどだったので、比較的理解するのに苦労しなかった覚えがあります。一方で、ローマ帝国の歴史や中世世界の歴史の授業では、使われる英語の知識がほとんどなく、聞いたことのない専門用語や固有名詞が飛び交うため、ついていくのに苦労しました。こういった場面で使われる英語は日本にいながら勉強することは大変困難で、留学開始から5ヶ月後くらいにようやく自然に聞き取れ、素早く反応できるようになってきた気がしますが、今でも聞き取れない英語が多く存在します。しかし、逆を言えば、日本で伸ばすことのできなかった自分の英語の部分を伸ばすことができたと捉えることができます。どれだけ対策しても現地で苦労することになると心配するのではなく、むしろ、今までの勉強で不十分だったところを改善する、あるいは現地でしか学べないことを学ぶために現地で苦労する、というスタンスで英語を伸ばしていくことが大切かと思います。
単位認定(互換)、在学期間
私は、情報通信系B3の後期で派遣交換留学に行きましたが、在学期間を伸ばすことはありませんでした。いわゆるB4への進級要件として知られる「特課研所属要件」をB3の前期のうちに達成し、B4で留学期間中に取れなかった単位を取得して卒業要件を達成できることを確認できたので、B3の後期を全て留学に費やしても、これから必要な単位を取得することができれば在学期間を伸ばすことなく卒業できる見込みです。情報通信系では、特課研要件の1つである研究プロジェクトがB3の3Qに開講されますが、系主任の先生と相談し、早期卒業予定の学生と共にB3の1Qに履修させてもらいました。また、留学前に履修した単位を万が一取得できないことを懸念し、留学中に取れない単位(一部必修も含む)をオンラインで受講しても問題ないかを各授業の担当の先生方一人一人にメールをし確認しました。一部必修の授業も含め、オンラインで対応できると申し出てくださった授業がいくつかありましたが、留学直前の成績発表で留学中にオンラインで科学大の必要単位を取らなくても在学期間に影響することがないことが確定し、留学中は現地の授業に集中したいと思ったため、最終的に留学中は科学大の授業を一切受けませんでした。
また、ワシントン大学で取得した単位を科学大で必要な単位に変換しようと考えていた時期がありました。そのためには、留学先で取得した授業と互換性のある科学大の授業を探し、その授業の担当の先生や学務課へ自ら話を持ちかけ、単位認定可能かを協議する必要があります。教科担当の先生方が単位互換に詳しく、成績を提示すればすぐに対応してくださる訳ではないため、手続きが大変になることが予想できたこと、自分の専門科目に認定できそうな授業が見つからなかったこと、単位認定をしてもあまり成績に影響がないことが分かったことなどの理由から、留学中に取得した単位を認定することはありませんでした。
就職活動
派遣交換留学用のビザであるJ1ビザでは、学内のアルバイト及びインターンシップに限り有給で働くことができます。当初留学中に現地でインターンを申し込もうと考えていましたが、そもそも仕事先を探すのが大変であり、勉強や自由時間に支障が出ると考えたため、インターンを申し込むことを断念しました。
個人的に、アメリカでの就職・生活はどのような感じなのか、日本を出てアメリカで生活する方が良いのか、などといった疑問に対する答えを見つけることも、留学の目的の1つとして設定していました。現地の人にアメリカの労働環境や生活状況を聞き、実際に自分で生活した上で思うのは、職場の緊張感が少なく、楽しみながら仕事ができ、健康的に働けることはアメリカで就職することの利点だということです。しかしながら、給料が高い反面物価も高いため、移住して間もない頃は生活が苦しくなることが予想できる点、実力主義が顕著である点、そして、物の清潔さや治安等を考慮した結果、やはり日本で生活する方が自分の求める生活形態に合っていると感じました。家族と疎遠にならずに済む点も理由の1つに挙げられます。とはいえ、留学で得た知識や経験、そして英語力を無駄にすることがないように、外資系の企業など日本にいながら世界と交流することのできる職場で、自分にしかできない仕事に就きたいと考えています。
留学先で困ったこと
アメリカの文化で日本と大きく異なる点の1つに大麻があります。アメリカではほとんどの州で大麻の使用が認められており、ワシントン州もそのうちの1つです。そのため街中で大麻の臭いを嗅ぐことが頻繁にありました。また、大麻は普通のたばこと違い麻酔作用が強く、吸引するとお酒を飲んだ時と似た効果が現れます(副流煙の麻酔作用はほとんどありません)。さらに、大麻の臭いは広範囲に広がり、その場所に残っている時間も長いです。合法とはされていますが、道端で吸う人も多く、不快な思いをすることがしばしばありました。
個人的な体験ですが、最初のクォーターのルームメイトの1人が共有スペースで大麻を吸うようになり、人の食べ物を勝手に盗んで食べたり、ゴミを散らかしたまま何日も放置したりするようになりました。これらのことについて問いただしても、嘘をつき誤魔化し続けるばかりでした。寮を管理している最高責任者に直接対談しに行ったこともありましたが、こうした行為は違法ではないため部屋を変えてもらうことが難しく、大麻に関しては、「お酒と同じなのに何が怖いのか」と逆に詰められることもありました。しかしそこで諦めず、勉強と健康に悪影響があるからという主張を基に何度も訴え続けた結果、次のクォーターから別の寮で生活させてもらえることになりました。
こうしたケースは非常に稀だと思います。現に、新しい寮のルームメイトとは全く問題なく生活できました。私はこのようなトラブルを経験しましたが、決して悪いことばかりではありませんでした。まず、メールでのやり取りや対談を何度も繰り返した結果、法律や大学のルールを学びながら英語で自分の主張を強く伝える能力が飛躍的に伸びました。寮の管理者たちだけではなく、ルームメイトや友達、カウンセラーの人とも相談を繰り返し、英語で状況を簡潔に伝える能力も身に着いたと感じます。今でも、留学中に最も英語力が伸びたのはこの期間であったと感じています。さらに、弱い立場であっても周りの意見に流されず、しっかりと自己主張をする姿勢が身に着きました。アメリカでは大麻擁護派が多く、部屋で大麻を喫煙していた人がいることを理由に部屋を変えてもらう主張はなかなか受け入れられませんでした。しかし、「ワシントン州では大麻は合法であり、お酒と同程度の悪影響しかなかったとしても、体に悪いという事実は変わらず、たまたま北米で大麻が流通してきたため合法になっているだけであり、流通していなければお酒やたばこも違法となっていた世界線もある」という主張で、大麻を危険と感じていることを訴え続け、最終的に寮の最高責任者に処置を講じてもらうことができました。こうした経験から、「主張しなければ権利が失われてしまう」ということを実感し、自分の権利が侵害された際には、法律や文化的背景を自ら学び、誰に対しても臆することなく主張をすることで自分の身を自分で守る、という精神が身に着いたと思います。
留学を希望する後輩へアドバイス
当初は、単純に得意な英語を伸ばしたいという思いから留学に興味を抱いていましたが、調べているうちに、海外の多様な考えを学べること、実践的で総合的な知識を身に着けられること、自立する精神を身につけられることなど、英語力以外にも重要な経験を得られることを知り、ますます留学が魅力的に感じられていきました。実際に留学生活を通してそのような経験をすることができ、当初期待していた以上の恩恵を得ることができたと感じています。
長期間海外に滞在するため、英語でコミュニケーションが取れるか不安に思うかもしれません。しかし、そこで困るということは、まだその部分が不完全であり、成長させることができるということでもあるので、英語を嫌いにならず学び続けることが大切だと思います。また、第一言語である日本語でコミュニケーションが上手くない人は英語であってもコミュニケーションが上手くない傾向にあります。アメリカに行くとフレンドリーな会話が多く、コミュニケーション能力が磨かれることはもちろんだと思います。しかし、自分自身が失敗を恐れず、対話を繰り返し、英語を伸ばしていこうという姿勢を根本的に持たなければ成長に限界があります。そういった面で、普段から人と対話をする能力を磨いていくことは非常に有意義であると思います。
最後に、これは持論になりますが、今後日本に住み続ける限り、極論、英語を勉強する必要はないと思います。海外の人とお話しする機会があっても、翻訳アプリを使えば意思疎通を図ることは容易ですし、中国語やスペイン語など、他に世界で多く使われている言語もあり、英語だけを極める必要性を問われた場合、反論する術はあまりありません。しかし、世界で広く話されている英語を勉強することで、世界中の情報、文化、考えを直接理解することができるようになります。学会や国際的な職場などで道具として使う為だけに英語を学ぶ人は多くいます。しかし、世界共通語となりつつある英語を学ぶことで、より多くの国の人と英語で会話することができ、その国の文化をよりよく知ることができます。これは、翻訳アプリを通してでも可能ですが、自分で英語を話すことで、1人の「人」として「人」と対話したいという姿勢を見せなければ、生産的に会話や議論が進むことは見込めないと思います。さらに、世界中の人々が、その国の情報を英語で発信するため、その国の映画、歴史、政治、食事、ユーモア、話し方など、様々な文化を知る機会に繋がり、それらをもっと知りたいと思えるようになります。さらに、国際的なリーダーたちのほとんどは英語が話せます。ウクライナのゼレンスキー大統領、イスラエルのネタニヤフ首相、フランスのマクロン大統領など、第一言語が英語でない国のリーダーたちも英語を堪能に話します。日本人でも、ソフトバンクの孫正義氏や日本銀行の植田総裁など、世界を相手にするリーダーたちは英語で議論ができる重要性を認識しており、英語を流暢に話します。世界人口の半分はバイリンガルといわれるこの時代に、世界と対等に競争できる国にするためには、日本人でありながらも英語で活発に議論ができる人材が必要になってくると確信しています。
この体験談の留学・国際経験プログラム情報
他の関連する体験談
-

派遣交換留学 ミラノ工科大学 2023年9月5日~2024年8月16日
- イタリア共和国
- ミラノ工科大学
- 2023年9月5日~2024年8月16日
- 授業履修
-

派遣交換留学 ジョージア工科大学 2024年8月19日~2024年12月12日
- アメリカ合衆国
- ジョージア工科大学
- 2024年8月19日~2024年12月12日
- 授業履修
-

派遣交換留学 シンガポール国立大学 2023年8月7日~2024年5月12日
- シンガポール共和国
- シンガポール国立大学
- 2023年8月7日~2024年5月12日
- 授業履修
-

派遣交換留学 アアルト大学 2024年8月23日~2025年7月18日
- フィンランド共和国
- アアルト大学
- 2024年8月23日~2025年7月18日
- 授業履修
-

派遣交換留学 ウィーン工科大学 2024年2月14日~2025年2月28日
- オーストリア共和国
- ウィーン工科大学
- 2024年2月14日~2025年2月28日
- 授業履修
-

派遣交換留学 アアルト大学 2023年10月1日~2024年6月11日
- フィンランド共和国
- アアルト大学
- 2023年10月1日~2024年6月11日
- 研究
-

派遣交換留学 イスタンブール工科大学 2024年9月25日~2025年6月23日
- トルコ共和国
- イスタンブール工科大学
- 2024年9月25日~2025年6月23日
- 授業履修
-

派遣交換留学 ボローニャ大学 2025年2月14日~2025年8月13日
- イタリア共和国
- ボローニャ大学
- 2025年2月14日~2025年8月13日
- 授業履修
-

派遣交換留学 バンドン工科大学 2024年8月31日~2025年1月10日
- インドネシア共和国
- バンドン工科大学
- 2024年8月31日~2025年1月10日
- 授業履修
-

派遣交換留学 アーヘン工科大学 2023年9月15日~ 2024年3月24日
- ドイツ
- アーヘン工科大学
- 2023年9月15日~ 2024年3月24日
- 授業履修
-

派遣交換留学 デンマーク工科大学 2023年8月21日~ 2024年2月8日
- デンマーク
- デンマーク工科大学
- 2023年8月21日~ 2024年2月8日
- 授業履修
-

派遣交換留学 パリ建築ラヴィレット校 2022年8月29日~ 2023年8月26日
- フランス
- パリ建築大学ヴィレット校
- 2022年8月29日~ 2023年8月26日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 デルフト工科大学 2022年8月9日~ 2023年8月28日
- オランダ王国
- デルフト工科大学
- 2022年8月9日~ 2023年8月28日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ミュンヘン工科大学 2022年10月4日~2023年8月20日
- ドイツ
- ミュンヘン工科大学
- 2022年10月4日~2023年8月20日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 シャルマーズ工科大学 2022年8月23日~ 2023年6月4日
- スウェーデン王国
- シャルマーズ工科大学
- 2022年8月23日~ 2023年6月4日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ウプサラ大学 2022/8/29~ 2023/6/4
- スウェーデン
- ウプサラ大学
- 2022年8月29日~ 2023年6月4日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ヨーク大学 2023/1/12~2023/6/25
- イギリス
- ヨーク大学
- 2023/1/12~2023/6/25
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 国立台湾大学 2023/2/12~2023/6/10
- 台湾
- 国立台湾大学
- 2023/2/12~2023/6/10
- 研究
-

派遣交換留学 ハノーファー大学 2022年10月13日~2023年3月31日
- ドイツ
- ハノーファー大学
- 2022年10月13日~2023年3月31日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 スイス連邦工科大学 ローザンヌ校 2021/8/17~2022/7/14
- スイス連邦
- スイス連邦工科大学 ローザンヌ校(EPFL)
- 2021/8/17~2022/7/14
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ベルリン工科大学 2022/3/1~2023/1/17
- ドイツ
- ベルリン工科大学
- 2022/3/1~2023/1/17
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ウィーン工科大学 2022年2月7日~2023年1月31日
- オーストリア共和国
- ウィーン工科大学
- 2022年2月7日~2023年1月31日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 カセサート大学 2022年8月8日~2022年12月14日
- タイ
- カセサート大学
- 2022年8月8日~2022年12月14日
- 授業履修
-

派遣交換留学 シュツットガルト大学 2021年9月1日~2022年2月28日
- ドイツ
- シュツットガルト大学
- 2021年9月1日~2022年2月28日
- 国際交流・異文化体験、語学、授業履修、研究、スキルアップ
-

派遣交換留学 ミラノ工科大学 2021/9/1~2022/8/30
- イタリア
- ミラノ工科大学
- 2021/9/1~2022/8/30
- 国際交流・異文化体験、語学、授業履修、研究、スキルアップ
-

派遣交換留学 ソウル国立大学 2021年9月1日~2022年2月28日
- 大韓民国
- ソウル国立大学
- 2021年9月1日~2022年2月28日
- 授業履修、研究
-
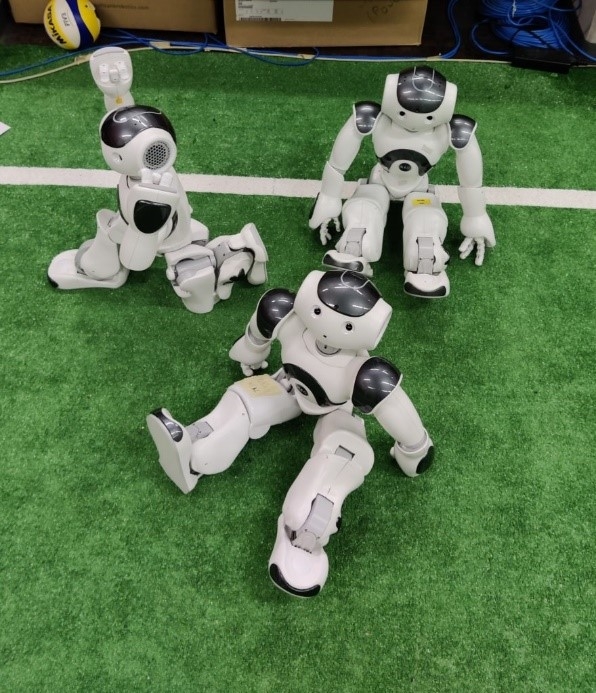
派遣交換留学 スイス連邦工科大学チューリッヒ校 2021年9月1日~2022年1月25日
- スイス連邦
- スイス連邦工科大学チューリッヒ校
- 2021年9月1日~2022年1月25日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 スウェーデン王立工科大学 2021年8月22日~2022年1月17日
- スウェーデン王国
- スウェーデン王立工科大学
- 2021年8月22日~2022年1月17日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 デンマーク工科大学 2021年8月23日~2021年12月23日
- デンマーク王国
- デンマーク工科大学
- 2021年8月23日~2021年12月23日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 スイス連邦工科大学チューリッヒ校 2021年9月1日~2022年2月16日
- スイス連邦
- スイス連邦工科大学チューリッヒ校
- 2021年9月1日~2022年2月16日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ウィーン工科大学 2019年10月1日~2020年1月31日
- オーストリア共和国
- ウィーン工科大学
- 2019年10月1日~2020年1月31日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ウィーン工科大学 2019年3月~2020年2月
- オーストリア共和国
- ウィーン工科大学
- 2019年3月~2020年2月
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 スイス連邦工科大学ローザンヌ校 2018年8月15日~2019年7月23日
- スイス連邦
- スイス連邦工科大学ローザンヌ校
- 2018年8月15日~2019年7月23日
- 授業履修、研究
-
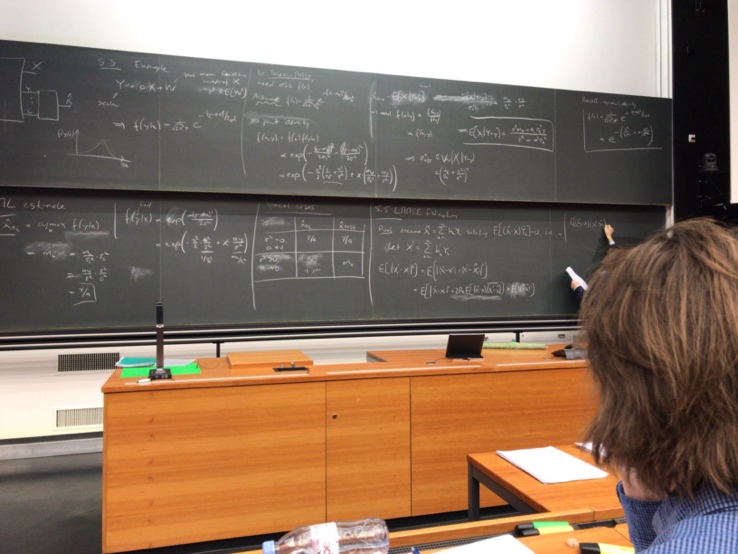
派遣交換留学 スイス連邦工科大学チューリッヒ校 2019年9月1日~2020年8月30日
- スイス連邦
- スイス連邦工科大学チューリッヒ校
- 2019年9月1日~2020年8月30日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 スイス連邦工科大学チューリッヒ校 2018年9月1日~2019年8月30日
- スイス連邦
- スイス連邦工科大学チューリッヒ校
- 2018年9月1日~2019年8月30日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 スイス連邦工科大学チューリッヒ校 2017年9月2日~2018年2月9日
- スイス連邦
- スイス連邦工科大学チューリッヒ校
- 2017年9月2日~2018年2月9日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ミラノ工科大学 2019年2月14日-2020年2月11日
- イタリア共和国
- ミラノ工科大学
- 2019年2月14日-2020年2月11日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ミラノ工科大学 2016年9月15日~2017年8月25日
- イタリア共和国
- ミラノ工科大学
- 2016年9月15日~2017年8月25日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ミラノ工科大学 2016年10月1日~2017年2月28日
- イタリア共和国
- ミラノ工科大学
- 2016年10月1日~2017年2月28日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ボローニャ大学 2019年9月8日~2020年3月3日
- イタリア共和国
- ボローニャ大学
- 2019年9月8日~2020年3月3日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ポン・ゼ・ショセ 2016年8月7日~2017年2月19日
- フランス共和国
- ポン・ゼ・ショセ
- 2016年8月7日~2017年2月19日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 パリ建築大学ヴィレット校 2017年1月31日~2017年7月7日
- フランス共和国
- パリ建築大学ヴィレット校
- 2017年1月31日~2017年7月7日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ストラスブール大学 2016年8月13日~2017年5月16日
- フランス共和国
- ストラスブール大学
- 2016年8月13日~2017年5月16日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 アール・ゼ・メティエ 2017年8月29日~2018年2月7日
- フランス共和国
- アール・ゼ・メティエ
- 2017年8月29日~2018年2月7日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ベルリン工科大学 2019年9月1日~2020年7月31日
- ドイツ連邦共和国
- ベルリン工科大学
- 2019年9月1日~2020年7月31日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ベルリン工科大学 2018年9月1日~2019年3月24日
- ドイツ連邦共和国
- ベルリン工科大学
- 2018年9月1日~2019年3月24日
- 授業履修、研究
-
派遣交換留学 アーヘン工科大学 2018年9月4日-2019年8月31日
- ドイツ連邦共和国
- アーヘン工科大学
- 2018年9月4日-2019年8月31日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 アーヘン工科大学 2017年9月1日~2018年7月31日
- ドイツ連邦共和国
- アーヘン工科大学
- 2017年9月1日~2018年7月31日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 シュツッツガルト大学 2019年9月2日-2020年3月29日
- ドイツ連邦共和国
- シュツッツガルト大学
- 2019年9月2日-2020年3月29日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ミュンヘン工科大学 2019年10月1日~2020年3月31日
- ドイツ連邦共和国
- ミュンヘン工科大学
- 2019年10月1日~2020年3月31日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ミュンヘン工科大学 2018年10月1日~2019年3月26日
- ドイツ連邦共和国
- ミュンヘン工科大学
- 2018年10月1日~2019年3月26日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ミュンヘン工科大学 2017年10月1日~2018年3月1日
- ドイツ連邦共和国
- ミュンヘン工科大学
- 2017年10月1日~2018年3月1日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ミュンヘン工科大学 2017年10月1日~2018年9月15日
- ドイツ連邦共和国
- ミュンヘン工科大学
- 2017年10月1日~2018年9月15日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 デルフト工科大学 2017年8月17日~2018年7月26日
- ドイツ連邦共和国
- デルフト工科大学
- 2017年8月17日~2018年7月26日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 デルフト工科大学 2019年8月27日~2020年9月5日
- ドイツ連邦共和国
- デルフト工科大学
- 2019年8月27日~2020年9月5日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ゲント大学 2018年9月10日~2019年7月6日
- ベルギー王国
- ゲント大学
- 2018年9月10日~2019年7月6日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ヨーク大学 2017年9月18日~2018年6月22日
- 英国
- ヨーク大学
- 2017年9月18日~2018年6月22日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ヨーク大学 2018年9月20日~2019年6月25日
- 英国
- ヨーク大学
- 2018年9月20日~2019年6月25日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 デンマーク工科大学 2017年9月4日~2018年5月30日
- デンマーク王国
- デンマーク工科大学
- 2017年9月4日~2018年5月30日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 デンマーク工科大学 2017年9月4日~2017年12月23日
- デンマーク王国
- デンマーク工科大学
- 2017年9月4日~2017年12月23日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 シャルマーズ工科大学 2020年1月17日~2020年6月12日
- スウェーデン王国
- シャルマーズ工科大学
- 2020年1月17日~2020年6月12日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 シャルマーズ工科大学 2017年1月16日~2017年8月26日
- スウェーデン王国
- シャルマーズ工科大学
- 2017年1月16日~2017年8月26日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 スウェーデン王立工科大学 2019年8月16日~2020年6月5日
- スウェーデン王国
- スウェーデン王立工科大学
- 2019年8月16日~2020年6月5日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 スウェーデン王立工科大学 2018年8月20日~2019年6月21日
- スウェーデン王国
- スウェーデン王立工科大学
- 2018年8月20日~2019年6月21日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ラッペンランタ・ラハティ工科大学 2019年8月28日~2020年5月31日
- フィンランド共和国
- ラッペンランタ・ラハティ工科大学
- 2019年8月28日~2020年5月31日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 アアルト大学 2017年8月15日~2018年7月1日
- フィンランド共和国
- アアルト大学
- 2017年8月15日~2018年7月1日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 アアルト大学 2018年8月29日~2019年6月18日
- フィンランド共和国
- アアルト大学
- 2018年8月29日~2019年6月18日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 カリフォルニア大学バークレー校 2018年8月16日~2019年5月22日
- アメリカ合衆国
- カリフォルニア大学バークレー校
- 2018年8月16日~2019年5月22日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 カリフォルニア大学バークレー校 2019年8月15日~2020年3月15日
- アメリカ合衆国
- カリフォルニア大学バークレー校
- 2019年8月15日~2020年3月15日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ワシントン大学 2019年1月6日-2020年6月22日
- アメリカ合衆国
- ワシントン大学
- 2019年1月6日-2020年6月22日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ワシントン大学 2017年9月13日~2018年6月29日
- アメリカ合衆国
- ワシントン大学
- 2017年9月13日~2018年6月29日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ジョージア工科大学 2016年8月12日~2017年5月27日
- アメリカ合衆国
- ジョージア工科大学
- 2016年8月12日~2017年5月27日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ジョージア工科大学 2018年1月1日~2018年5月4日
- アメリカ合衆国
- ジョージア工科大学
- 2018年1月1日~2018年5月4日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 メルボルン大学 2016年7月7日~2017年7月15日
- オーストラリア連邦
- メルボルン大学
- 2016年7月7日~2017年7月15日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 メルボルン大学 2017年7月15日~2017年11月29日
- オーストラリア連邦
- メルボルン大学
- 2017年7月15日~2017年11月29日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 インド工科大学マドラス校 2019年7月15日~2020年2月28日
- インド
- インド工科大学マドラス校
- 2019年7月15日~2020年2月28日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 南洋理工大学 2018年8月7日~2019年4月30日
- シンガポール共和国
- 南洋理工大学
- 2018年8月7日~2019年4月30日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 シンガポール国立大学 2017年8月1日~2017年12月19日
- シンガポール共和国
- シンガポール国立大学
- 2017年8月1日~2017年12月19日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 シンガポール国立大学 2019年8月5日~2020年5月2日
- シンガポール共和国
- シンガポール国立大学
- 2019年8月5日~2020年5月2日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 キングモンクット工科大学トンブリ校 2016年8月1日~2016年12月26日
- タイ王国
- キングモンクット工科大学トンブリ校
- 2016年8月1日~2016年12月26日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 タマサート大学 2015年8月4日~2016年5月31日
- タイ王国
- タマサート大学
- 2015年8月4日~2016年5月31日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ガジャマダ大学 2015年8月18日~2016年9月31日
- インドネシア共和国
- ガジャマダ大学
- 2015年8月18日~2016年9月31日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 バンドン工科大学 2017年1月11日~2018年3月31日
- インドネシア共和国
- バンドン工科大学
- 2017年1月11日~2018年3月31日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 バンドン工科大学 2017年8月10日~2017年12月20日
- インドネシア共和国
- バンドン工科大学
- 2017年8月10日~2017年12月20日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 デラサール大学 2017年9月1日~2018年8月30日
- フィリピン共和国
- デラサール大学
- 2017年9月1日~2018年8月30日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 国立台湾大学 2019年2月12日~2020年1月19日
- 台湾
- 国立台湾大学
- 2019年2月12日~2020年1月19日
- 授業履修、研究
-
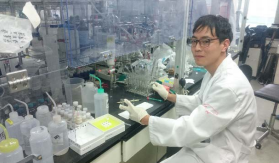
派遣交換留学 ソウル国立大学 2017年7月8日~2017年9月29日
- 大韓民国
- ソウル国立大学
- 2017年7月8日~2017年9月29日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 ソウル国立大学 2017年8月30日~2018年7月7日
- 大韓民国
- ソウル国立大学
- 2017年8月30日~2018年7月7日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 清華大学 2018年9月13日~2019年1月14日
- 中華人民共和国
- 清華大学
- 2018年9月13日~2019年1月14日
- 授業履修、研究
-

派遣交換留学 清華大学 2018年9月20日~2019年6月25日
- 中華人民共和国
- 清華大学
- 2018年9月20日~2019年6月25日
- 授業履修、研究