研究
研究
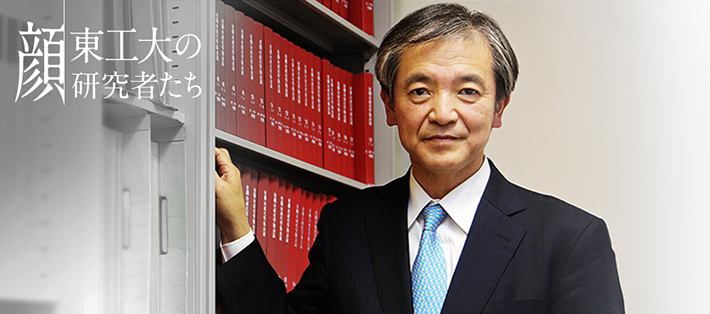
vol. 19
理学院 化学系 教授
鈴木啓介(Keisuke Suzuki)
医薬品やプラスチックなどの製品は、われわれ現代人の健康や日常生活に欠かせない。これらは有機化合物と呼ばれ、その特徴は「炭素」から成る基本骨格にある。炭素は炭素同士や水素、酸素、窒素などと結合しやすく、それらの組合せででき上がる有機化合物の種類は無限ともいえる。
実は、私たち人間の体も、水分やミネラルを除けば、大半は有機化合物からできている。一人あたり60兆個とも言われる細胞の内外は核酸、タンパク質、糖質、脂肪など多様な有機化合物の織りなす生命活動の場となっている。しかし、そうした活動の恒常性が乱れた時、つまり病気になった時に、我々の先祖は太古の昔から天然の恵みに救いを求めてきた。実際、動植物や微生物が作り出す天然有機化合物には特別な薬効があるものがあるが、その一方で天然からの入手が困難で、希少なものも少なくない。

そのような場面で力を発揮するのが「有機合成」、つまり人工的に行われる有機化合物の合成だ。1828年、有機化学とは生命体が、無機化学とは鉱物が作り出すものであると厳然と分かれていた時代に、ドイツの化学者・ヴェーラー[用語1]は、試験管の中で無機物であるシアン酸アンモニウムを加熱するうちに、有機化合物である尿素が得られることを偶然発見。これにより有機化合物も人工的に合成が可能であることが立証され、以後研究が盛んになった。私たちの身の回りでも、石炭や石油の化石原料から人工的に作り出された多彩な有機化合物、繊維などの素材や有機ELなどの機能性材料がなくてはならないものとなっている。また、健康福祉関係でも天然有機化合物の構造をヒントとして設計、合成された医薬品等も多い。
「毒と薬は紙一重と言いますが、ある生理活性をもつ天然有機化合物が見つかっても、そこに毒性が付随することが多いんですね。ところが、その分子構造に手を加えていくと、活性向上、毒性低減、という理想形に変貌を遂げる可能性がある。たとえば、昨秋のノーベル医学生理学賞に輝いた大村智博士のイベルメクチンという化合物は、何億人ものアフリカの人々をオンコセルカ症による失明の危機から救った話で有名になりました。実はこれは静岡県の土から採取された微生物の作る化合物(エバーメクチン)をもとに、有機合成で水素を付加して改良したものです。こうしたことを実現するポテンシャルが有機合成の魅力です。」
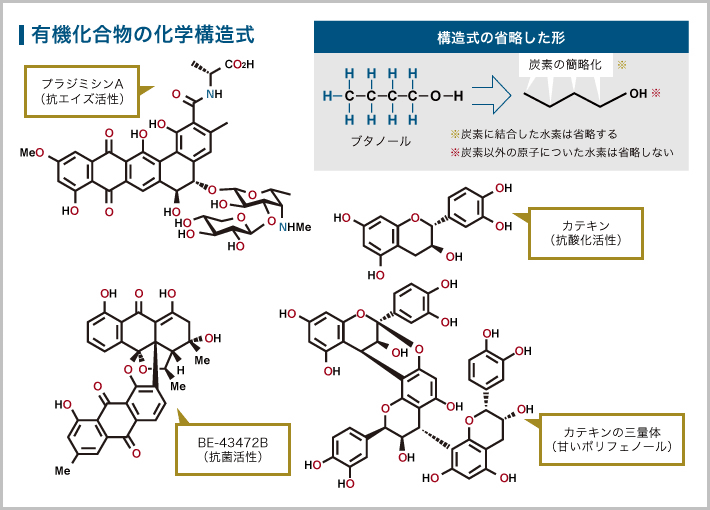
合成した天然有機化合物の例
さらに、上の例のように天然由来の化合物を構造修飾するばかりでなく、ありふれた簡単な化合物から出発し、目的の化合物の合成を一から目指すこともある。これを全合成という。目的の構造が複雑な場合、複数の反応段階が必要なので、これを多段階合成という。複雑な構造の化合物の合成には、入手容易な出発物質を選択し、正しい反応を順序よく適用し、強力な炭素結合を組み替えて目的物の構造を作り上げていく必要があるので、いずれにしても一筋縄のことではない。この研究者泣かせの難題に真っ向から挑んできたのが、有機合成の最前線に立つ鈴木であった。
有機合成の研究には、大別して二つの側面がある。すなわち、合成に用いる化学反応自体を開発する研究(反応開発)と、それらの合成反応をどのように組み合わせて目的物を作るかという研究(合成研究)である。鈴木は、反応開発において、ベンザインやニトリルオキシドと呼ばれる高反応性の化学種を活用し、画期的な炭素骨格構築法や立体制御法[用語2]を編みだす。一方、合成研究においては、糖質やテルペン(植物や昆虫、菌類などの働きにより生成される生体物質)、ポリケチド[用語3]など、異なる生合成経路に由来する構造単位が複雑に絡み合った「高次構造天然有機化合物」を標的として、数々の合成を実現してきた。
有機合成とは、端的に言うとジグソーパズルみたいなもの、と例える鈴木。あるパズルの完成形が作りたいとしたときに、頭の中でそれを解体していって、これなら行けそうだというピースの組合せ方を思い描く。そこから実際に組み立てていくのが合成だ。しかし、バラバラのところから完成形に仕上げるのは簡単ではない。そのためには以下の3つの要素が重要であるという。
第一には、基本骨格の組み立て。冒頭にも述べたとおり、有機化合物の骨格は基本的に「炭素」でできている。しかし、それにも多様なものが存在し、リノール酸など高級脂肪酸の「鎖式骨格」や、ステロイドなどの「環式骨格」などがある。合成の第一歩は、作りたい分子の基本骨格の特徴を把握し、その構築方法を模索するところに始まる。
二つ目は「官能基」だ。官能基とは特定の原子の集合体で、炭素鎖に付随して機能を担い、分子に特定の化学的性質を与える役割を果たす。有機分子を魚に例えれば、炭素鎖が「骨組み」、官能基は「肉付け」ということになる。
そして三つ目が、「立体化学の制御」。鈴木はこれを「左ヒラメの右カレイ」の例えで解説する。
「ヒラメとカレイ。見た目は左と右の関係ですが、似て非なるものです。そこをきちんと作り分けないといけない。ヒラメが作りたいとしたら、左仕様の骨格を作り、その肉付けをして、正しく仕上げなければいけない。最終的に「骨格、肉付け、左右」と三位一体で完成させるというのが、合成のキーポイントなんです。」
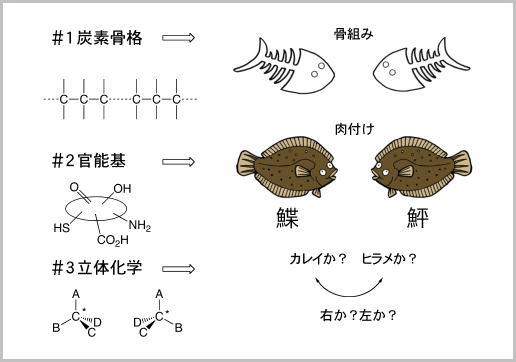
合成の三要素

簡単そうに思えるが、合成には各所に落とし穴が用意され、すんなりと行くことはないという。鈴木が東大在学時から恩師と仰ぐ向山光昭(むかいやまてるあき)[用語4]は、当時「反応開発はゼロから1を産み出す研究、合成研究は1から10につなげる応用の場」として、新反応の開発に力点を置いていた。鈴木は学生時代に薫陶を受け、反応開発に取り組んだが、面白いのは、その厳しい鍛錬の場において密かに合成研究を行っていたことだ。そのヤミ実験(?)の成果は論文として日の目を見ることはなかったが、最初に職を得て研究生活をスタートした慶應大学では、晴れてこれらの両方を思い切り展開するようになったという。
要するに、反応と合成は表裏一体のもので、どちらが欠けても成り立たないと言うことだ。登山で言えば、反応は登山装備、合成計画はルート選択に相当する。優れた装備を用意し、正しいルートを選択し、初めて登山が可能になる。しかも、最後の最後にもう一つ、大きな難関が待ち受けている、と鈴木は続ける。
「我々が取り組んでいる複雑な分子は気位が高く、頑として他を寄せつけないようなところがあります。登山に例えるなら、未踏峰の登頂に向けた最後のベースキャンプから道が閉ざされているという場面でしょうか。ほとんど頂上の直下にいるのに、どこからも登れない歯がゆい思いです。しかし、何度かそこを突破した経験から、そこに醍醐味を感じるようにもなりました。なぜなら、登頂成功は無上の喜びですから。」
この最後のむずかしさは、目的物を純粋に取得することにもある。複雑精緻な構造の天然有機化合物は、化学的に不安定であったり、特別な性質により精製手段がなかったりということもある。また、多くの有機合成は有機溶媒の中で行うのに対し、目的物が水溶性である場合には、最後の精製に特別な難しさがある。この乖離は大きく、その意味で複雑な天然物合成の研究はまだ発展途上だと言う。
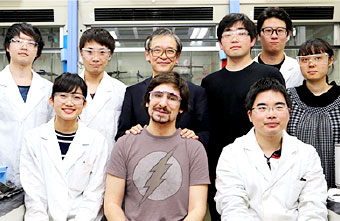
「自然界で生み出され、何らかの役割を営々と果たしている分子には、なぜか魅力的な構造のものが多いんです。私たちが目指しているのは、これらの分子たちを有機合成の力で自由自在に作り上げることです。自然は、こうした分子を難なく作っているように見えるのに、いざ私たちが合成しようとすると、本当に試行錯誤の連続です。思うにまかせずいると、自分達の合成力が自然界から試されているかのように思えてくるんです。しかし、難しいからこそ、よけいに魅せられます。毎日が知的チャレンジです」といって、現在、ベニハナの色素や抗生物質の合成などに取り組んでいる。
そんな鈴木も、長年にわたる研究が評価され、2015年には日本学士院賞を受賞している。
「研究者として最終コーナーに差し掛かったところで栄誉ある賞をいただけたことはたいへん感慨深いですね。もうひと頑張り、と励みになりました」
鈴木はいつも恩師、向山光昭の言葉にも励まされると言う。『信深は新』、『素直さと明るさと情熱を』。また、"適齢期"を過ぎてからの海外滞在以来、師と仰ぐスイス連邦工科大学チューリッヒ校のディーター・ゼーバッハ名誉教授の言葉『研究は計画できるが、結果は計画できない』が好きだ。
「Curiosity-Driven Research。計画通りにいった研究はむしろ失敗かもしれない。計画通りに行くなら、研究をしなくても良かった。学生たちには、教科書(先人の智恵)を十分学んだ上で、そこに留まらず、斬新な仮説を立てて実験に取り組んで欲しい。実験はいくら失敗しても構わない、予想外の結果にこそ、新たな鉱脈との出会いがあるのだから」。
鈴木の言葉の端々に、力強く、揺るぎない信念が感じられた。知的挑戦の日々はまだまだ続く。
用語説明
[用語1] フリードリヒ・ヴェーラー: (1800~1882)1882年シアン酸アンモニウムを加熱中に尿素が結晶化しているのを偶然発見。無機物から人工的に有機物を合成できることを初めて世に示した。
[用語2] 立体制御法: 炭素原子に4つの異なる置換基が結合した場合、これを不斉炭素原子という。この場合、置換基の空間的関係により、右手と左手の如く、互いに鏡像関係にある異性体(鏡像異性体)が存在する。不斉炭素原子をn個持つ化合物には、最大で2n個の異性体(ジアステレオ異性体)が存在するが、これらを分離することは困難が伴う。しかし、近年、化学反応を通じ、必要な異性体を選択的に得る手法が進展した。これを立体制御法と呼ぶ。
[用語3] ポリケチド: 微生物が生産する多くの環状構造をもつ化合物。アセチルCoA、マロニルCoAなどからポリケトン鎖を合成後、複合的に生合成された多様な化合物の総称。医薬、農薬などの有用化合物も数多い。
[用語4] 向山光昭: (1927~ )向山アルドール反応の開発をはじめ、様々な独創的な有機合成反応の開発に携わる。文化勲章受章者。東京大学名誉教授。東京工業大学栄誉教授。東京理科大学名誉教授。前社団法人北里研究所基礎研究所名誉所員。

鈴木啓介(Keisuke Suzuki)
理学院 化学系 教授
スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。
2016年6月掲載